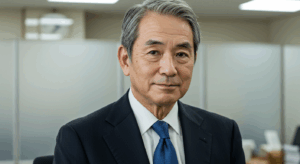なぜ不動産投資が節税対策になるのか?所得税の観点から税理士が解説

皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週水曜日に、経営者なら知っておきたい「節税対策」についての知識を解説しています。
中小企業の経営者の皆様にとって、事業の成長と並んで重要な課題の一つが「節税」ではないでしょうか。
様々な節税策が考えられますが、今回は「不動産投資」を活用した所得税の節税について解説します。
税理士としての知見と実務経験に基づき、個人の所得税負担を軽減する仕組みに焦点を当てていきます。
不動産投資における所得税節税の基本:減価償却と損益通算
不動産投資による所得税節税の基本的な考え方は、「不動産所得の赤字」を他の所得(例えば給与所得や事業所得)と合算し、
課税対象となる所得全体を圧縮する「損益通算」という仕組みを活用することです。
そして、この不動産所得の赤字を意図的に作り出す上で鍵となるのが「減価償却」です。
減価償却とは? 現金支出を伴わない経費の活用
減価償却とは、建物などの固定資産が時間とともに価値を減少させていくという考え方に基づき、
その価値の減少分を一定期間にわたって経費として計上できる制度です。
不動産投資における減価償却の大きなポイントは、現金の支出を伴わない経費であるという点です。
不動産を購入する際には、もちろん土地建物の購入代金という大きな支出が発生します。
しかし、一度購入してしまえば、その後は減価償却費として毎年経費計上できるものの、実際に財布からお金が出ていくわけではありません。
この「帳簿上の経費」を計上することで、不動産所得を圧縮し、結果として所得税の節税につなげることができるのです。
減価償却費の計算方法
減価償却費は、基本的に以下の計算式で算出されます。
減価償却費=建物の取得価格×償却率
この償却率は、資産の種類や「法定耐用年数」に応じて定められています。
具体的な計算例:中古木造アパート(建物価格4,000万円)のケース
仮に、建物価格4,000万円の中古木造アパートを購入し、この物件の税務上の耐用年数が4年で償却できるケースを考えてみましょう(土地の価格はここでは考慮しません)。
- 1年目
- 減価償却費:4,000万円 ÷ 4年 = 1,000万円
- このアパートから年間200万円の家賃収入があり、減価償却費以外の経費も200万円かかったとします。
- 不動産所得:家賃収入200万円 – 経費200万円 – 減価償却費1,000万円 = マイナス1,000万円
このマイナス1,000万円の不動産所得を、例えば給与所得6,000万円と損益通算すると、課税所得は5,000万円となります。
仮に所得税・住民税の合計税率が55%の方であれば、1,000万円 × 55% = 550万円もの節税効果が期待できる計算になります。
- 2年目~4年目
同様に、毎年1,000万円の減価償却費を計上できます(最終年は備忘価額1円を残す調整あり)。
4年間で建物価格4,000万円のほぼ全額を経費として計上するイメージです。
このように、現金の支出を伴わない減価償却費を利用して不動産所得を赤字にし、
他の所得と損益通算することで所得税を圧縮するのが、不動産投資による節税の基本的な仕組みです。
ただし、この手法は、ある程度の給与所得などがあり、支払うべき税金が多い方にとって特に有効です。
所得が低い、あるいは赤字の場合は、そもそも節税する税金がないため、効果は薄くなります。
減価償却費を最大化する鍵:中古資産の耐用年数
前述の例では、耐用年数4年という短い期間で償却できるケースを挙げました。
なぜこのような短期間での償却が可能なのでしょうか。それは「中古資産の耐用年数」の考え方がポイントとなります。
法定耐用年数と中古資産の耐用年数
新品の資産には、それぞれ法で定められた「法定耐用年数」があります。
例えば、木造の建物であれば22年、鉄筋コンクリート造であれば47年といった具合です。
新築物件の場合は、この法定耐用年数に基づいて減価償却費を計算するため、1年あたりの減価償却費は比較的少額になります。
しかし、中古資産の場合は、以下の簡便的な計算方法で耐用年数を算出することが認められています。
- 法定耐用年数の全部を経過した資産
中古資産の耐用年数=法定耐用年数×20% (計算結果の1年未満の端数は切り捨て) - 法定耐用年数の一部を経過した資産
中古資産の耐用年数=(法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×20%) (計算結果の1年未満の端数は切り捨て)
なぜ中古木造アパート(築22年以上)が節税に有利なのか
所得税の節税を目的とした不動産投資でよく活用されるのが、築年数が法定耐用年数(木造なら22年)を経過した中古木造アパートです。
例えば、築25年の木造アパートの場合、
中古資産の耐用年数=22年×20%=4.4年
小数点以下は切り捨てるため、耐用年数は「4年」となります。
これにより、建物の取得価格を4年間という短期間で集中的に経費計上(減価償却)することが可能になるのです。
初期に多くの減価償却費を計上することで、損益通算による節税効果を早期に、かつ大きく享受できるというメリットがあります。
出口戦略の重要性:売却時の税金と税率差
4年間で減価償却を終えてしまうと、それ以降は大きな経費を計上できなくなります。
節税効果を享受できたとしても、投資した資金(建物価格4,000万円)を回収できなければ、トータルで見て得をしたことにはなりません。
そこで重要になるのが「売却」という出口戦略です。
不動産売却益にかかる「譲渡所得」
土地や建物を売却して得た利益には、「譲渡所得」として税金がかかります。
これは、給与所得や不動産賃貸収入などとは別に計算される「分離課税」という方式が取られます。
譲渡所得の計算方法は以下の通りです。
譲渡所得=収入金額(売却金額)−(取得費(購入金額など)+譲渡費用(売却にかかった費用))
ここで注意が必要なのは「取得費」です。建物の取得費は、それまでに計上した減価償却費の累計額を差し引いた金額(帳簿価額)となります。
先ほどの4年償却の例で言えば、4年後には建物の帳簿価額はほぼゼロ(備忘価額1円)になっています。
譲渡所得の税率:長期譲渡と短期譲渡
譲渡所得にかかる税率は、不動産の所有期間によって異なります。
- 長期譲渡所得
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える場合- 税率:20.315%(所得税15.315% + 住民税5%) ※復興特別所得税を含む
- 短期譲渡所得
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の場合- 税率:39.63%(所得税30.63% + 住民税9%) ※復興特別所得税を含む
節税のポイントは「税率差」
所得税の節税スキームの核心は、損益通算で節税した際の税率と、不動産を売却した際の譲渡所得の税率の「差」にあります。
例えば、給与所得が高く、損益通算時に所得税・住民税合わせて55%の税率が適用されていた方が、5年を超えて所有した不動産を売却し、
長期譲渡所得として20.315%の税率で済んだ場合、その差額(約34.685%)が実質的な節税メリットとなるのです。
国内中古不動産を活用した節税スキームの具体例
ここで、国内の中古木造アパートを用いた所得税節税スキームの具体的な効果を見てみましょう。
- 前提条件
- 給与収入:6,000万円(所得税・住民税の合計税率55%と仮定)
- 購入物件:中古木造アパート(建物4,000万円、土地2,000万円で購入)
- 償却期間:4年(毎年1,000万円の減価償却費を計上)
- 売却:5年経過後に建物部分を4,000万円で売却(土地の売却益はここでは無視)
- 売却費用:500万円
- 途中の家賃収入や経費は簡略化のため考慮しない
- 4年間の減価償却による節税効果
- 減価償却費総額:1,000万円/年 × 4年間 = 4,000万円
- 節税額:4,000万円 × 55% = 2,200万円
- 売却時の譲渡所得税 (5年超所有のため長期譲渡)
- 建物の取得費は減価償却によりほぼゼロとします。
- 譲渡所得:売却金額4,000万円 – 取得費0円 – 売却費用500万円 = 3,500万円
- 譲渡所得税:3,500万円 × 20.315% ≒ 711万円
- トータルの節税効果
- 節税額2,200万円 – 譲渡所得税711万円 = 約1,489万円
これが、国内の中古不動産を活用した所得税節税の一般的なスキームです。
実際には家賃収入やその他の経費、土地の売却なども考慮に入れる必要がありますが、基本的な考え方はこのようになります。
国外不動産投資の現状と注意点
以前は、国外、特にアメリカなどの中古不動産を活用した節税手法が注目されていました。
これは、海外では中古不動産市場が確立しており、物件価値が下がりにくく、むしろ上昇することも期待できたこと、
そして建物比率が高く評価される傾向があり、多額の減価償却費を計上しやすかったためです。
しかし、税制改正により、個人が国外の中古不動産について、簡便法で計算した耐用年数に基づく減価償却費を損益通算することができなくなりました。
つまり、国外不動産を利用して不動産所得を大幅なマイナスにし、国内の所得と損益通算するという節税の道は、
個人においては基本的に塞がれた形となります(法人の場合は依然として認められています)。
したがって、現在、個人が所得税の節税を目的として不動産投資を検討する際には、主に国内不動産が対象となると言えるでしょう。
不動産投資による所得税節税の留意点
不動産投資による所得税節税は魅力的に見えますが、実行する際にはいくつかの重要な留意点があります。
- 節税目的だけの投資は危険
節税効果だけを追い求めると、収益性の低い物件や、将来的に売却が困難な物件を選んでしまうリスクがあります。
あくまでも「投資」である以上、物件自体の収益性や資産価値の維持・向上が大前提です。
出口戦略、つまり売却時の価格が想定より大幅に低い場合、節税効果を加味してもトータルで損失を被る可能性も十分にあります。
また、想定外の修繕費が発生し、キャッシュフローが悪化するケースも考慮に入れるべきです。 - 損益通算の制限
不動産所得の赤字を他の所得と損益通算できますが、注意点があります。
それは、土地の取得にかかる借入金の利子に相当する金額は、損益通算の対象とならないというルールです。
フルローンで物件を購入し、多額の金利を支払っている場合、その全てが経費として認められ、損益通算できるわけではないことを理解しておく必要があります。 - キャッシュフローの管理
減価償却費は現金の支出を伴わない経費ですが、実際の不動産経営では固定資産税、修繕費、管理費などの現金支出が発生します。
税務上の所得と実際のキャッシュフローは異なるため、手元の資金がショートしないよう、資金繰りをしっかりと管理することが不可欠です。 - 売却タイミングと所有期間
売却時の税率を低く抑えるためには、所有期間が5年を超えてから売却することが重要です。
5年以内の短期譲渡となると税率が約40%と高くなるため、節税効果が大きく損なわれてしまいます。 - 高所得者向けの戦略
繰り返しになりますが、この節税スキームは、所得が高く、適用される所得税率が高い方ほどメリットが大きくなります。
ご自身の所得状況と照らし合わせて、効果を慎重に検討する必要があります。
まとめ
今回は、不動産投資、特に中古不動産を活用した所得税の節税スキームについて解説しました。
ポイントは以下の通りです。
- 減価償却費という現金支出を伴わない経費を計上し、不動産所得を圧縮する。
- 不動産所得の赤字を給与所得など他の所得と損益通算することで、課税所得全体を減らす。
- 中古資産の耐用年数の仕組みを利用し、特に築古の木造物件などで短期償却を目指す。
- 出口戦略(売却)が重要であり、損益通算時の税率と売却時の譲渡所得税率の差を利用してトータルの節税効果を狙う。
- 売却時は所有期間5年超で長期譲渡所得の低い税率を適用する。
不動産投資による節税は、仕組みを正しく理解し、適切な物件を選び、出口戦略までしっかりと計画することで、大きな効果が期待できます。
しかし、税制は複雑であり、個々の状況によって最適な対応は異なります。
実際に検討される際には、必ず税理士などの専門家に相談し、ご自身の状況に合わせたアドバイスを受けることを強くお勧めします。
本記事が、節税対策を検討されている経営者の皆様にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。