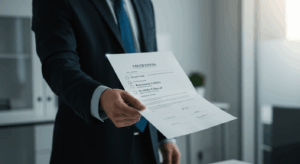自社株評価を合法的に引き下げる経営者のための節税対策

皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週水曜日に、経営者なら知っておきたい「節税対策」についての知識を解説しています。
「会社は順調に成長し、利益も出ている。しかし、その分だけ税金の負担が重くのしかかる…」
「自分が引退した後、会社を子供に継がせたいが、自社株の相続税がとんでもない金額になると聞いて頭が痛い…」
会社の成長は喜ばしい一方で、それに伴う法人税や、将来必ず訪れる相続・事業承継時の税金問題は、経営者の皆様にとって決して無視できない、深刻な課題ではないでしょうか。
特に、非上場会社である中小企業にとって、「自社株」はまさに諸刃の剣です。会社の価値そのものであると同時に、将来、莫大な相続税を生み出す火種にもなり得ます。
本記事では、多くの中小企業経営者が直面する「相続税対策」と「法人税対策」について、その考え方から、今だからこそ有効な具体的な手法まで、徹底的に解説していきます。
なぜ、あなたの会社の「自社株」が相続時の時限爆弾になるのか?
多くの中小企業経営者が見過ごしがちだが、最も重要な事実とは、経営者が亡くなった際の最大の相続税負担は、多くの場合「自社株」から発生するという現実です。
上場株式であれば市場でいつでも売却し、納税資金に充てることができます。
しかし、中小企業の自社株は、たとえ会社の価値が高くても、自由に売買できる市場はありません。
つまり、換金できないにもかかわらず、高額な相続財産として評価され、多額の相続税が課せられてしまうのです。
特に、以下のような会社は注意が必要です。
- 純資産額が多額な会社(内部留保が厚い健全経営の会社)
- 利益が堅調に伸びている会社
こうした優良企業ほど、税務上の株価は高く評価されます。
その結果、後継者であるご子息が相続のために多額の借金を背負ったり、最悪の場合、納税資金を確保するために会社そのものを手放さざるを得ないといった事態に陥りかねません。
これでは、まさに本末転倒です。
相続税対策の王道は「株価引き下げ」と「株式移転」のコンビネーション
では、この「自社株問題」にどう立ち向かえば良いのでしょうか。
その答えは、極めてシンプルです。相続税対策の王道は、以下の2つのステップで構成されます。
- 税務上の株価を、適切な方法で引き下げる
- 株価が下がったタイミングで、経営者(大株主)から後継者(子供や孫)へ自社株を移転する(贈与または低額での譲渡)
つまり、会社の価値が低いタイミングを意図的に作り出し、そのタイミングで次世代に株式を渡すことで、将来の相続税や移転時の贈与税を最小限に抑える。
これが事業承継における節税の基本戦略となります。
この戦略を実行するためには、まず「どうやって株価を下げるか」を考えなければなりません。
例えば、役員退職金の支給や、後述するオペレーティングリースの活用、場合によっては他社との合併なども株価引き下げの手法として検討されます。
【要注意】焦りは禁物!株価対策直後の贈与に潜む「税務否認リスク」とは
「なるほど、株価を下げてすぐに贈与すればいいのか!」と考えるのは、少し早計です。
実は、ここには税務上の大きな落とし穴が潜んでいます。
専門家が恐れる「総則6項」の罠
株価引き下げ策を実行した【直後に】自社株の贈与や低額譲渡を行うと、税務署から「一連の行為は税金を不当に安くするためのものだ」と見なされてしまう可能性があります。
これは専門家の間で「総則6項(そうそくろっこう)」と呼ばれる規定によるもので、形式的には合法な行為であっても、その実質が租税回避目的であると判断された場合、その行為がなかったものとして(つまり、株価を下げる前の高い評価額で)税金が計算されてしまうという、非常に厳しいものです。
リスク回避と株価再上昇のジレンマ
この「総則6項」による否認リスクを避けるためには、どうすれば良いのでしょうか。
明確な基準はありませんが、実務上は、合併などの株価対策を行ってから、実際に贈与するまでに2~3年程度の期間を空けることが一つの目安とされています。
しかし、ここに経営者を悩ませる大きなジレンマが生まれます。
期間を長く空ければ空けるほど税務上の否認リスクは下がりますが、その間に会社の業績が好調であれば、せっかく下げた株価が再び上昇してしまうのです。
リスクを取って短期決戦に出るか、安全策を取って株価の再上昇を覚悟するか。ここが専門家の知見と、経営者様の判断が問われる部分なのです。
法人税対策にも効く!今、私が注目する節税スキーム「オペレーティングリース」
さて、ここまでは主に相続税対策としての自社株評価に焦点を当ててきました。
しかし、経営者の皆様にとっては、目先の「法人税」も大きな課題でしょう。
「何か有効な節税策はないか?」というご質問に対し、私が現時点で有力な選択肢の一つとして挙げているのが「オペレーティングリース」です。
数年前まで、節税の代表格といえば生命保険でしたが、相次ぐ税制改正により、現在ではその効果はかなり限定的になっています。
その代替案として、今改めて注目されているのが、このオペレーティングリースなのです。
オペレーティングリースの仕組みを簡単解説
オペレーティングリースとは、一言でいえば「航空機やコンテナ、船舶といった大型資産への共同投資」です。
その仕組みと節税効果は以下のようになります。
- 仕組み
リース会社が、複数の投資家(法人)から資金を集めます。
例えば「1口1億円×100口=100億円」といった形で資金調達し、その資金で航空機などを購入します。
そして、購入した資産を航空会社などにリース(貸し出し)します。 - 損金の発生
投資した法人は、出資持分に応じた航空機などの減価償却費を自社の経費(損金)として計上できます。 - 利益の繰り延べ効果
リース期間の初期(特に初年度)に減価償却費が大きく計上されるため、会計上は多額の赤字(損失)が発生します。
これにより、その期の法人税を大幅に圧縮できます。
一方、リース期間の後半(5~6年後以降)は、リース料収入が減価償却費を上回り、大きな黒字(利益)となって戻ってきます。
つまり、今期の利益を将来に繰り延べることで、短期的に大きな節税効果を生み出すスキームです。
この手法は、過去に国税当局と裁判で争われた経緯もありますが、現在では完全に認められた節税商品として定着しています。
具体的な節税効果は案件によりますが、例えば1億円を出資した場合、初年度に約70%にあたる7,000万円もの損金を計上できるケースもあり、その効果は絶大です。
高い節税効果の裏にある「2つの重大リスク」を直視する
これほど高い節税効果を持つオペレーティングリースですが、手放しで推奨できるわけではありません。
これは節税商品であると同時に「投資」であるため、当然ながらリスクが存在します。
専門家として、そのリスクを包み隠さずお伝えする責任があると考えています。
リスク1:リース先の破綻リスク
最も大きなリスクは、リース先である航空会社や海運会社が倒産してしまうことです。
記憶に新しいコロナ禍や、過去のリーマンショックでは、実際に多くの航空会社が経営危機に陥りました。
万が一、リース先が破綻すれば、投資元本が大きく毀損し、節税どころか「ただ多額の損失を出しただけ」という最悪の結果になりかねません。
リスク2:為替リスク
オペレーティングリースの多くは、日本円で出資したとしても、実際の資産運用は米ドル建てで行われます。
そのため、出資金が戻ってくる償還時の為替レートによって、最終的な手取り額が大きく変動します。
契約時よりも円高が進んでいれば為替差損が発生し、逆に円安が進んでいれば為替差益が生まれます。
この為替の動向は、誰にも正確に予測することはできません。
また、出資単位も一般的には最小で3,000万円程度からと高額であり、節税効果を求めて数億円単位の出資を行う企業も少なくありません。
これらのリスクを十分に認識した上で、慎重に判断する必要があります。
【応用編】オペレーティングリースで自社株評価をゼロにし、無税で事業承継する方法
このオペレーティングリース、実は単なる法人税対策に留まりません。
冒頭でご説明した「自社株の相続税対策」と組み合わせることで、驚異的な効果を発揮します。
具体的なスキームはこうです。
- 会社に多額の利益が出た期に、オペレーティングリースへ大型の出資を行う。
- 初年度に多額の損失が計上され、会社の決算は大きな赤字になる。
- その結果、会社の純資産が圧縮され、税務上の自社株評価額が限りなくゼロに近くなる。
- この株価がゼロになったタイミングで、後継者である子供へ自社株を贈与する。
例えば、3億円の出資を行い、初年度に2億円の損失を計上することで、税務上の株価をほぼゼロにする。
そして、そのタイミングで贈与税を課されることなく、次世代への株式移転を完了させる。
これは、目先の法人税と、将来の相続税・贈与税という2つの大きな税負担を一気に解消できる可能性がある、非常にダイナミックな手法です。
もちろん、先ほど述べた投資リスクとの兼ね合いになりますが、成功した際のリターンは計り知れません。
まとめ:節税対策は、リスクとリターンのバランスを見極める経営判断そのもの
今回は、中小企業の節税対策として、「自社株対策の王道」と、それを実践する上でも有効な「オペレーティングリース」について解説しました。
将来の事業承継を見据え、計画的に株価を引き下げ、適切なタイミングで株式を移転することの重要性をご理解いただけたかと思います。
そして、オペレーティングリースのような手法は、法人税を繰り延べるだけでなく、株価評価を劇的に引き下げる起爆剤にもなり得るのです。
よくわからない投資話に手を出すくらいであれば、仕組みが明確で、税務上の効果が確立されているオペレーティングリースの方が、はるかに確実な節税策であると言えます。
もちろん、今回ご紹介した手法が、すべての会社にとって最適解とは限りません。
会社の財務状況、利益水準、そして経営者様ご自身の事業承継に対するお考えによって、取るべき戦略は大きく変わります。
重要なのは、これらの知識を武器に、自社にとってのリスクとリターンを正しく見極め、最適な経営判断を下すことです。
もし、具体的な対策でお悩みの場合は、ぜひ一度、経験豊富な専門家にご相談ください。貴社にとって最善の道筋を、共に描いていけるはずです。