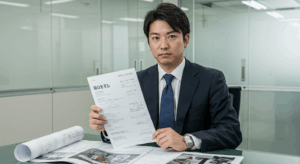税務調査で「使途不明金」と指摘されたらどうする?
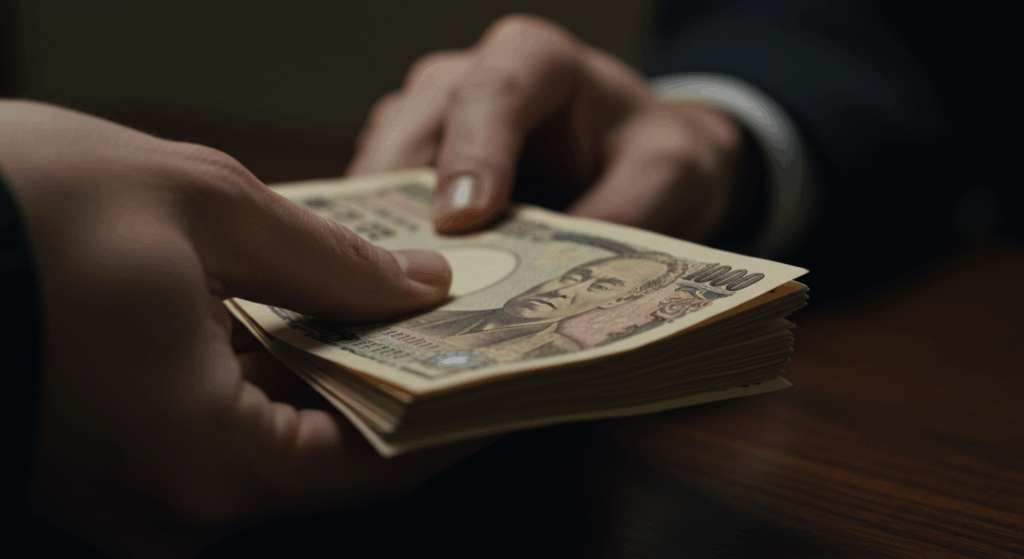
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週月曜日に、経営者なら知っておきたい「税務調査」についての知識を解説しています。
「社長、この経費は何に使ったか証明できますか?」
税務調査で調査官からこう問われ、冷や汗をかいた経験はありませんか?
領収書がない、あるいは内容が曖昧な支出は「費途不明金」と見なされ、原則として損金(経費)として認められません。
しかし、そこで「証明できないので仕方ない」と諦めてしまうのは早計です。
この記事では、多くの経営者が頭を悩ませる「費途不明金」について、損金算入が認められるための要件や、税務調査における具体的な交渉・立証のポイントを、専門家の視点から分かりやすく解説します。
税務調査で不利な判断をされないために、正しい知識と対策を身につけましょう。
そもそも「費途不明金」はなぜ損金にならないのか?
まず、基本原則から確認しましょう。
法人が支出したお金のうち、何に使ったのかが明らかでないものは、損金の額に算入されません。
これは法人税の基本的なルールとして定められています。
法人税基本通達9―7―20(費途不明の交際費等)
法人が交際費,機密費,接待費等の名義をもつて支出した金銭でその費途が明らかでないものは,損金の額に算入しない。
なぜこのような厳しいルールがあるのでしょうか。
それは、「経費であることの証明は、本来、納税者自身が行うべき」という考え方が根底にあるからです。
もし、使途が分からない支出を簡単に経費として認めてしまえば、誰もが不透明な支出を経費に計上し、課税の公平性が保てなくなってしまいます。
税金の計算は、客観的で正当な事実に基づいて行われる必要があります。
その大前提を守るために、費途不明金は損金として認められないのです。
「損金の立証責任」は誰にある?知っておきたい裁判所の考え方
では、ある支出が損金かどうかを証明する責任(立証責任)は、納税者と税務署(課税庁)のどちらにあるのでしょうか。
この点について、非常に重要な裁判例があります。
東京地裁平成6年9月28日判決(要旨)
- 損金の額については、本来、課税庁が「これ以上損金は存在しない」ということを主張・立証する責任を負う。
- しかし、提出された資料などから見て、その支出を損金にできないことが事実上推認できる場合は話が別。
- その場合は、納税者側が「その支出は業務に関連している」と合理的に思わせるだけの具体的な反証をしない限り、損金への算入は否定される。
少し難しい表現ですが、ポイントは以下の2点です。
- 原則論
立証責任は税務署側にある。 - 実務上の現実
客観的に見て「これは経費とは言えないだろう」という状況(例えば、領収書がなく、何に使ったか全く説明できない)があれば、納税者側が「いや、これは正当な経費です」と証明する必要が出てくる。
つまり、「立証責任は税務署にあるから何もしなくても良い」というわけにはいかないのです。
税務調査では、この「事実上の推認」を覆すための具体的な主張と資料の提示が求められます。
領収書がなくてもOK!損金算入が認められた2つのパターン
「領収書や請求書がないと、もうダメなのか…」と落胆する必要はありません。
たとえ直接的な証拠がなくても、状況証拠を積み重ねることで損金算入が認められたケースは存在します。
ここでは代表的な2つのパターンをご紹介します。
パターン1:支払いのルールと業務内容が明確だったケース
最初のケースは、領収書がなくても、「あらかじめ定められたルールに基づいて支払いが行われ、その対価として提供されたサービス内容も明確だった」と証明できた場合です。
ある裁決例を見てみましょう。
昭和57年1月14日裁決(要旨)
支出先を明らかにできなかった支出について、以下の点が認められたため、販売手数料として損金算入が相当と判断された。
- その支出があらかじめ定められた支払基準に基づくものであること
- 提供を受ける役務の内容が支払基準において具体的に明らかにされていること
- 相手先は支払基準の内容について知らされていたこと
- 各支出金額がその提供を受けた役務の内容に照らして相当であること
この事例から学べるのは、支出に関する社内ルールを整備し、そのルールに則って運用することの重要性です。
例えば、「紹介者へのリベートは売上の〇%」といった基準を明確に文書化し、その基準通りに支払っていれば、たとえ個別の領収書がなくても、支出の正当性を主張しやすくなります。
パターン2:客観的に見て業務の実態が証明できたケース
次に、支払いの事実を裏付ける客観的な状況証拠によって、業務の実態が認められたケースです。
ある裁決では、外注費の支払先が判然としないものの、以下の事実から、業務委託の対価として支払われた費用(外注費)であると認められ、損金算入が認められました。
平成22年3月11日裁決(要旨)
- 測量図面が作成され、実際に外注先が測量していたことが明らか。
- 測量に必要な伐採の跡が確認された。
- 外注先が作業員を手配し、具体的な指示を行っていた。
これらの状況から、伐採業務が実際に行われ、その対価として金銭が支払われたと認めるのが相当であり、業務遂行上必要な外注費として損金に算入できると判断された。
さらに、別の古い裁決例では、「自社の従業員の作業能力から見て、その業務を内製化することは不可能だった」という状況が、外注の必要性を裏付ける有力な証拠となりました。
昭和48年12月10日裁決(要旨)
外注工賃の支払先を明らかにしない場合でも、
- 補助簿に数量、単価が記載されている
- 製品の製造工程からみてその作業が必要である
- 当時の従業員の作業能力からみて自社で加工することができない
と認められるときは、外注工賃を原価として認めるのが相当である。
これらの事例が示すのは、「その支出がなければ業務が成り立たなかった」という客観的な事実や状況を、いかに具体的に説明できるかが重要であるという点です。
【実践編】税務調査で「費途不明金」を認めてもらうための交渉術
理論は分かっても、実際の税務調査の現場でどう立ち回れば良いのかが最も気になるところでしょう。
私自身のコンサルティング事例でも、支出の事実はあるものの、資料がほとんど残っておらず、使途が判然としないケースがありました。
このような絶望的な状況でも、打つ手はあります。重要なのは、「立証のために、できる限りの努力を尽くす」姿勢を見せることです。
本件では、まず社内に残っている断片的な資料をかき集め、当時の状況を知る担当者を探し出してヒアリングを行いました。
さらに、取引先など関連企業の社長にもお願いし、税務署の「反面調査」(取引先などへの聞き取り調査)に協力していただきました。
まさに、「これ以上は調査のしようがない」というところまで事実関係の解明に協力した結果、税務署もこちらの努力を汲んでくれ、最終的に損金算入を認めてくれました。
税務署側からすれば、強硬に「費途不明金」として処分することもできたはずです。
しかし、そうすると裏付け調査に多大な手間がかかりますし、将来的に裁判になった場合のリスクも考えなければなりません。
納税者が立証のために真摯に協力する姿勢を見せることで、「総合的に判断して、今回は認めましょう」という着地点を見出しやすくなるのです。
調査で否認されても、まだチャンスはある
万が一、税務調査の段階で損金算入が認められなかったとしても、諦める必要はありません。
その後の「審査請求」という不服申し立ての段階で、新たな証拠を提出して主張が認められる可能性があります。
ある裁決例では、調査時には支払先の詳細を明らかにしなかったため損金不算入とされましたが、審査請求の段階で支払先の一部を具体的に特定し、その支払先からも受領の事実が確認できたため、その部分については交際費として損金算入が認められました。
最も避けたい「認定賞与」のリスクと対抗策
費途不明金の処理で最も厳しいのが、その支出が「役員(社長など)への賞与(ボーナス)」と見なされてしまう「認定賞与」です。
認定賞与とされると、法人はその分を損金にできず法人税がかかる上、役員個人には高額な所得税と住民税が課され、さらに源泉徴収義務違反の問題も生じるという、まさに三重苦の状態に陥ります。
しかし、税務署が認定賞与として課税するためには、越えなければならないハードルがあります。
過去の判例では、認定賞与とするためには、「そのお金を役員個人が自分のために消費した、あるいは個人の資産にした(個人の預金口座に入れたなど)」ことを税務署側が立証する必要がある、と示されています。
熊本地裁昭和43年10月21日判決(要旨)
会社の使途不明金について、役員個人が消費または資産化したことの立証がない限り、役員への賞与と認定して課税することは違法である。
もし、税務調査で費途不明金を安易に認定賞与として処理されそうになった場合は、この判例を盾に、「社長個人が私的に流用したという具体的な証拠を示してください」と毅然と交渉することが極めて重要です。
まとめ:費途不明金は「交渉の余地が大きい」と心得る
今回は、税務調査における「費途不明金」の取り扱いについて、基本的な考え方から実践的な対応策まで解説しました。
- 原則
費途不明金は損金にならない。 - 立証責任
実務上は、納税者側が業務との関連性を証明する必要がある。 - 対策
領収書がなくても、「支払基準の明確化」や「業務実態の客観的な証明」で損金算入の可能性がある。 - 交渉
調査では「立証努力」を尽くす姿勢が重要。諦めずに交渉の糸口を探る。 - リスク管理
「認定賞与」とされないために、国側の立証責任を理解しておく。
税務調査で費途不明金を指摘されると、動揺してしまう経営者の方は少なくありません。
しかし、その支出が本当に事業のために必要だったものであれば、必ず説明できる要素があるはずです。
すぐに諦めるのではなく、記憶を辿り、資料を探し、状況を整理して、粘り強く主張を組み立てること。
それが、あなたの会社を不当な課税から守るための第一歩です。
もし対応に不安があれば、税務調査に精通した当事務所までお気軽にご相談ください。