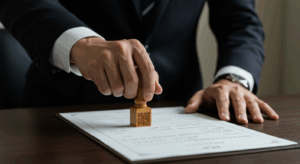税務調査はこうして選ばれる!調査対象となる会社の選定基準と5つのステップ

皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週月曜日に、経営者なら知っておきたい「税務調査」についての知識を解説しています。
「そろそろ、うちの会社にも税務調査が来るのではないか…」
多くの経営者様が、心のどこかで抱えている不安ではないでしょうか。
特に、税務署の人事異動が終わり、新しい体制で調査活動が本格化する7月後半から年末にかけては、税務調査の最盛期となります。
税務署から一本の電話がかかってきた時、多くの経営者様は「なぜ、うちの会社が?」と疑問に思われることでしょう。
税務調査は、決して無作為に選ばれているわけではありません。そこには、明確な選定基準と合理的な順序が存在します。
今回は、調査官がどのようにして調査先を選んでいるのか、その具体的な「選定基準と順序」について徹底的に解説します。
この記事を最後までお読みいただければ、税務調査の選定プロセスが明確に理解でき、自社が今どのような状況にあるのかを客観的に把握できるようになるはずです。
ステップ1:すべての始まりは「KSKシステム」による網羅的なスクリーニング
調査先選定の第一歩は、国税総合管理システム、通称「KSKシステム」による機械的な選定から始まります。
これは、全国の国税局と税務署をネットワークで結び、申告・納税に関するあらゆる情報を一元管理している巨大なデータベースです。
このKSKシステムが、蓄積された膨大なデータの中から、以下のような基準で「調査すべき可能性が高い法人」を自動的にリストアップします。
- ① 前回から長期間調査が実施されていない法人
企業の事業活動は年々変化します。そのため、長期間調査が行われていない法人は、取引内容や経理処理の状況を把握する必要があると考えられ、優先順位が上がります。 - ② 所得率が低調な法人
所得率とは、売上に対してどれくらいの所得(利益)が出ているかを示す指標です(所得率 = 所得 ÷ 売上)。
この数値が例年と比較して急に下がっている場合、「何らかの理由で利益が減少している」とシステムが判断し、その原因を探るべきだとフラグが立てられます。 - ③ 同業他社と比較して所得率が低調な法人
KSKシステムには、業種ごとの平均所得率がデータとして蓄積されています。
自社の所得率が、同じ地域の同業者と比較して著しく低い場合、「業界の傾向から見て不自然ではないか」と判断され、選定候補となります。
このように、最初のスクリーニングは、個別の事情ではなく、あくまでも客観的なデータに基づいて機械的に行われるのです。
ステップ2:「資料せん」との突合で深掘りし、矛盾点を洗い出す
KSKシステムでリストアップされた法人は、あくまで「見込み先」です。
次に調査官は、提出された申告書や決算書といった書類と、「資料せん」と呼ばれる内部資料を突き合わせ、より深く内容を吟味していきます。
「資料せん」とは、税務署が様々な取引先から収集した「支払いや受け取りの記録」のことです。
これには法律で提出が義務付けられている「法定調書」と、税務署の任意のお願いで集められる「法定外調書」がありますが、調査官はどちらも非常に重要視しています。
この突合プロセスで特に注目されるのが、「勘定科目内訳明細書に記載のない取引先」の存在です。
例えば、A社から100万円の支払いを受けたという資料せんが税務署にあるにもかかわらず、あなたの会社の申告書類のどこにもA社との取引記録が見当たらない場合、調査官はどう考えるでしょうか。
このような場合では、調査官は「これは売上を除外している、いわゆる『簿外取引』の可能性があるのではないか?」と考えます。
このように、資料せんとの矛盾は、意図的な利益隠しの疑念に直結します。
この段階で具体的な矛盾点や不明点が見つかった法人は、調査対象として極めて有力な候補となります。
ステップ3:急成長企業は要注意!「好況調査」という名の重点チェック
次に調査官が注目するのが、「好況な会社」、特にここ数年で売上が急激に伸びている会社です。これは「好況調査」とも呼ばれ、選定における重要なカテゴリーの一つです。
なぜ、業績が良い会社が狙われやすいのでしょうか。
それは、「売上が急激に伸びている会社は、利益を圧縮したいというインセンティブが働きやすい」と経験則上考えられているからです。
急な増益は、納税額の増加に直結します。その負担を少しでも軽くしたいという気持ちから、過度な節税に走ってしまったり、中には売上の一部を計上しなかったりといった不正に手を染めてしまったりするケースが後を絶ちません。
調査官はそうした傾向を熟知しているため、売上が急成長している企業を「成果が見込める調査先」として、真っ先にリストアップするのです。
ステップ4:赤字だからと安心はできない?「数値異常・赤字法人」の選定
「うちは赤字だから、税務調査は来ないだろう」
このように考えている経営者様は少なくありません。この通説は、ある意味で事実です。
税務調査も、限られた人員と時間の中で行われる行政活動です。
同じ調査日数をかけるのであれば、より多くの追徴税額が見込める黒字法人を優先するのは、調査の「効率性」を考えれば当然のことと言えます。
実際に、赤字法人に調査が入っても、追加で納税が発生するケース(増差税額の発生)は少ないのが実情です。
しかし、だからといって赤字法人が絶対に調査されないわけではありません。
以下のような場合は、赤字であっても選定対象となります。
- 決算書の勘定科目に異常な数値がある場合
- ステップ2の「資料せんとの突合」で帳尻が合わない点が見つかった場合
特に後者は重要です。たとえ最終的に赤字申告であっても、把握されている取引内容と申告内容に食い違いがあれば、「赤字を意図的に作り出しているのではないか」「本当は黒字なのではないか」という疑いが生じます。
「赤字だから大丈夫」という考えは禁物です。調査の優先順位が下がるだけで、免除されるわけではないことを理解しておく必要があります。
ステップ5:絶対に逃れられない!「継続管理対象先」という特別な存在
さて、これまでご紹介したステップ1から4の選定基準から外れたとしても、最後に「継続管理対象先」という、ほぼ自動的に調査対象となる法人が存在します。
これに該当する場合、調査から逃れることは極めて困難です。
継続管理対象先とは、主に以下の2つの法人を指します。
- 大規模法人
資本金1億円以上の大規模法人は、取引が複雑で多岐にわたるため、一度の調査ですべてを把握することが困難です。
そのため、不正の有無にかかわらず、一定の周期(通常3~4年)で定期的に調査が行われることになっています。 - 前回の税務調査で重加算税が賦課された法人
こちらが中小企業にとって特に重要です。
「重加算税」とは、税金を意図的に少なく申告した場合、すなわち「仮装または隠ぺい」という最も悪質な行為に対して課される、非常に重いペナルティです。
一度でも重加算税を課された法人は、「不正を行う体質がある」と税務署に認定されたことになります。
そのため、大規模法人と同様に、3~4年周期で「その後の状況はどうか」をチェックするための調査が、半ば義務的に行われることになるのです。
まとめ:税務調査で最も重視される2つのポイントと、経営者がすべきこと
ここまで、税務調査先が選定される5つのステップを見てきました。
そのプロセスは、KSKシステムによる網羅的なスクリーニングから始まり、資料せんとの突合、業績や過去の実績に基づく絞り込みへと進んでいきます。
様々な基準がありますが、特にキーとなるポイントはどこにあるのでしょうか。
それは、本記事で繰り返し触れた、
- 「資料せんとの突合」で見つかる矛盾点
- 「重加算税の課税事績」という過去の不正
この2点にあると言っても過言ではありません。
外部から収集した客観的な情報(資料せん)との食い違いや、過去の悪質な不正行為の履歴は、調査官にとって「不正の確たる証拠」に繋がりやすい、非常に有力な情報なのです。
この記事を通じてお伝えしたいのは、税務調査は決して運や偶然で選ばれるものではない、ということです。
日々の取引を正確に記帳し、根拠のある誠実な申告を続けることが、結果として最大の税務調査対策となります。
もし、自社の経理処理や申告内容に少しでも不安がある、あるいは過去の調査で指摘を受けた経験があるという経営者様は、専門家の視点から現状をチェックすることをお勧めします。
問題が大きくなる前に、ぜひ一度ご相談ください。