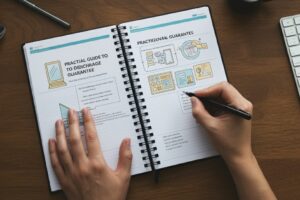その経費は危険です!税務調査官が「期末の返品・商品券購入」を見抜く手口
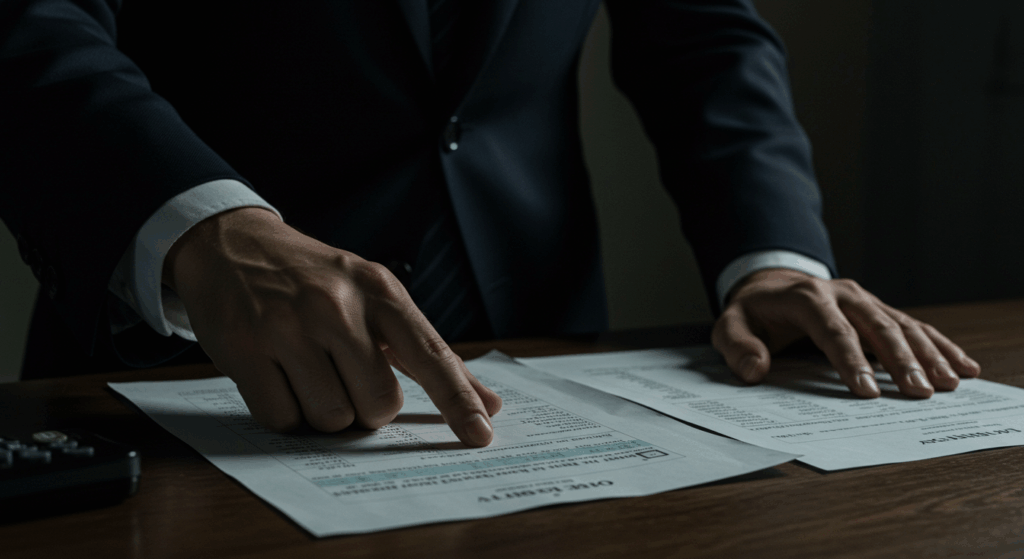
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週月曜日に、経営者なら知っておきたい「税務調査」についての知識を解説しています。
「今期もなんとか黒字になったが、それにしても税金が高い…」
期末が近づき、試算表や決算見込みの数字を見て、そう溜息をつく経営者の方も少なくないのではないでしょうか。
日々汗水流して稼いだ利益から、大きな金額が税金として納めなければならない現実に、理不尽さを感じてしまうお気持ちは痛いほど分かります。
そして、その驚きと焦りから、「少しでも納税額を減らせないか」と、その場しのぎの“節税策”に手を出してしまうケースが後を絶ちません。
しかし、こうした付け焼き刃の対策は、税務のプロである税務調査官の目から見れば、矛盾だらけに見えることがほとんどです。
実は、税務調査で否認される(間違いを指摘される)事項の大半は、この「期末の慌てた経理処理」に起因しています。
普段は関与していない経営者が主導することで、顧問税理士すら知らない取引が行われ、発覚したときにはもう手遅れ…という事態になりかねません。
この記事では、過去に実際にあった「返品」などを利用した安易な不正行為が、いかにして税務調査で見破られてしまうのか、その手口と調査手法を具体的に解説します。
自社の健全な経営を守るためにも、ぜひ最後までお読みください。
なぜ期末に不正が起きやすいのか?経営者の焦りが招く落とし穴
冒頭でも触れましたが、税務調査で問題となりやすいのは、期末に集中しています。なぜでしょうか。
それは、多くの経営者にとって、税金が「年に一度、期末にだけ意識するもの」になっているからです。
日々の経営活動に追われ、資金繰りや売上拡大に奮闘する中で、納税のことは二の次になりがちです。
そして、決算が迫ったタイミングで初めて予想以上の納税額を突きつけられ、愕然とします。
「このままでは資金繰りが苦しくなる」
「こんなに持っていかれるのはおかしい」
こうした焦りや不満が、冷静な判断を鈍らせます。
そして、「少し経費を多く見せかけられないか」「売上を少しだけ来期にずらせないか」といった安易な考えに至ってしまうのです。
しかし、こうしたその場しのぎの対策は、取引全体で見ると必ずどこかに歪みを生じさせます。
そして、その歪みこそが、税務調査官が真っ先に目を光らせるポイントなのです。
【手口1】巧妙な「カラ返品」による脱税とその見破り方
過去に頻繁に行われ、そして厳しく追及された脱税の手口の一つに、「仕入れの返品」を悪用したものがあります。
一見すると帳簿上は完璧に見えるため、非常に巧妙な手口と言えます。
手口の概要:帳簿上は完璧な仕入れ取引
この手口のカラクリは非常にシンプルです。
- 通常通り、取引先から商品を仕入れ、代金を支払う。
- この際、請求書や領収書、納品書など、経費計上に必要な証拠書類(証憑)はすべて揃っています。
- その後、仕入れた商品を取引先に「返品」する。
- 返品なので、支払った代金は当然戻ってきます。
- 会計処理では、「仕入れ」の事実だけを帳簿に記載し、「返品」の事実は隠蔽する。
- 返品によってお金が戻ってきた取引を帳簿から抜いてしまうのです。
結果として、帳簿上は「正規の仕入れ取引があった」としか見えません。
証拠書類も完璧に揃っているため、一見すると何の不備もないように思えます。
そして、返品によって戻ってきた資金は、帳簿に載らない「簿外資金」として、経営者の懐に入ってしまうのです。
税務調査官はどう見破るのか?「反面調査」という切り札
自社の帳簿だけを見ていては、この不正を発見するのは困難です。
では、調査官はどうやってこのカラクリを突き止めるのでしょうか。
答えは、「反面調査(はんめんちょうさ)」にあります。
反面調査とは、納税者の申告内容が正しいかどうかを確認するために、その取引の相手方(このケースでは仕入先)に対して行う調査のことです。
自社では返品の伝票を破棄・隠滅して証拠を消したつもりでも、返品を受けた納品業者には必ずその記録が残っています。
納品業者が返品を受けた際には、「赤伝(あかでん)」と呼ばれる返品専用の伝票を発行・保管しているのが一般的です。
これは、業者側の売上を取り消すための重要な証拠書類だからです。
調査官は、不自然に仕入額が大きい取引や、期末に集中している取引に狙いを定めます。
そして、その取引業者へ反面調査を実施し、「御社からA社(調査対象の会社)への売上についてですが、返品などはありませんでしたか?」と確認します。
業者側に保管されている赤伝と、調査対象の会社の帳簿を突き合わせれば、隠されていた返品の事実は一目瞭然で発覚してしまうのです。
自社の証拠は隠せても、取引相手の証拠まで消すことはできません。この一点を突かれるだけで、巧妙に仕組んだつもりの計画は脆くも崩れ去ります。
【手口2】仕入品の「横流し」による簿外資金の形成
返品と似たような手口で、仕入れた商品を別の業者に転売し、その売上を申告しない「横流し」という方法もあります。
- ステップ1: A社から商品を100万円で仕入れる(経費として計上)。
- ステップ2: その商品を、B社に90万円で転売する。
- ステップ3: B社から受け取った90万円の売上は帳簿に記載せず、裏金としてストックする。
この場合も、A社からの仕入れに関する証憑は揃っているため、一見すると不正は見抜けません。
しかし、これもB社への反面調査や、在庫の数量が帳簿と合わない「実地棚卸」などで矛盾が明らかになります。
古典的な手口ですが、それゆえに調査官も常に警戒している不正の一つです。
【手口3】経費を使った巧妙な資金捻出(商品券のケース)
商品を仕入れるのではなく、「経費」を悪用して簿外資金を作り出す、より巧妙な手口も存在します。
その代表例が、商品券やプリペイドカードの購入です。
ノベルティーを装った巧妙な手口
このケースでは、広告宣伝費や交際費などの名目で、大量の商品券が購入されていました。
帳簿を確認すると、確かに商品券の購入記録はあり、領収書も保管されています。
経営者に使途を尋ねると、「お得意様へのノベルティーとして配布した」と説明します。
実際に、一部の商品券はノベルティーとして顧客にプレゼントされていました。
このように、一部は実際に経費として使われているため、不正の全容を掴むのは非常に困難です。
購入枚数が異常に多いという不審点はあっても、「どの顧客に、いつ、何枚渡したのか」を完璧に証明することは不可能です。
調査官の執念の調査手法
しかし、税務調査官はここで引き下がりません。「帳簿の数字がすべて」とは考えていないからです。
彼らは、取引の「実態」を解明するために、あらゆる角度から調査を進めます。
- 顧客名簿との照合
経営者が「配布した」と主張する顧客の名簿を提出させ、本当に配布された可能性があるのか、配布枚数が妥当かなどを検討します。
配布したとされる顧客に直接確認の連絡(反面調査)をすることもあります。 - 予測枚数の割り出し
会社の規模や業種、過去の実績などから、ノベルティーとして配布されるであろう妥当な枚数を予測します。
帳簿上の購入枚数が、その予測を大幅に超えている場合、疑いはさらに深まります。 - 金券ショップへのローラー調査
最終手段として、会社近隣の金券ショップをしらみつぶしに調査します。
事業者による大量の商品券の持ち込みは目立つため、ショップ側も記録を残している場合があります。
このケースでも、調査官が粘り強く調査を続けた結果、1軒の金券ショップからこの企業による転売の事実が発覚しました。
調査の結果、ノベルティーとして使われたのはごく一部で、大半の商品券が現金化され、そのお金はすべて経営者個人の遊興費に充てられていたことが明らかになりました。
税務調査官は「帳簿の裏側」にある真実を見ている
今回ご紹介した手口に共通しているのは、「自社の帳簿さえ完璧にしておけばバレないだろう」という安易な考えです。しかし、それは大きな間違いです。
税務調査官は、単に帳簿の数字が合っているかを見ているわけではありません。
彼らは、その数字の裏側にある「お金の流れ」と「取引の実態」を徹底的に追跡します。
そのために、反面調査や銀行調査、内偵調査など、あらゆる権限と手法を駆使するのです。
長年の経験で幾多の脱税手口を見てきた調査官の目は、決して節穴ではありません。
その場しのぎでごまかせるほど、税務調査は甘くないのです。
まとめ:健全な経営のために、専門家との信頼関係を
期末に慌てて行う不自然な経理処理は、かえって税務調査官の注意を引き、結果として不正の発覚に繋がります。
そして、一度「脱税」と認定されれば、本来納めるべき税金に加えて、重いペナルティ(重加算税や延滞税)が課され、会社の信用も失墜するなど、計り知れないダメージを負うことになります。
最も重要なのは、日頃から自社の財務状況を正確に把握し、顧問税理士のような専門家と密にコミュニケーションを取ることです。
「税理士も知らないところで」行われた不正は、最も危険なパターンです。
目先の納税額を少し減らすために大きなリスクを冒すのではなく、長期的な視点で健全な経営を続けることこそが、会社を成長させる唯一の道です。
もし税金のことでお悩みであれば、決して一人で抱え込まず、信頼できる専門家にご相談ください。
正しい知識に基づいた節税と、将来を見据えた納税計画を一緒に立てていくことが、経営者であるあなたと、あなたの大切な会社を守ることに繋がるのです。