その土地は本当に固定資産?税務調査で狙われる「不動産の資産区分」
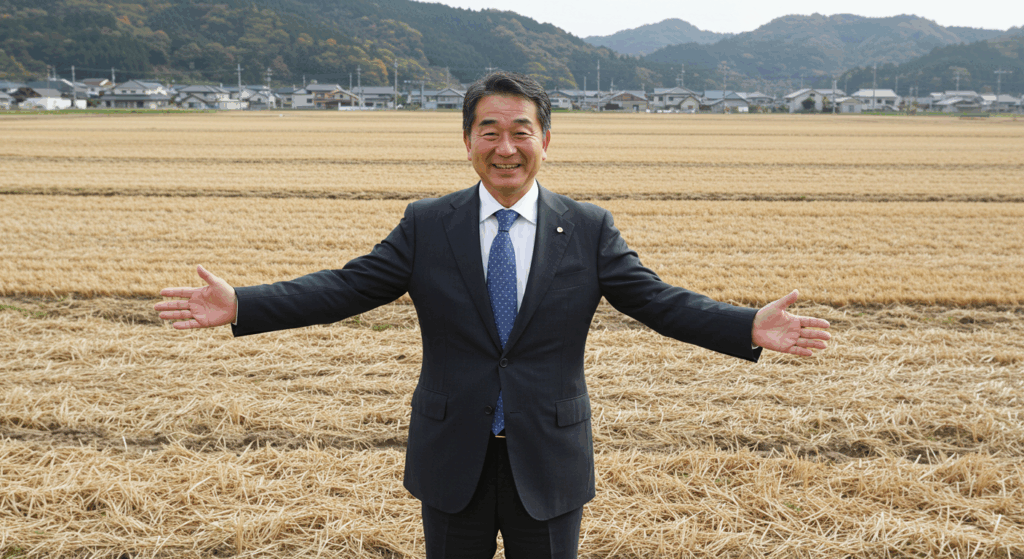
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週月曜日に、経営者なら知っておきたい「税務調査」についての知識を解説しています。
不動産業を営む経営者の方であれば、「この物件は販売用だから棚卸資産」「このビルは自社で使うから固定資産」といった区分は日常的に行われていることでしょう。
しかし、この一見シンプルな資産区分が、税務調査において重大な指摘事項となり、ときには数千万円単位の追徴課税に繋がるケースがあることをご存知でしょうか?
特に、収用や交換の特例(圧縮記帳など)を利用する際、その対象が「固定資産」でなければ適用が認められません。
販売目的の「棚卸資産」で特例を適用してしまえば、税務調査で確実に否認されます。
「うちは大丈夫」と思っていても、実務の現場では判断に迷うケースが頻発し、多くのトラブルが生じているのが現実です。
本記事では、不動産の「固定資産」と「棚卸資産」の区分がなぜ重要なのか、そして税務調査官がどこを見ているのかを、実際の裁決事例を交えながら徹底的に解説します。
なぜ資産区分が税務調査で問題になるのか?
不動産の資産区分は、会計上の表示だけの問題ではありません。
税金の計算、特に税務上の特例適用の可否に直結するため、税務署は非常に厳しい目でチェックします。
- 棚卸資産(販売用不動産)
いわゆる「商品」です。
売却して得た利益は、事業所得や売上総利益として計上されます。 - 固定資産(自社使用・賃貸用不動産)
長期間にわたって事業のために使用する資産です。
売却益は譲渡所得となり、収用や交換など一定の要件を満たせば、課税を繰り延べる「圧縮記帳」などの特例が適用できる場合があります。
問題は、この圧縮記帳などの有利な特例が、棚卸資産には一切適用されない点にあります。
そのため、「本当は販売目的(棚卸資産)だったのに、特例を使いたいがために固定資産として申告した」といったケースが後を絶たず、税務調査の主要なターゲットとなっているのです。
税務調査官が注目する3つの判断基準
では、税務調査官は具体的にどのような基準で資産区分を判断するのでしょうか。
実務上、特に重要視されるのは以下の3つのポイントです。
- 目的の客観性
その不動産を「取得した目的」が何であったか。
口頭での主張だけでなく、それを裏付ける客観的な資料があるかどうかが問われます。 - 経理処理の一貫性
会社の会計帳簿上で、一貫してその資産区分(棚卸資産 or 固定資産)で処理されているか。 - 実際の利用形態
主張する目的に沿った利用実態があるか。
例えば、「固定資産だ」と主張しながら、全く使用も賃貸もされていない、といった状況は不自然と見なされます。
これら3つのポイントが、実際の税務調査や裁判でどのように評価されるのか、具体的な事例を見ていきましょう。
ケース1:当初の取得目的がすべてを決めた事例
まず、資産の取得当初からの目的がいかに重要かを示す裁決例です。
これは、不動産の交換特例の適用が争われた事案です。
【平成7年7月4日裁決】のポイント
- 事案
F社が所有していた乙土地が、交換特例の対象となる「固定資産」に該当するかどうかが争点となった。- 調査で判明した事実
- 乙土地の取得に関する稟議書に「商業ビルの請負工事条件付の転売目的で取得する」と明確に記載されていた。
- F社の貸借対照表では、乙土地は「棚卸資産」として計上されていた。
- F社の総務部長が「購入当初から交換時まで棚卸資産であり、固定資産として利用した事実は一切ない」という確認書を提出していた。
- 結論
上記の客観的証拠から、乙土地は棚卸資産と認定。交換特例の適用は否認された。
この事例から学べるのは、税務調査では当事者の「内心の意思」よりも、「客観的な証拠」が絶対的に優先されるという事実です。
稟議書や決算書といった、 その当時に作成された資料の記載が、後からの主張を覆す決定的な証拠となります。
ケース2:「売れないから賃貸に…」安易な資産転用が認められなかった事例
次に、当初は販売目的(棚卸資産)だった不動産を、何らかの理由で固定資産に転用したと主張したものの、認められなかったケースを複数見ていきましょう。
これは実務上、最もトラブルになりやすいパターンです。
駐車場計画や老人ホーム計画は「証拠不十分」
収用に伴う特別控除(5,000万円控除)の適用が争われた事案では、裁判所は納税者の主張を退けました。
【東京地裁令和2年8月6日判決】のポイント
- 納税者の主張
販売目的で取得した土地だが、後に老人ホーム事業者へ賃貸したり、駐車場として利用したりすることを検討していた。だから、この土地は固定資産だ。- 裁判所の判断
- 駐車場計画の図面などが作成されたのは、収用の話が出るかなり前の時点であり、その後も検討が継続されていた客観的証拠がない。
- 老人ホーム計画については、検討時期も不明で、客観的証拠が一切ない。
- 何より、取得してから売却するまで、一度も自社利用や賃貸をした事実がなかった。
- 経理上は一貫して販売用の土地として処理されていた。
- 結論
総合的に見て、販売目的で所有していたとみるのが自然であり、棚卸資産に該当する。特別控除の適用は否認。
この判決は、「検討していた」という主張だけでは不十分で、具体的な行動とそれを裏付ける客観的証拠や実際の利用実態がなければ、資産の転用は認められないことを示しています。
利用実態があっても「最終目的」次第では否認される
では、実際に賃貸などの利用実態があれば、必ず固定資産と認められるのでしょうか。実はそうとも限りません。
【平成17年7月8日裁決】のポイント
- 事案
公社が取得した土地を一時的に賃貸していたが、これは固定資産への転用と言えるか。- 審判所の判断
- この土地は、もともと市の代替地として取得され、市に引き取られることが予定されていた(=最終目的は売却)。
- 土地の賃貸は、あくまで積極的な利用の一環にすぎず、土地の最終的な利用(売却)の妨げとならない範囲で行われている。
- 結論
当初の販売目的は変更されておらず、固定資産への区分変更は行われていない。棚卸資産に該当するため、交換特例の適用は否認。
たとえ賃貸実績があったとしても、それが「最終目的である転売を妨げない一時的な利用」と判断されれば、棚卸資産のままであると見なされるのです。
事業廃止=固定資産化ではない
さらに、「個人事業を廃業して法人成りしたのだから、売れ残った不動産はもはや棚卸資産ではなく固定資産だ」という主張も認められませんでした。
【昭和45年10月29日裁決】のポイント
- 納税者の主張
個人事業を廃止した後に残った不動産を売却したので、これは固定資産の譲渡(譲渡所得)だ。- 審判所の判断
- 事業を廃止しても、棚卸資産が残っており、その処分が完了していなければ、実質的な事業は継続していると解釈される。
- 個人事業の残務整理として棚卸資産を売却する行為は、個人事業活動の一部である。
- 結論
固定資産の売却ではなく、棚卸資産の売却(事業所得)と認めるのが相当。
このように、税務署は形式的な変更ではなく、経済的な実態に着目して判断します。
安易な理屈での資産区分の変更は通用しないと心得ましょう。
ケース3:固定資産から棚卸資産への転用が認められた事例
逆に、固定資産から棚卸資産への転用が認められ、評価損の計上(低価法の適用)が認められたケースもあります。
【平成26年12月1日裁決】のポイント
- 事案
固定資産として計上していた土地について、販売目的に転用したとして棚卸資産に振り替え、評価損(低価法)を計上した申告の是非が争われた。- 審判所が認めた事実
- 当該土地を販売物件として開発し、販売活動を推進することについて、稟議を経た取締役会決議による明確な意思決定があった。
- 共有持分を取得した直後から、実際に売却交渉を行っていた事実があった。
- 経理上も、意思決定に基づき固定資産から棚卸資産に振り替える会計処理を行っていた。
- 逆に、その土地を自社の事務所や賃貸物件として利用する目的があったことを示す証拠資料は認められなかった。
- 結論
これらの事実を総合的に勘案すると、販売目的で所有していたと認めるのが相当。棚卸資産への転用を認め、評価損の計上を認容。
この裁決が示唆するのは、「明確な意思決定の証拠」と「具体的な行動の証拠」の重要性です。
取締役会議事録という会社の公式な意思決定の記録や、実際の売却交渉といった行動の記録が、資産区分の転用を裏付ける強力な証拠となったのです。
まとめ:将来の税務調査に備え、今すぐやるべきこと
これまで見てきたように、不動産の資産区分は、税務調査において極めて厳格に判断されます。
経営者として、自社を守るために以下の点を徹底してください。
- 取得目的を必ず書面で残す不動産を取得する際は、その目的が「販売」なのか「自社利用」なのか「賃貸」なのかを、必ず稟議書や取締役会議事録に明記してください。
これが全ての基本であり、最も強力な証拠となります。 - 経理処理と実態を一致させる経理上の資産区分と、実際の利用実態、そして当初の目的に矛盾がないか、常に確認する癖をつけましょう。
特に、資産の利用目的を変更する際には、安易に経理処理だけを変えるのではなく、その意思決定のプロセスを議事録等で明確に残し、実際の利用形態も変更することが不可欠です。 - 判断に迷ったら専門家に相談する資産区分の判断や目的の変更は、税務リスクを伴う重要な経営判断です。
「このくらい大丈夫だろう」という自己判断が、将来的に大きな損失を招く可能性があります。
少しでも迷ったり、収用や交換といった特殊な取引が関わる場合は、必ず税務の専門家に相談してください。
税務調査は、過去の事実を客観的な証拠に基づいて検証する場です。
未来の調査で慌てないために、日々の取引の一つひとつを、証拠資料と共に丁寧に取り扱っていくことが、会社を守る最善の策と言えるでしょう。

