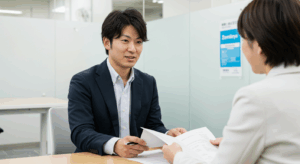この費用、どこまで税務調査で認められる?専門家が解説する経費の限界と対策
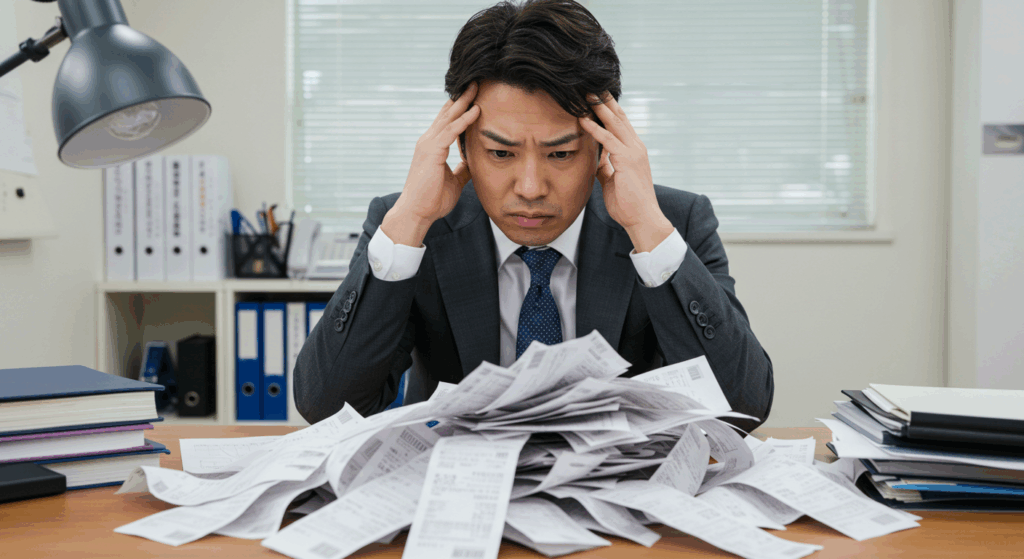
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週月曜日に、経営者なら知っておきたい「税務調査」についての知識を解説しています。
「この費用、どこまで経費で認められるのだろう?」
中小企業の経営者であれば、一度はこんな疑問を抱いたことがあるのではないでしょうか。
特に、ご自身のスキルアップのためのセミナー代や、自宅兼事務所の家賃など、プライベートとビジネスの境界線が曖昧な支出は、税務調査で指摘されやすいポイントの1つです。
もし税務調査でこれらの経費が否認されれば、追徴課税という手痛いペナルティが待っています。
しかし、どこまでが「事業のため」で、どこからが「プライベート」なのか、その線引きは非常に難しい問題です。
そこで本記事では、実際の裁決事例を基に、プライベートとの境界線上にある経費がどのように判断されるのか、そのロジックと具体的な対策を徹底解説します。
この記事を読めば、税務調査で慌てないための知識と、自信を持って経費を主張するためのヒントが得られるはずです。
なぜMBAや博士号の取得費用は経費にならないのか?
経営者としての知見を広げるために、MBA(経営学修士)や博士号の取得を目指す方もいらっしゃるでしょう。
事業に役立つことは間違いありませんが、その学費は経費として認められるのでしょうか。
結論から言うと、ほとんどのケースで否認されると考えられます。
その理由を、歯科医師が博士号を取得した際の学費に関する裁決事例から見ていきましょう。
博士号の取得費用が否認された裁決例(平成13年9月12日裁決)
国税不服審判所は、この博士号取得費用について、以下のように判断しました。
本件学費は、専ら歯科医業という業務の遂行上の必要性に基づき支出されたものというよりも、主として一身専属的な新たな地位である学位の資格を取得するために支出されたものであると認められること、また、学位を取得しなくても、通常、歯科医業の遂行は可能であることから、学位の取得は業務遂行上必要とまではいえない。
したがって、本件学費は、業務遂行上、直接かつ通常必要なものと客観的に認めることはできないので、必要経費に該当しない。
ポイントは「一身専属的」という言葉です。
これは、「その人個人に帰属する能力や地位」という意味です。博士号やMBAは、会社や事業ではなく、取得した経営者個人のものです。
たとえ事業に役立ったとしても、その資格は個人の財産であり、事業と完全に切り離すことができません。
さらに、「博士号がなくても歯科医業はできる」と指摘されている点も重要です。
つまり、「その支出がなければ事業が成り立たない」というレベルの直接的な必要性が求められるのです。
「人的資本の価値増加」という否認ロジック
近年、この「一身専属的」な資格取得費を否認するロジックとして、「人的資本の価値増加」という考え方が判決で示されました。
柔道整復師の資格取得のために専門学校へ支払った学費に関する裁判例です。
大阪地裁令和元年10月25日判決の要旨
- 所得税法は、個人の担税力を増加させる「利得(所得)」に課税するものである。
- 一方で、利得を獲得する能力である**「人的資本の価値増加」については、所得には含めない**。
- 資格取得のための学費は、業務独占資格という「人的資本の価値増加」を得るためのものであり、当時の事業収入を維持・増加させるものではない。
- したがって、必要経費には該当しない。
少し難しいですが、要するにこういうことです。
資格を取ることで、あなた個人の「稼ぐ力(=人的資本)」は上がります。
しかし、その「稼ぐ力」そのものに税金はかかりません。
税金がかかるのは、その力を使って実際に得た所得に対してです。
税金がかからない「価値の増加」のために支払った費用を、課税対象である「所得」から差し引く(経費にする)のはおかしい、というのが裁判所の考え方です。
このロジックに立つと、弁護士や税理士などの士業資格、あるいは学士・修士・博士といった学位の取得費用は、そのほとんどが必要経費として認められないということになります。
YouTuberの衣装代は?公私混同しやすい経費の判断基準
近年は、YouTuberやインフルエンサーのように、ライフスタイルそのものが事業コンテンツとなる業種も増えています。
このような場合、経費の線引きはさらに難しくなります。
ライブチャットサービスを行っていた事業者の、衣服や美容費などが必要経費になるかどうかが争われた事例を見てみましょう。
客観的な証拠がなければ「NO」とされる(平成26年5月22日裁決)
この事例で、パソコンやウェブカメラ、インターネット料金は「業務遂行上必要不可欠」として経費と認められました。
しかし、衣服、水着、ソファー、カーテン、美容費などは否認されています。その理由はどこにあったのでしょうか。
しかしながら、上記各費用のうちパソコンの購入費等以外の各費用については、請求人から本件業務をどのように行っていたのかを明らかにする動画や静止画等の客観的な証拠の提出はなく、当審判所の調査の結果によっても、これを確認することはできない。
(中略)
いずれの費用も客観的にみて本件業務と直接の関係を有し、かつ、本件業務の遂行上必要なものとは認められない。
ここでの最大のポイントは、「客観的な証拠」の有無です。
その衣服や美容費が、本当に事業のためだけに使われたのかを、動画や写真などで証明できなかったのです。
「この服は撮影でしか着ません」と口で主張しても、プライベートで着ている可能性を排除できません。
税務調査では、「100%事業に関連する」と明確に区分できない限り、経費として認めるのは難しい、というのが基本的なスタンスです。
【意外な事例】カウンセリング費用が経費として認められたケース
ここまで、プライベートとの境界にある経費の厳しさについて解説してきましたが、一見プライベート費用にしか見えないものが、経費として認められた意外なケースも存在します。
ある事業者が、カウンセリングサービスを行う会社に支払った手数料が、全額必要経費として認められた事例です。
なぜ「プライベート費用」に見えるものが認められたのか?(平成27年6月17日裁決)
「カウンセリング」と聞くと、個人的な悩みの相談であり、典型的なプライベート費用(家事費)だと考えてしまいます。
しかし、審判所は以下のように判断しました。
平成27年6月17日裁決の要旨
- このサービスは、事業の遂行上生じた創作活動や事業活動に関する諸問題の相談に対し、専門家が具体的な解決策を指導・助言するものだった。
- 時として感情面・精神面に触れることがあっても、それは事業上の問題解決に向けた建設的な指導・助言の一環であり、単なる私的なメンタルケアではない。
- 実際に、このサービスを受けてから事業の収入金額が大幅に増加しており、事業に直接寄与していることが認められる。
この事例から学べる重要なポイントは2つです。
- 名称ではなく実態で判断される「カウンセリング」という名称だけで判断するのではなく、そのサービスの実態が「事業上の課題解決に直接結びつくもの」であったことが重視されました。
- 事業への貢献が客観的に示された実際に「収入が大幅に増加した」という客観的な事実が、その支出が事業遂行上、有効であったことの強力な裏付けとなりました。
つまり、支出の名称や形式ではなく、「その支出が、いかに事業の売上向上に直接貢献したか」を具体的に説明できるかどうかが、運命の分かれ道となるのです。
税務調査の勝敗を分ける「立証責任」の重要性
実は、先ほどのカウンセリング費用の事例には、もう一つ重要な側面があります。
それは、国税側(税務署)の調査が不十分であったと指摘されている点です。
調査担当職員は、(中略)どのような内容のサービスが行われたか詳細な事実認定をも行わずに、当初契約書及び説明文書に記載された一部の文言並びに請求人の申述の一部のみを捉えて、本件サービスは家事費に当たる旨認定したものと認められる。
したがって、原処分庁が(中略)必要経費とならないと判断したことは、十分な証拠に基づかない不合理な認定といわざるを得ない。
本来、税務調査において「この経費は認められない」と主張する場合、その理由を証拠に基づいて証明する責任(立証責任)は、原則として国税側にあります。
この事例では、税務署側がサービスの具体的な内容を十分に調査せず、表面的な情報だけで「これは家事費だ」と判断したため、その処分が取り消されたのです。
このことは、私たちに重要な教訓を与えてくれます。それは、税務調査における対応が、経費の範囲を左右するということです。
グレーゾーン経費を認めてもらうための税務調査対策
立証責任が国税側にあるとはいえ、近年は納税者側にも「これは事業に必要な経費です」と説明する責任が求められる傾向が強まっています。
調査官の言いなりになるのではなく、適切な準備と戦略的な対応が不可欠です。
では、具体的にどうすればよいのでしょうか。
1. 「事業との関連性」を証明する記録を残す
カウンセリングの事例のように、「この支出が売上につながった」というストーリーを語れるように、日頃から記録を残しておくことが最も重要です。
- 契約書・請求書・領収書
但し書きは「お品代」ではなく、具体的な内容を記載してもらいましょう。 - 業務日報や議事録
セミナーやコンサルティングを受けた際は、その内容や、それをどう事業に活かすかを記録しておきましょう。 - 成果を示す資料
コンサルティング費用であれば、その後の売上の推移を示すデータなどを用意しておくと説得力が増します。
これらの客観的な資料が、あなたの主張を裏付ける強力な武器となります。
2. 資料の提出は戦略的に行う
税務調査では、調査官から様々な資料の提出を求められます。
ここで、求められるがままに全ての資料を一度に渡してしまうのは得策ではありません。
調査官は、与えられた情報の中から、課税に有利な部分(つまり、納税者に不利な部分)を探し出そうとします。
一度に全ての情報を渡してしまうと、相手のペースで調査が進み、こちらが不利な状況に陥りかねません。
もちろん、正当な理由なく提出を拒否することはできませんが、質問されたことに的確に答え、求められた資料をその都度提出していくという対応が効果的です。
これにより、調査の主導権を握り、こちらの主張を有利に進めやすくなります。
これは、いわば税務調査における交渉術の一つです。
まとめ
プライベートとビジネスの境界線上にある経費。
それが税務調査で認められるか否かは、以下の3つのポイントにかかっています。
- 事業への直接性
その支出がなければ事業が成り立たない、あるいは、売上に直接貢献すると明確に言えるか。 - 客観的な証拠
事業目的で支出したことを、第三者が見ても納得できる資料(契約書、記録、成果データなど)で証明できるか。 - 調査での的確な主張
立証責任の所在を理解し、準備した資料を基に、戦略的に主張・立証できるか。
MBAの学費のように、個人の能力を高める「一身専属的」な費用は経費になりにくい一方、カウンセリング費用のように、名称はプライベート寄りでも、実態が「事業上の課題解決」であれば経費として認められる可能性は十分にあります。
最終的には、個々の事情に応じた判断となります。
もし、ご自身の経費について少しでも不安があれば、税務調査が来る前に、当事務所まで一度ご相談ください。
事前の準備と対策が、あなたの大切な会社を守ることに繋がります。