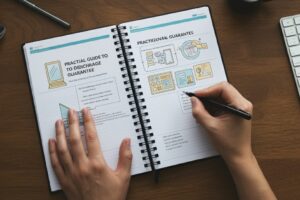サブスク導入で効率化?安定収入の裏に潜む3つの落とし穴と成功への道筋

皆さんこんにちは。クラウド会計で経営支援を提供する千葉の税理士、中川祐輔です。
毎週木曜日に、経営者なら知っておきたい「業務効率」についての知識を解説しています。
「毎月安定した売上がほしい」「顧客との長期的な関係を築きたい」とお考えの中小企業経営者の皆様にとって、
「サブスクリプション(サブスク)」というビジネスモデルは、非常に魅力的に映ることでしょう。
しかし、一見すると夢のようなビジネスモデルにも、その裏には知られざる「光と影」が存在します。
私はこれまで数多くの中小企業のコンサルティングに携わってきましたが、サブスクビジネスで成功を収めるためには、表面的な理解だけでは不十分だと感じています。
本記事では、サブスクビジネスがなぜ今ほど注目され、そしてなぜ安易な導入が危険なのか、その本質と成功の秘訣について、私の経験と知見に基づき深く掘り下げていきます。
継続課金がもたらす安定と落とし穴
「サブスクをやれば、毎月決まった売上が入ってくるから経営が楽になる」――多くの経営者が抱くこの認識は、半分は正しく、半分は誤りです。
確かに、サブスクは一度顧客を獲得すれば、継続的に収益が上がるため、短期的な売上の変動に左右されにくいという大きなメリットがあります。
まるで「毎月決まった金額が入ってくる年金のようなもの」と表現されることもあります。しかし、これはあくまで理想論です。
実際には、顧客がどれだけ継続してくれるか、そしてその継続を維持するためにどれだけのコストがかかるかという現実と向き合う必要があります。
例えば、月額100円のサービスに50人が加入すれば、毎月5,000円の安定収入が見込めます。
もし固定費が5,000円で収まるなら、理論上は「すごい楽」に思えるでしょうが、これは「50人が永遠に継続してくれる」という前提に立っています。
顧客が途中で解約してしまえば、安定収入は途絶えます。
「サブスク=楽」は幻想?高い維持コストと競争激化の現実
私が税理士として働き始めた15年前は、顧問先の会計を見ていても、まだサブスクという言葉や概念は一般的ではありませんでした。
しかし、この5年ほどでサブスクは爆発的に普及し、今や「サブスクは絶対大事」という認識が社会全体に広まりました。
その結果、何が起こったでしょうか?
1. 競争激化による「売りにくさ」
誰もがサブスクを始めるようになったことで、消費者はサブスクに慣れ、同時にその選択肢は爆発的に増えました。
これにより、顧客獲得競争は以前にも増して激化しています。以前は「月額1円」や「月額5円」のような
低価格のサブスクでも比較的容易に顧客を獲得できましたが、今は「単発で500円の商品を売る」のと
「月額100円のサブスクを5ヶ月継続してもらう」のが、同じくらいの難易度になりつつあります。
2. 見えない維持コスト
サブスクは、売ったら終わりではありません。むしろ、そこからが本番です。
顧客に継続して利用してもらうためには、常に価値を提供し続ける必要があります。
- コンテンツ制作・更新コスト
デジタルコンテンツや情報提供型のサブスクの場合、毎月新しいコンテンツを制作し続けなければなりません。
たとえ顧客が一人しかいなくても、そのコンテンツは作らなければならないのです。 - システム開発・運用コスト
SaaS(Software as a Service)のようなシステム提供型のサブスクの場合、
初期開発費用が莫大になるだけでなく、継続的なメンテナンスや機能追加が必要です。
これは、売れるかどうかも分からないものに、大きな先行投資をする「ギャンブル性」をはらんでいます。 - 顧客サポートコスト
継続的に顧客と関わるため、問い合わせ対応やサポート体制の維持も不可欠です。
これらを考慮すると、「サブスク=売上安定=仕事が楽」という単純な図式は成り立ちません。
むしろ、単発商品と比較して、顧客獲得から継続維持、そしてそれに伴う手間とコストがかかることを理解しておく必要があります。
サブスク導入の前に考えるべき「時給」と「購入者リスト」
では、サブスクを成功させるためには、具体的に何をすべきでしょうか。
私がコンサルティングの現場で常にクライアントに伝えているのは、以下の2点です。
1. 自分の「時給」を意識する
例えば、月額100円のサブスクに10人が加入し、毎月1,000円の売上があったとします。
そのコンテンツを制作するのに毎月半日かかるとしたら、あなたの時給に見合うでしょうか?
自分が「納得できる時給」を得るためには、どれくらいの顧客数が必要なのかを具体的に計算してみるべきです。
もし、満足のいく時給を確保するために必要な顧客数が、現状の事業規模では非現実的であれば、サブスク導入は時期尚早かもしれません。
2. まずは「単発商品」で顧客との関係を構築する
サブスクは、顧客との信頼関係が不可欠なビジネスモデルです。
いきなりサブスクを提供しても、顧客は「本当に継続する価値があるのか?」と懐疑的になります。
そのため、まずは単発商品を通じて顧客との接点を持ち、良好な関係を構築していくことが重要です。
- 購入者リストの獲得
単発商品を購入してくれた顧客は、あなたの提供する価値を一度は認めてくれた人たちです。
彼らは、将来的にサブスクに加入してくれる可能性が高い「質の高い見込み客」となります。 - 信頼関係の構築
単発商品の購入を通じて、顧客はあなたの企業やサービスに対する信頼を深めます。
この信頼関係こそが、サブスク継続の最大の鍵となります。
ある程度の購入者リストが蓄積され、彼らがあなたの提供する価値に満足している状態であれば、
「〇〇さんがサブスクを始めるなら、ぜひ利用したい!」という心理が働きやすくなります。
サブスクは「ギャンブル」ではない、計算と覚悟が必要
サブスク導入は、ある意味「ギャンブル性」をはらんでいます。
特にシステム開発を伴うようなケースでは、多額の先行投資が必要になります。
しかし、これを「勢い」や「やってみよう精神」だけで突っ走るのは危険です。
もちろん、新しいことに挑戦する姿勢は重要ですが、ビジネスにおいては「ある程度の担保」が必要です。
単発商品での購入者リストや顧客の反応を元に、サブスクに移行した場合の売上や継続率を仮説立て、収益シミュレーションを行うべきです。
「このくらいの顧客数がいれば、このくらいの売上になり、これなら最低限やっていける」という確固たる見通しを持つこと。
そして、その見通しが外れたとしても、一時的に「ただ働き」が増えることを覚悟し、継続するための「腹を据える」ことが重要です。
昔と今、サブスクの立ち位置の変化
私が税理士として働き始めた頃は、まだサブスクという概念が浸透していなかったため、一度顧客を獲得したら比較的容易に継続していました。
そのため、「とにかく売ってしまえば黒字に転換するから、どんどん行こう!」という戦略が有効な時期もありました。
しかし、今は状況が全く異なります。サブスクはもはや特別なものではなく、消費者の生活に当たり前のように溶け込んでいます。
NetflixやSpotify、Amazonプライムなど、私たちはすでに多くのサブスクサービスを利用しており、
新たなサブスクを契約する際には、その必要性や費用対効果を以前よりもはるかにシビアに判断しています。
つまり、今のサブスクは「あれば素晴らしいもの」であることに変わりはありませんが、「簡単に売れるもの」ではなくなっているのです。
まとめ:サブスク成功へのロードマップ
サブスクは、確かにビジネスの安定化に貢献する強力なツールです。しかし、その導入は慎重に進める必要があります。
中小企業経営者の皆様には、以下のステップを踏まえることをお勧めします。
- 単発商品で顧客基盤を構築する
まずは質の高い単発商品を提供し、顧客との信頼関係を築き、購入者リストを増やすことに注力します。 - 事業の「時給」と採算ラインを見極める
サブスクで提供するサービスのコンテンツ制作や維持にかかる手間とコストを算出し、
どれくらいの顧客数で自分の納得する「時給」が得られるのかを明確にします。 - 具体的なシミュレーションと覚悟を持つ
購入者リストのデータに基づき、サブスクに移行した場合の顧客獲得数、継続率、売上を具体的にシミュレーションします。
そして、初期段階での「ただ働き」や収益の伸び悩みも覚悟し、継続する強い意志を持つことが重要です。
サブスクは、顧客との「長い付き合い」を前提としたビジネスです。
だからこそ、吟味に吟味を重ね、顧客との良好な関係性を土台とした上で導入することが、成功への確かな一歩となるでしょう。