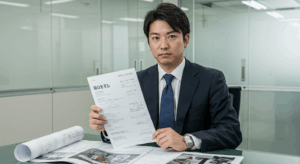新規事業は子会社?別会社?どちらが正しい節税対策なのか
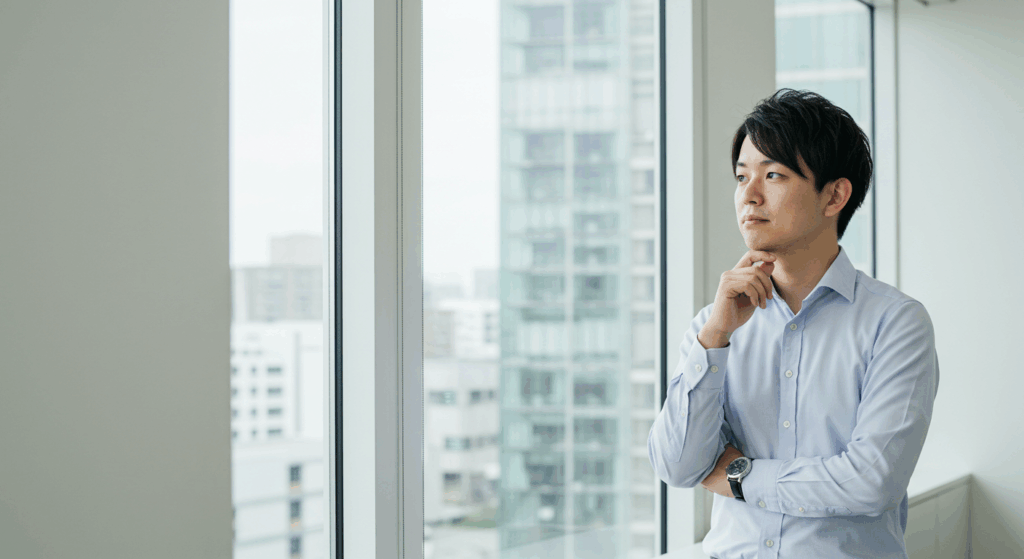
「新しい事業を始めよう」
中小企業の経営者であれば、常に新たな成長の種を探し、事業拡大の機会を伺っていることでしょう。
その際、新事業を「今ある会社の一部門」として始めるか、「子会社」を作るか、それとも「全く別の会社」を設立するか、どのように判断されていますか?
実は、この最初の法人形態の選択が、将来、会社を売却(M&A)する際の経営者の手取り額に数千万円単位の違いを生む可能性があることをご存知でしょうか。
目先の運営のしやすさだけで判断してしまうと、いざという時に「あの時、違う選択をしていれば…」と後悔することになりかねません。
これまで数多くの中小企業経営者様の相談に乗ってきた経験から、今回は「出口戦略」、特にM&Aを見据えた際の最適な法人設立の考え方について、具体的な税額のシミュレーションも交えながら、プロの視点から徹底的に解説します。
この記事を読めば、将来の選択肢を広げ、ご自身と会社の資産を最大化するための戦略的な一歩が踏み出せるはずです。
なぜ「株式譲渡」が税制面で有利なのか?
本題に入る前に、経営者の出口戦略における基本を確認しておきましょう。
会社の出口戦略には、IPO(株式上場)や事業承継など様々な形がありますが、中小企業にとって最も現実的で有力な選択肢の一つがM&Aによる売却です。
そして、この売却において重要なのが「税金」です。
事業の売却益に対してかかる税金は、その手法によって大きく異なります。
- 事業譲渡の場合
会社の事業の一部または全部を売却する方法。
売却益は会社の利益となり、法人税(実効税率 約30%)の対象となります。 - 株式譲渡の場合
経営者個人が保有する株式を売却する方法。
売却益は経営者個人の譲渡所得となり、所得税・住民税合わせて一律約20%の分離課税で済みます。
この約10%の税率差が、最終的な手取り額に大きな影響を与えるのです。
したがって、出口戦略を考える上での大原則は、「経営者個人が株主として、株式譲渡できる形を目指す」ことが税制面で最も有利である、という点です。
この基本を念頭に、次のテーマに進みましょう。
新規事業、子会社と別会社どちらで始めるべきか?
将来、M&Aによる売却の可能性がある新規事業を立ち上げるケースを考えてみましょう。
選択肢は大きく分けて2つあります。
「親会社が出資する子会社」として設立するか、「経営者個人が出資する別会社(兄弟会社)」として設立するかです。
この選択の違いが、将来どれほどのインパクトを持つのか、具体的なシミュレーションで見ていきましょう。
1億円で事業を売却した場合の税金シミュレーション
ここでは、1,000万円の資本金で設立した会社(事業)が順調に成長し、最終的に1億円で売却できたと仮定します。売却による利益(譲渡益)は9,000万円です。
(1)「子会社」として設立していた場合
親会社が100%株主である子会社を売却した場合、その売却益9,000万円は親会社の利益として計上されます。そのため、課されるのは法人税です。
- 計算式:譲渡益 9,000万円 × 法人税率 約30% = 税額 約2,700万円
この場合、売却によって得た資金は親会社に入ります。
経営者個人がその資金を使いたい場合は、役員報酬や配当といった形で引き出す必要があり、そこでもさらに所得税や社会保険料が発生します。
(2)「別会社(経営者個人出資)」として設立していた場合
一方で、経営者個人が100%株主である別会社を売却した場合、その売却益9,000万円は経営者個人の譲渡所得となります。
この場合に課されるのは所得税(分離課税)です。
- 計算式:譲渡益 9,000万円 × 所得税率 約20% = 税額 約1,800万円
このケースでは、税引き後の資金が直接経営者個人に入ります。
両者を比較すると、その差は歴然です。
税額差:2,700万円 – 1,800万円 = 900万円
法人形態の選択一つで、実に900万円もの手取り額の差が生まれるのです。
売却価額がさらに大きくなれば、その差は数千万円にも膨れ上がります。
これが、新規事業を始める際に、将来の出口戦略まで見据えるべき決定的な理由です。
「別会社設立」を推奨する戦略的理由
一般的に、新規事業を開始する際の判断軸は以下の3つに分けられます。
- 同じ会社内で開始する
担当社員や資金は既存の会社のリソースを活用する。 - 子会社を設立する
グループ内でシナジーを生みながら事業を成長させる。 - 別会社を設立する
完全に独立した事業として展開し、売却時の手取り額を最大化する。
実務上、多くの経営者様が手間や管理のしやすさから(1)や(2)を選択しがちです。
しかし、私が経営者様からご相談を受けた際には、その事業内容や目指す規模にもよりますが、全くの別事業であれば(3)の別会社設立を強く推奨しています。
その理由は、単に売却時の手取り額が最大化できるという節税メリットだけではありません。
もう一つの大きな理由は、戦略の柔軟性にあります。
- 事業が成功した場合
他の事業と切り離されているため、売却の交渉がスムーズに進みます。
買い手にとっても、欲しい事業だけをクリーンな形で手に入れられるため、魅力的な案件となりやすいのです。 - 事業がうまくいかなかった場合
万が一事業がスケールしなかった場合でも、後から既存の会社と合併させるなど、打てる手の選択肢が多く残されています。
最初に別会社としておくことで、成功した場合の果実を最大化しつつ、失敗した場合のリスクヘッジも可能になる。
これこそが、私が「別会社設立」をお勧めする戦略的な理由です。
すでに複数事業がある場合の「分社化」という賢い選択肢
「なるほど、新規事業の話はよくわかった。でも、うちは既に一つの会社の中で複数の事業を展開してしまっているんだが…」
そういった経営者様のために、既存の事業を切り分ける「分社化」という選択肢がありますので、ご安心ください。
将来のM&Aを見据えるのであれば、事業ごとに会社を分けておくことには、税制面以外にも大きなメリットが存在します。
なぜ分社化が有効なのか?
分社化を検討すべき理由は、大きく「M&A戦略上のメリット」と「事業運営上のメリット」の2つに分けられます。
M&A戦略上のメリット
前述の通り、特定の事業だけを売却したいと考えた場合、その事業が独立した会社になっていれば「株式譲渡」という有利なスキームが使えます。
もし同一会社内の一事業として存在している場合、売却方法は「事業譲渡」となり、会社の利益として法人税が課されてしまいます。
分社化は、この状況を解消し、節税メリットを享受するための布石となります。
事業運営上のメリット
M&Aを抜きにしても、事業の性格が異なる部門を分社化することには、以下のような経営上の利点があります。
- 正確な損益管理
会社ごとに独立採算が徹底され、どの事業がどれだけ利益を生んでいるのかが明確になります。 - 最適な制度設計
例えば、IT系の事業と製造業系の事業では、働き方や評価制度が全く異なります。
分社化により、それぞれの事業特性に合った社内制度や企業カルチャーを構築しやすくなります。 - 柔軟な給与体系
事業ごとに給与テーブルを分けることで、業界水準に合わせた適切な人材獲得やリテンション(人材定着)が可能になります。
分社化を実現する具体的な手法「会社分割」とは?
では、具体的にどのようにして分社化を進めるのでしょうか。
その代表的な手法が「会社分割」という組織再編の手法です。
専門的な解説は割愛しますが、経営者様が知っておくべき「会社分割」のメリットは以下の通りです。
- 簡易的な手続き
新しく法人を設立し、そこに許認可を取り直し、資産や契約を一つずつ移管していく…といった煩雑な手続きをスキップし、比較的簡易に事業を別会社に移すことが可能です。 - 子会社でも兄弟会社でも設立可能
分割した事業を、元会社の「子会社」にすることも、経営者個人が株主となる「兄弟会社」にすることも可能です。
もちろん、M&Aを見据えるのであれば兄弟会社として設立する方が有利です。 - 従業員の個別同意が不要
事業譲渡の場合、転籍する従業員一人ひとりから個別の同意を得る必要がありますが、会社分割の場合は原則として個別同意は不要です。
これにより、スムーズな人員の移管が実現します。 - 消費税が課されない
新法人を設立してそこに事業譲渡を行うと、資産の譲渡に対して消費税が課される場合がありますが、会社分割のスキームを使えば消費税は課されません。
このように、会社分割は多くのメリットを持つ有効な手段です。
もし分社化によるM&A対策や経営の効率化にご興味があれば、まずは顧問税理士や弁護士といった専門家にご相談されることをお勧めします。
まとめ:未来を見据えた法人戦略で、企業の価値を最大化する
今回は、M&Aという出口戦略から逆算した、最適な法人設立・再編の考え方について解説しました。
- 新規事業を始める際は、将来の売却を少しでも視野に入れるのであれば、経営者個人が出資する「別会社(兄弟会社)」として設立することで、税負担を大幅に軽減できる。
- 既に複数の事業を運営している場合は、「会社分割」という手法を用いて事業ごとに分社化することで、M&Aに備えつつ、事業運営の効率化も図ることができる。
目先の利便性や管理コストだけで法人形態を決定するのは、非常にもったいない選択です。
5年後、10年後を見据えた戦略的な法人設計こそが、経営者であるあなたの努力の結晶である事業の価値を、真に最大化する鍵となります。
ご自身の会社の未来のために、今一度、法人戦略を見直してみてはいかがでしょうか。