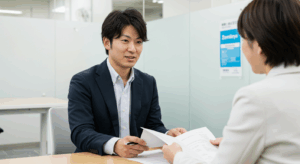「守り」から「攻め」へ転換する所得税の節税対策
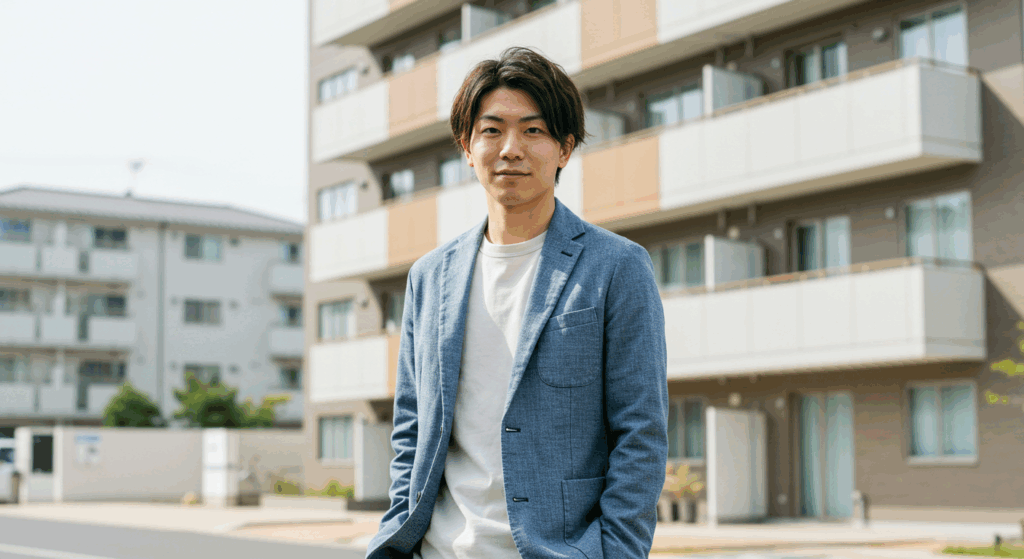
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週水曜日に、経営者なら知っておきたい「節税対策」についての知識を解説しています。
会社の利益を確保するための「法人税対策」に力を入れている経営者の方は多いでしょう。
しかし、その次の一手、つまり経営者個人の手取りを最大化するための「所得税対策」について、どれだけ具体的に設計できているでしょうか?
会社に利益を残すことも重要ですが、最終的に経営者やそのご家族の生活を豊かにするためには、役員報酬などから差し引かれる所得税や住民税を適切にコントロールし、個人の資産形成を加速させることが不可欠です。
税金は、無策のままでは資産形成を妨げる単なる「コスト」でしかありません。
しかし、正しい知識を持ち、戦略的に対策を講じることで、税金の仕組みそのものを「資産を増やすための強力なエンジン」へと変えることができるのです。
本記事では、単なる節税に留まらない、将来の可処分所得を最大化するための所得税対策の考え方と具体的な手法について、実践的に解説します。
なぜ、今「所得税対策」が経営者に必要なのか?
多額の役員報酬を得ていても、その半分近くが税金で消えてしまうという現実に、頭を悩ませている経営者の方は少なくありません。
まずは、なぜ所得税対策が急務なのか、その背景から見ていきましょう。
年収1,000万円の壁と高すぎる税負担の現実
ご存知の通り、日本の所得税は累進課税制度を採用しており、所得が高くなるほど税率も上がっていきます。
特に、年収1,000万円を超えるあたりからその負担は急増し、所得税・住民税を合わせた実効税率は30%〜55%にも達します。
これは、汗水流して稼いだ収入の1/3から半分近くを、何も対策をしなければ税金として納めなければならないことを意味します。
同じ収入であっても、適切な対策を講じているかどうかで、最終的に手元に残る「可処分所得」には数百万円単位の差が生まれるのです。
「何もしないこと」が最大のリスクになる時代
「節税は難しそうだから、とりあえず預金や保険で堅実に…」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、現在の経済状況において、その考え方は深刻なリスクをはらんでいます。
- インフレリスク
昨今の物価上昇により、現金の価値は年々目減りしています。
1,000万円の預金も、数年後には今と同じ購買力を維持できていない可能性が高いのです。 - 為替リスク
円安が進行すれば、輸入品の価格が上昇するだけでなく、相対的に円資産の価値も低下してしまいます。
このような時代において、資産を守り、そして増やしていくためには、現金や預金だけで保有するのではなく、「収入を生み続ける資産を持つこと」が、将来の経済的な安心を手に入れるための鍵となります。
資産形成を加速させる、私が提唱する「4つの視点」
私は、効果的な所得税対策を設計する上で、以下の4つの視点を組み合わせた考え方を非常に重視しています。
これらを連動させることで、単発の節税で終わらない、持続可能な資産形成の仕組みを構築できるのです。
- 自己資金(融資の活用)
手元の自己資金が少なくても、融資を戦略的に活用することで、レバレッジを効かせた大規模な投資が可能になります。
これにより、資産形成のスタートダッシュを加速させることができます。 - 税効果(課税所得の圧縮)
減価償却や消費税還付といった税制上のメリットを最大限に活用し、課税対象となる所得を効果的に圧縮します。
これが直接的な節税効果を生み出します。 - 収入(黒字化できる投資)
節税効果だけを追い求めるのではなく、長期的に安定した収益(キャッシュフロー)を生み出す、利回りの良い投資対象を選ぶことが極めて重要です。
これにより、将来的な手取り収入の向上に直結します。 - 複利(雪だるま式に資産を増やす)
投資から得られた収益や、税効果によって還付された資金を、再び次の投資に回します。
この再投資のサイクルを繰り返すことで、資産が雪だるま式に増えていく「複利効果」を最大化します。
この私の考え方は、守りの節税ではなく、将来の資産を積極的に増やしていくための「攻めの設計図」なのです。
所得税を直接的に圧縮する具体的な手法
では、この考え方を、具体的にどのような手法で実践していくのでしょうか。
ここでは、特に効果の高い2つの手法をご紹介します。
手法1:事業所得の損失を給与と合算する「損益通算」
経営者個人の所得税対策として非常に有効なのが、太陽光発電事業や不動産投資といった実物資産への投資です。
これらの事業で生じた会計上の損失(赤字)を、役員報酬などの給与所得と合算できる「損益通算」という制度を活用します。
例えば、不動産投資では、建物の購入費用を数年間にわたって経費計上できる「減価償却」により、初年度に会計上の大きな赤字を計上することが可能です。
この赤字を給与所得から差し引くことで、課税所得全体を大幅に圧縮できます。
課税所得=給与所得−事業の損失(減価償却費など)
結果として、その年の所得税が大幅に減額され、翌年の住民税も安くなるという直接的なメリットを享受できるのです。
手法2:初期投資を早期に回収する「消費税還付」
太陽光発電事業など、大規模な設備投資を伴う事業においては、初期投資にかかった消費税の還付を受けられる可能性があります。
これは、資産形成の初速を大きく高める強力なブースターとなり得ます。
実際にあったケースでは、1基2,000万円の太陽光発電設備を5基(合計1億円)導入した際に、最大で1,250万円もの消費税が還付されました。
この還付金を、ただ消費してしまうのではなく、次の投資の原資として活用することでどうなるでしょうか。
ここで「複利」の効果が働き、資産規模を当初の計画の数倍にまで拡大させることも夢ではありません。
現金信仰は危険?将来の安心に繋がる資産の持ち方とは
これまで見てきたように、所得税対策は単に税金を減らす行為ではありません。
税制を味方につけて効率的に資産を形成し、インフレや円安といった経済リスクから自分と家族を守るための、極めて重要な生存戦略です。
繰り返しになりますが、これからの時代は、現金(預金)で資産を持つことよりも、「収入を生み続ける資産を持つこと」の方が、はるかに将来的な安心に繋がります。
もちろん、すべての資産を投資に回すべきだというわけではありません。
しかし、高所得者であるがゆえに重い税負担を強いられている経営者の方々こそ、その税負担を軽減しながら資産ポートフォリオを構築できる、一石二鳥の対策を積極的に検討すべきなのです。
まとめ:所得税対策は、未来の自分への最高の投資
所得税対策は、目先の税金を減らすための小手先のテクニックではありません。
それは、将来のゆとりある生活を実現するための“設計図”そのものです。
現役でバリバリ働けるうちに、会社の利益だけでなく、個人の資産形成にも目を向け、適切な行動を取ること。
それが、10年後、20年後の自分と家族の金銭的な不安を大きく軽減し、人生の選択肢を広げることに繋がります。
この記事が、あなたの資産形成戦略を見直すきっかけとなれば幸いです。
ご自身の状況に最適なプランを設計するためには、専門的な知識と経験が不可欠です。
ぜひ一度、専門家にご相談されることをお勧めします。