「中小企業事業再編投資損失準備金」を活用する節税対策
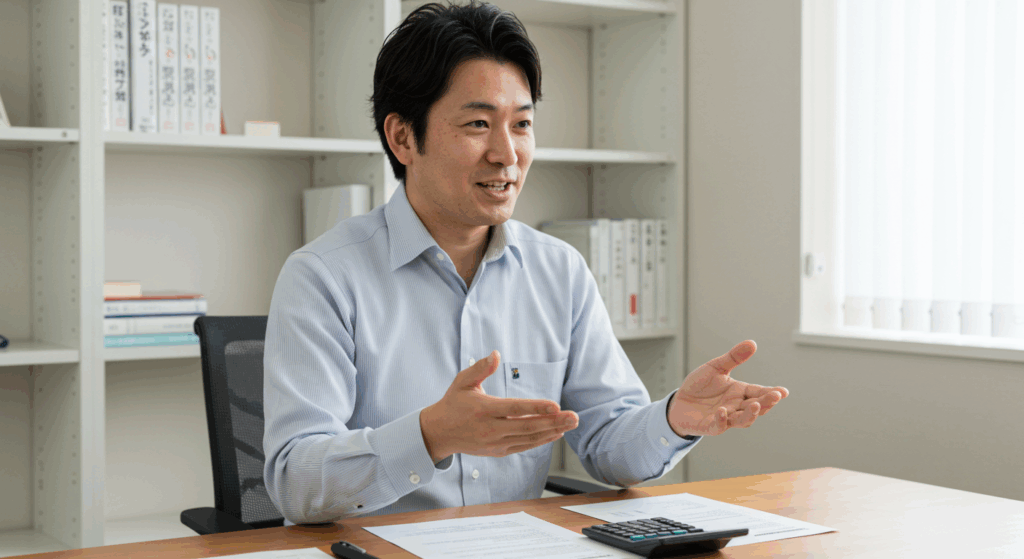
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週水曜日に、経営者なら知っておきたい「節税対策」についての知識を解説しています。
中小企業経営者の皆様、事業拡大を志す上で、オーガニックな成長だけでなくM&Aを一つの選択肢として検討されている方も少なくないでしょう。
しかし、M&Aが単なる事業拡大の手段に留まらず、実はダイナミックな節税策となり得ることをご存知でしょうか?
ほとんどの経営者が知らないこの「中小企業事業再編投資損失準備金」は、M&Aを検討する上で見過ごせないメリットをもたらします。
今回は、この画期的な制度の概要から、実際に活用するための具体的なステップ、そして注意点までを、深く掘り下げて解説していきます。
買収金額の最大100%が損金に!驚きの節税効果とは?
通常、会社や事業の買収(M&Aにおける株式取得など)は、その買収金額が直接経費(損金)となることはありません。
しかし、「中小企業事業再編投資損失準備金」を活用することで、買収金額の最大100%を、買収時の経費(損金)に算入することが可能になります。
具体的なイメージを掴んでいただくために、5億円の買収(株式買取り)を実施した場合を考えてみましょう。
- 初期のキャッシュフロー改善効果
5億円の買収(株式買取り)を実施した場合、90%にあたる4.5億円が買収時の損金となります。
もし当期に3億円の利益が出ていれば、本来約1億円発生する法人税はゼロになります。
さらに、1.5億円のマイナスは翌期に繰り越され、将来の税負担を軽減します。
これは、M&A実行後のキャッシュフローを大幅に改善する効果があります。 - 課税の繰延べ効果
損金算入された金額は、10年後から5年間かけて均等に益金として課税の対象となります。
つまり、実質的には10年後の課税の繰延べ効果ですが、M&Aを実行した時点での税負担を劇的に軽減し、手元の資金を事業成長に再投資できるメリットは計り知れません。 - 2回目以降のM&Aによる優遇
もし、この制度適用期間中に2回目のM&Aを実施する場合、損金算入割合は90%ではなく100%に引き上げられます。
これは、継続的なM&Aによる成長戦略を国が後押ししている証拠とも言えるでしょう。 - 対象となるM&Aの規模
ただし、1億円未満の買収は対象外となりますが、最大100億円までと、非常に大きな枠が設けられています。
これは、中小企業がより積極的なM&A戦略を展開できるよう、国が政策的に促進している表れです。
この制度は、実は令和3年から実施されていましたが、
以前は「1~10億円の範囲内」「損金算入割合は70%」「据置き期間は5年間」と限定的だったため、適用実績はわずか20件に留まっていました。
しかし、昨年の要件大幅緩和により、中小企業の皆様にとって、より現実的で魅力的な選択肢となっています。
M&Aを成功に導く!「経営力向上計画」申請の重要性
この画期的な節税制度を適用する上で、最も重要なポイントは、M&Aを実行する【前に】国に対する申請を行い、認定を受けなければならないということです。
もし、この事前申請をせずにM&Aを実行してしまうと、せっかくの節税効果は得られません。
顧問税理士との連携がカギ
「そんな大事なこと、顧問税理士が教えてくれるはずだ」と思われるかもしれません。
確かに、M&Aを検討していることを事前に顧問税理士に相談していれば、顧問税理士も「事前に申請しましょう」とアドバイスしてくれるでしょう。
しかし、もし相談なしにM&Aを実行し、事後報告となれば、顧問税理士も対応しようがありません。
M&Aは水面下で進むケースも少なくありませんが、この制度を活用するためには、早期の段階での情報共有と連携が不可欠です。
「経営力向上計画」作成から認定までのタイムライン
この制度を適用するために、事前に対応しなければならない時間軸は以下のようになります。
- 買収(M&A)の相手方と協議開始
- 双方の合意形成と基本合意契約の締結
- このタイミングで「経営力向上計画」を作成し、官公庁へ提出します。
- 提出後、正式な認定を受けます。
- デューデリジェンス(DD)の実施
- M&Aを実施するかどうかを双方で最終的に協議します。
- M&Aの最終合意(株式譲渡契約の締結など)
- 官公庁へのM&A実行に関する報告・確認書の発行
- 「経営力向上計画」に沿ったM&Aが実行されたことを報告し、確認書の発行を受けます。
- 確認書をもって税務申告
- この段階で、初めて節税効果が適用されます。
申請手続きで注意すべきこと
上記の流れから、特に気を付けるべき点は以下の通りです。
- M&A実施前の顧問税理士への相談
M&Aを検討する段階で、早い段階から顧問税理士に相談し、「経営力向上計画」の作成・提出を依頼することが重要です。 - 「経営力向上計画」の内容精査
「経営力向上計画」は、顧問税理士に任せきりにするのではなく、その内容を自社内で詳細に詰め、M&Aの目的や効果、事業シナジーなどを具体的に記述する必要があります。
計画内容に不備や齟齬があると、認定を受けるまでに時間を要することが多く、M&Aの手続き上の時間的な余裕がない場合、申請・認定が間に合わない可能性もあります。 - 税理士の経験値の確認
現実的な話として、この制度の適用を経験したことがある税理士は、まだほとんどいないのが現状です。
中には、この制度自体を知らない税理士も少なくありません。
そのため、顧問税理士の対応にかなりの時間がかかる可能性も考慮しておくべきでしょう。
まとめ:M&Aを通じた成長と税負担最適化の追求
「中小企業事業再編投資損失準備金」は、国がM&Aを積極的に促進するための政策的な制度であり、中小企業の皆様が事業拡大と同時に税負担を最適化できる、非常に有効な手段です。
この制度を最大限に活用し、M&Aによるダイナミックな成長を実現するためには、早期の情報収集と適切な計画、そして専門家との綿密な連携が不可欠です。
M&Aは、単なる企業の売買に留まらず、貴社の未来を切り拓く戦略的な一手です。この制度を賢く活用し、次なる成長フェーズへとステップアップしませんか?
具体的なM&A戦略の立案から、「経営力向上計画」の策定、そして税務申告までのサポートについて、ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

