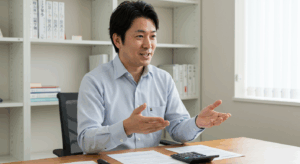経営者保証の解除を後押しする個人資産の活用術

皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週金曜日に、経営者なら知っておきたい「銀行融資」についての知識を解説しています。
通常、金融機関は融資に対して経営者保証を設定することで、貸し倒れリスクを最小限に抑えようとします。
しかし、保証の設定によって経営者個人の資産や信用力が常にリスクにさらされる状態が続くのは、経営者にとって大きな負担です。
保証解除を実現するためには、当然ながら会社の業績や財務内容が重要になりますが、経営者個人の資産状況が大きな判断材料となるケースは少なくありません。
潤沢な個人資産を保有している経営者であれば、金融機関も「保証を外しても、返済の原資となる資産は用意できるだろう」とみなしやすくなります。
本記事では、そうした保証解除の交渉時に役立つ「個人資産の活用術」について、具体的なポイントや注意点を踏まえながら解説します。
資産状況の適切な開示
まず、経営者保証の解除交渉を有利に進めるうえで大切なのが、「個人資産の開示」です。
経営者の個人資産は、会社の事業や財務データだけでは把握しきれない部分を補う指標となるため、貸し倒れリスクが下がるかどうかを判断しやすくなります。
経営者の個人資産としては、預金や有価証券、不動産、生命保険など、さまざまな種類があります。
これらを示すときには、以下のような資料が効果的です。
- 預金残高証明書(全取引金融機関の分)
- 不動産登記簿謄本
- 株式や投資信託などの取引残高報告書
- 生命保険証券のコピー
このような書類を通じて、経営者自身がどの程度の資産規模を持っているか、どのような形態で資産を保持しているかを伝えることができます。
ただし、単に「資産が多いから安心だ」というアピールだけではなく、資産内容を具体的に示して「返済原資になり得るかどうか」をイメージさせることが重要です。
また、過度な隠し立てや後出しの開示は逆効果になる場合があります。経営者保証を外そうとしているのに、資産に関する不透明な要素があると金融機関の不信感を招くからです。
そうした点を踏まえ、正直かつ根拠ある資料で資産全体を開示する姿勢が求められます。
資産の適正評価
個人資産を保証解除の交渉材料として提示するにあたり、次に重要なのが「資産の評価額が適正かどうか」です。
金融機関としては、提示された資産が実際にどの程度の価値があるのかを正しく把握したいと考えます。
たとえば、不動産であれば「路線価ベース」なのか「実勢価格ベース」なのか、担保設定が既に行われている場合は「どの程度の余力があるのか」を知りたがります。
こうした点を正確に示すためには、不動産鑑定士などの専門家による評価書を取得することが効果的です。
評価書があれば、過大評価や過小評価とみなされにくくなり、客観的な裏づけとして金融機関との交渉に活用できます。
特に不動産を複数所有している場合は、それぞれの物件について鑑定を依頼することが望ましいでしょう。
また、複数の鑑定士に依頼すれば評価方法や評価金額にブレがないかをチェックできます。
適正な評価を行ううえでは、以下の点に留意する必要があります。
- 実勢価格ベースで評価を検討し、路線価だけに依拠しない
- 不動産鑑定士による客観的な評価書を活用する
- 既存担保がある不動産は、担保余力を明確に示す
過度に大きい評価をしてしまうと「実際はそんなに値がつかないのではないか」という疑念を呼び、金融機関の不信感につながります。
逆に価値を小さく見積もりすぎても、本来は高い資産価値があるのにアピールに失敗してしまいます。
実態に即した公正な評価を行うことが、保証解除を目指す交渉では不可欠です。
資産の機動的な保全
経営者の個人資産を保証解除の交渉材料に使う以上、「万が一のときにすぐ債務弁済に充てられるか」という点も金融機関にとっては大切な評価基準になります。
たとえ資産をたくさん持っていても、流動性があまりに低かったり、資産が毀損するリスクが大きかったりすると、実質的な返済原資として期待しづらいからです。
そこで重要になるのが、資産を「機動的に保全する仕組み」を整えておくことです。
必要に応じて資産を現金化し、債務の弁済に振り向けられる準備があるということを示すのは、金融機関の安心材料になります。
また、資産価値が急激に下がったり、不測の事態で処分できなくなったりするリスクを最小限に抑えることも重要です。
以下のような保全策は、実務上もよく取り入れられています。
- 不動産の証券化(不動産投資信託への組み込みなど)
- 株式の信託設定(相続・贈与税対策としても有効)
- 生命保険の活用(死亡保険金の非課税枠や契約者貸付制度など)
これらの手法を活用することで、資産を会社の債務と切り離して保全しながら、いざというときには現金化して弁済に回す道を確保できるわけです。
こうした対策を講じている姿勢を見せるだけでも、金融機関に対する説得力は大きく高まります。
資産に関するリスク管理
個人資産を保証解除の交渉に活用するのであれば、当然ながら「その資産価値を維持できるか」が問われます。
資産価値が大きく毀損してしまうと、借入金返済の原資としての確実性が低下し、金融機関との交渉力も下がってしまいます。
したがって、資産の形態ごとに適切なリスク管理を行うことは、経営者の責務といえるでしょう。
そうしたリスク管理の具体策としては、以下のようなものがあります。
- 不動産の定期的なメンテナンス(修繕計画の策定など)
- 株式ポートフォリオの分散投資(一極集中によるリスク回避)
- 為替リスクのヘッジ(海外資産を持つ場合)
- 地震保険や火災保険の適切な加入(災害リスクへの備え)
これらのリスク管理を適切に行い、資産価値を守り続ける姿勢を金融機関に伝えることは、保証解除の交渉において大きな信頼材料になります。
経営者自身としても、個人資産が毀損すれば会社経営にも悪影響を及ぼしかねないため、日常的なチェック体制と専門家の活用が重要です。
まとめ:個人資産の有効活用が保証解除を後押しする
以上のように、経営者の個人資産は、保証解除の交渉を大きく前進させるための重要な材料になります。
会社の事業内容や財務状況が健全であることは大前提ですが、そこに「個人資産という裏付け」が加わることで、金融機関の安心感と信頼感をより強固なものにできるのです。
具体的には、
- 資産状況を適切に開示し、金融機関の安心感を高める
- 資産の実勢価値を適正に評価し、過大評価や過小評価を避ける
- 資産を機動的に保全し、弁済原資として活用できる環境を整える
- 資産に関するリスク管理を徹底し、資産価値の毀損を防ぐ
といったポイントを実践することが求められます。
これらを着実に行うことで、金融機関に対して「いざというときに返済が確保できるだけの個人資産と、その保全および運用体制がある」と示すことができるでしょう。
また、個人資産を戦略的に活用することは、単に「経営者保証を外す」ためだけでなく、会社経営そのものの安定化にも寄与します。
資金繰りに窮した場合でも、個人資産を使って金融機関と柔軟な交渉ができる体制があれば、会社が倒産リスクに陥る可能性を軽減できます。
さらに、適切なリスク管理によって資産価値を守りながら運用できれば、経営者自身の将来の資産形成にもつながるでしょう。
経営者保証は、経営者にとって精神的にも経済的にも大きな負担となりますが、それを解除するためには、金融機関の信頼を勝ち得るだけの準備と戦略が欠かせません。
個人資産の開示と保全策、そしてリスク管理に関する取り組みが十分に整っていれば、その努力が金融機関への説得材料となり、結果として経営者保証の解除実現に近づくのです。
ぜひ、本記事で紹介したポイントを参考に、経営者保証の解除を目指すうえでの個人資産の活用を検討してみてください。
なお、今回紹介したような「経営者保証解除」に関する最新の情報や細かい事例などは、無料メルマガで紹介しています。
こちらも参考にしていただき、もし疑問点や不安な点があれば、お気軽にお問い合わせください。