銀行融資の常識を覆す!短期借入金と長期借入金の最適なバランスとは?
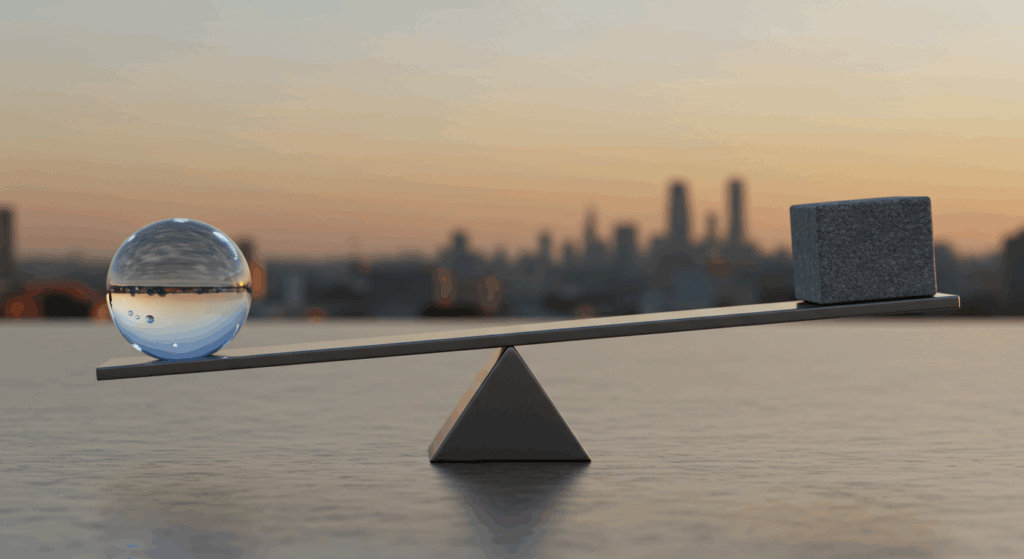
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週金曜日に、経営者なら知っておきたい「銀行融資」についての知識を解説しています。
「利益は出ているはずなのに、なぜか手元にお金が残らない…」
「追加の設備投資が必要だが、これ以上返済が増えたら資金繰りが回らない…」
中小企業の経営者の皆様から、このような切実なご相談をいただくことが少なくありません。
銀行融資は事業成長に不可欠な一方、その「借り方」一つで、会社の資金繰りを大きく左右する諸刃の剣でもあります。
もし、「借入総額が2億円から4億円に倍増したにもかかわらず、年間の返済額は2,600万円から約半分になった」という事例があるとしたら、皆様はどう思われるでしょうか。
今回ご紹介するのは、銀行融資の「常識」を少しだけ見直すことで、資金繰りを劇的に改善させる「最適な借り方」の考え方と、それを実現した具体的な交渉戦略です。
なぜ銀行は「最適な借り方」を提案してくれないのか?
多くの中小企業では、運転資金も設備資金も、まとめて長期借入で賄っているケースが見受けられます。
しかし、実は金融機関自身も、これが必ずしも企業にとって最適解ではないことを理解しています。
例えば、政府系金融機関である商工中金のホームページには、「運転資金は短期で、設備資金は長期で調達するのが基本」という趣旨の内容が明記されています。
これは、事業を継続する上で恒常的に必要となる運転資金は、元本返済の負担がない短期継続融資(手形貸付や当座貸越など、短期の借入を継続的に利用する方法)を活用する方が、企業の資金繰りは安定するという考え方です。
では、なぜ多くの銀行は積極的にこの方法を提案してくれないのでしょうか。そこには、金融機関が抱えるジレンマがあります。
金融機関には、「企業の安定した発展に貢献したい」という公共的な使命がある一方で、「融資を実行し、利息や手数料を得て業績を上げなければならない」という営利企業としての側面もあります。
返済期間が長い長期融資は、金融機関にとって安定した収益源となるため、業績目標を達成するためには、運転資金も含めて長期での貸付を提案せざるを得ない、という事情があるのです。
決して、担当者個人が悪いわけではありません。彼らも組織の一員として、こうした相反する役割の中で、日々の提案活動を行っているのです。
だからこそ、融資を受ける側の経営者が「自社にとって最適な借り方」を理解し、主体的に交渉していくことが何よりも重要になります。
資金繰りを安定させる「最適な借り方」の基本
ここで、改めて「最適な借り方」の考え方をご説明します。
これは、借入金をその目的によって2種類に分け、それぞれに最適な借り方を適用するアプローチです。
- ① 運転資金 → 短期継続融資で固定化
- 運転資金とは
商品の仕入れや人件費の支払いなど、事業を日常的に回していくために必要な資金のこと。
売上が入金されるまでの間、一時的に立て替える性質のものです。 - 最適な借り方
常に一定額が必要となる運転資金は、元本の返済負担がない「短期継続融資」や「当座貸越」を活用します。
これにより、毎月の返済額を抑え、資金繰りを圧迫する要因を取り除くことができます。
- 運転資金とは
- ② 設備資金など → 長期借入で返済計画を立てる
- 設備資金とは
工場の建設や機械の購入など、長期にわたって使用する固定資産を取得するための資金のこと。 - 最適な借り方
投資の回収期間に合わせて、無理のない返済計画を立てられる「長期借入(証書貸付)」を活用します。
重要なのは、自社のキャッシュフロー(事業活動によって生み出される現金)の範囲内で返済できるペースに設定することです。
- 設備資金とは
この2つを明確に区別し、借入を最適化するだけで、企業の資金繰りは驚くほど安定するのです。
【実例】借換で資金繰りを劇的に改善した製造業のケーススタディ
言葉だけではイメージが湧きにくいかもしれませんので、私が実際にサポートさせていただいた製造業の事例をご紹介します。
【ビフォー】追加融資で破綻の危機に瀕した状況
- 企業概要
製造業、売上高 約8億円 - 借入状況
A, B, C, Dの4行から合計2億円を借入 - 資金繰り
年間返済額が2,600万円。
一方、本業で生み出すキャッシュフローは年間1,500〜1,600万円。
毎年1,000万円ずつ会社の現金が減っていくという、極めて危険な状態でした。
利益は出ていたものの、借り方の問題で資金繰りが悪化していたのです。
そんな中、工場の建て替えで「どうしても追加で2億円が必要」というご相談を受けました。
現状のまま追加融資を受ければ、返済額は年間5,000万円を超え、事業継続は不可能になる、まさに崖っぷちの状況でした。
【アフター】「単・長最適」による劇的な変化
私は社長に「最適な借り方」の考え方をお伝えし、借換の交渉をサポートしました。
この会社で必要な運転資金は8,000万円でしたので、これを短期継続融資で固定化し、残りの借入(既存分+追加融資分)はキャッシュフローに見合った返済ペースに組み直すことを目標としました。
その結果が、以下の通りです。
- 借換後
D銀行に借入を一本化。- 運転資金
8,000万円を短期継続融資(返済負担なし)に固定化。 - 設備資金等
残りの3億2,000万円をキャッシュフローに合わせた長期借入に再編。
- 運転資金
- 資金繰りの変化
- 借入総額
2億円 → 4億円(倍増) - 年間返済額
2,600万円 → 約1,300万円(半減)
- 借入総額
さらに驚くべきことに、この取り組みから約2年後、この会社は経営者保証の解除にも成功しました。
社長からは「借入が倍になったのに返済は半分になり、おまけに保証まで外すことができた」と、大変喜んでいただけました。
「銀行に嫌われるのでは?」経営者が抱く“一本化”への不安を解消する交渉術
この事例をお話しすると、多くの経営者様が「一行にまとめると、他の銀行に恨まれて今後の付き合いが絶たれてしまうのではないか」と懸念を示されます。
特にお世話になった銀行の借入を全額返済することに、強い抵抗を感じる方も少なくありません。
お気持ちは痛いほど分かります。しかし、ビジネスの世界では、時にドライな判断が必要です。
よく「銀行は晴れた日に傘を貸し、雨が降ったら取り上げる」と言われますが、これは銀行を悪く言うためではなく、彼らが業績という指標で動く組織であるという事実を示しています。
業績が良ければ融資を提案してくれますし、悪くなれば、これまでの関係性に関わらず返済を求められることもあります。
担当者も3年ほどで異動することを考えれば、過去の義理人情に縛られすぎて資金繰りを悪化させては元も子もありません。
重要なのは、全ての取引銀行に対して、誠実に、そして公平に交渉することです。
今回の事例で、私から社長にお伝えした交渉のポイントは以下の通りです。
- 交渉の優先順位を明確に伝える
金融機関に伝える条件の優先順位は「①返済ペース>②保全(担保や保証)>③金利」であると、ハッキリ伝えることが重要です。
「金利が多少高くなっても構わないので、とにかくキャッシュフローに合わせた返済ペースと、できるだけ良い保全条件を提示してほしい」と、4行全てに同じ内容で依頼しました。 - 全行から提案を受け、最も良い条件を選ぶ
特定の銀行を贔屓するのではなく、全行に同じ土俵で競ってもらいます。
これにより、交渉は非常に公平かつスムーズに進みます。
最終的に最も自社にとって有利な条件を提示してくれた銀行を選びます。 - 断る銀行への配慮を忘れない
お断りすることになった銀行には、「今回はD銀行の条件が最も良かったため、そちらにお願いすることにしました。しかし、毎年融資条件は見直す方針です。もし来年、D銀行より良い条件をご提案いただけるのであれば、またまとめてお願いする可能性もございます。ぜひ今後とも変わらぬお付き合いをお願いします」とお伝えいただきました。
このアプローチは、無理に金融機関を苦しめるものではありません。
むしろ、自社の経営方針を明確に示し、フェアな土俵で交渉する姿勢は、金融機関からの信頼を高めることにも繋がります。
交渉で評価が上がる?銀行が本当に付き合いたい経営者とは
交渉後、社長が最も驚いていたのは、断った銀行の反応でした。
恨まれるどころか、ある銀行の担当者からは「非常に勉強になりました。言われるがままに借りるのではなく、しっかりとした考えのもとで経営を安定させようとする社長とこそ、我々も付き合っていきたいと改めて思いました」という言葉をいただいたそうです。
これは、経営者が正しい知識を持ち、主体的に経営をコントロールしようとする姿勢が、金融機関からの評価を高めるという何よりの証拠です。
交渉をためらう必要はまったくありません。むしろ、企業の未来を真剣に考えるからこその行動は、信頼される経営者への第一歩となるのです。
まとめ:資金繰り改善は始まりに過ぎない
今回ご紹介した「最適な借り方」による借換戦略は、あくまで資金繰りを安定させるための第一歩です。
安定した財務基盤を築くことで、初めて、精度の高い経営改善計画の策定や、未来に向けた投資戦略の検討といった、より本質的な経営課題に取り組むことができます。
もし、自社の借入状況に少しでも不安を感じたり、今回の記事内容に関心を持たれたりした場合は、ぜひ一度、顧問の会計事務所や我々のような専門家にご相談ください。
返済ペースの適正化は、目先のキャッシュフローを改善するだけでなく、金融機関との良好な関係を再構築し、会社の持続的な成長を実現するための重要なターニングポイントとなるはずです。

