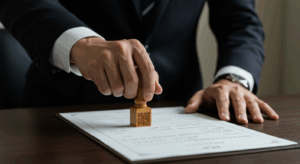なぜ儲かっているのにお金がない?銀行融資を成功に導く「運転資金」の正しい考え方
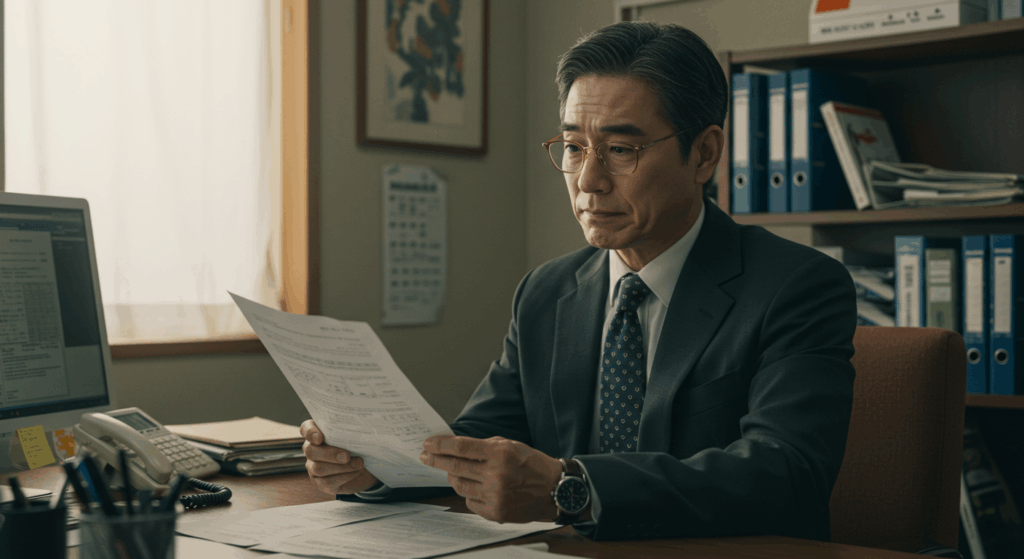
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週金曜日に、経営者なら知っておきたい「銀行融資」についての知識を解説しています。
多くの経営者様が「運転資金が足りないので融資をお願いしたい」と考え、銀行に相談された経験があるのではないでしょうか。
しかし、その「運転資金」という言葉、実は本来の意味とは少し違うニュアンスで使われているケースが少なくありません。
今回は、数々の企業の資金調達をサポートしてきた税理士の視点から、運転資金の本来の意味から、金融機関への融資申込に役立つ具体的な計算方法まで、分かりやすく解説していきます。
この記事を最後までお読みいただくことで、自社の資金繰り状況を正確に把握し、銀行担当者にも「この経営者は自社のことをよく理解している」と信頼される、説得力のある説明ができるようになります。
安定した経営基盤を築くための第一歩として、ぜひご一読ください。
その「運転資金」、本当に正しい意味で使っていますか?
まず、経営者の皆様に質問です。ご自身が「運転資金」と言うとき、具体的にどのような費用をイメージされていますか?
多くの方が、事務所の家賃や従業員の給与、水道光熱費といった、日々の事業運営に必要な「経費の支払い」を思い浮かべるかもしれません。
もちろん、それらも事業を継続する上で不可欠なお金です。
しかし、ファイナンスの世界、特に銀行融資の場面で使われる「運転資金」は、これらとは明確に区別される、もっと本質的な資金を指します。
商売において、最もリスクが小さい取引はどのような形でしょうか。
それは、「お客様から注文を受けてから商品を仕入れ、代金を支払う前に、お客様から入金してもらう」ことです。
これならば、在庫を抱えるリスクも、代金を回収できないリスクもありません。
しかし、現実のビジネス、特に事業を拡大し売上を伸ばしていくフェーズでは、このような取引は稀です。
多くの場合、競争力を高めるために、
- 先に商品を仕入れて在庫を持つ(先行投資)
- お客様には後払いを認める(掛売り)
という形を取るのが一般的です。
このとき、商品の仕入れ代金を支払ってから、お客様からの売上金が入金されるまでの間に、タイムラグが生まれます。
この期間、会社は一時的にお金を「立て替え」ている状態になります。
この「立て替えられているお金」こそが、運転資金の正体です。
銀行に融資を申し込む際に、この「なぜ立て替え資金が必要なのか」という原理原則を理解し、自社の状況を説明できなければ、「この経営者は自社の財務状況を正しく把握できていないのでは?」という不信感を与えかねません。
まずは、この正しい定義をしっかりと押さえることが、融資成功への第一歩となります。
運転資金の正体は3つの要素で決まる
では、運転資金(=立て替えられているお金)は、具体的にどのような要素で構成されているのでしょうか。
それは、以下の3つの勘定科目で構成されています。
1. 売上債権(売掛金、受取手形など)
商品を先にお客様へ提供し、代金の回収を待っている状態のお金です。
これは、見方を変えれば、あなたがお客様に「無利息でお金を貸している」のと同じことと言えます。
入金を待っている間、そのお金は他の支払いに使うことができません。
2. 棚卸資産(在庫など)
将来販売するために仕入れた商品や原材料が、倉庫で眠っている状態です。
お金が「商品」という形に変わり、売れるまで現金化されない資産です。
これも、会社のお金が「寝ている」状態と言えます。
3. 仕入債務(買掛金、支払手形など)
商品を先に仕入先から受け取り、支払いを待ってもらっている状態のお金です。
これは売上債権とは逆に、あなたが仕入先から「無利息でお金を借りている」のと同じ状態です。
支払いを猶予してもらっている分、手元の資金には余裕が生まれます。
これらの関係を整理した、以下の計算式が「経常運転資金」の正しい定義となります。
【運転資金の計算式】
運転資金=売上債権+棚卸資産−仕入債務
この計算式によって、事業を回していくために、常にどれくらいの資金が「立て替え」として必要になるのかを、金額として把握することができます。
「儲かっているのに、お金がない」の正体は“収支ずれ”
運転資金を理解する上で、もう一つ非常に重要なポイントがあります。
それは、「運転資金は、売上高に連動して増減する」という性質です。
事業が順調に成長し、売上が伸びている状況を想像してみてください。
これは経営者にとって喜ばしいことですが、同時に注意が必要です。
なぜなら、売上が増えれば、それに伴って仕入れる在庫の量(棚卸資産)も増え、お客様への掛売り(売上債権)も増加するからです。
極端に言えば、売上が10倍になれば、必要となる運転資金も約10倍になる可能性があります。
つまり、「売れば売るほど、追加の運転資金が必要になる」のです。
これが、多くの成長企業が直面する「黒字倒産」のリスクの根源にあります。
ここで登場するのが「収支ずれ」という概念です。
これは、「利益が出たタイミング」と「実際に手元にお金が入ってくるタイミング」のずれが、どれくらいの期間で発生するかを示す指標です。
この“ずれ”の期間が長ければ長いほど、会社の資金繰りは苦しくなります。
「損益計算書上は利益が出ているのに、なぜか手元の現金はいつもカツカツだ…」という現象の正体こそ、この「収支ずれ」なのです。
自社の資金繰り状況を可視化する「回転期間」とは?
では、自社の「収支ずれ」は、具体的にどれくらいの期間なのでしょうか。
これは、決算書を使って簡単な計算をすることで、誰でも明らかにすることができます。
そのために用いるのが、以下の3つの「回転期間」です。
① 売上債権回転期間
商品を販売してから、その代金が現金として入ってくるまでの平均的な期間です。
いわゆる「入金サイト」に近い概念です。
この期間が長いほど、資金の回収が遅いことを意味します。
計算式:
売上債権回転期間(ヶ月)=平均月商売上債権
② 棚卸資産回転期間
商品を仕入れてから、お客様に販売されるまでの平均的な期間です。
いわゆる「在庫期間」です。
この期間が長いほど、商品がお金に変わるまでの時間が長い(在庫が寝ている時間が長い)ことを意味します。
計算式:
棚卸資産回転期間(ヶ月)=平均月商棚卸資産
③ 仕入債務回転期間
商品を仕入れてから、その代金を支払うまでの平均的な期間です。
いわゆる「支払サイト」です。
この期間が長いほど、支払いを待ってもらえる期間が長く、資金繰り上有利になります。
計算式:
仕入債務回転期間(ヶ月)=平均月商仕入債務
※平均月商 = 年間売上高 ÷ 12
これらの回転期間を計算することで、自社の商習慣(入金サイト、在庫管理、支払サイト)が、資金繰りにどのような影響を与えているかを客観的な数値で把握できます。
「収支ずれ期間」の計算方法と、その意味を理解する
3つの回転期間が算出できたら、いよいよ「収支ずれ」の期間を計算します。
計算式は非常にシンプルです。
【収支ずれの計算式】
収支ずれ期間(ヶ月)=①売上債権回転期間+②棚卸資産回転期間−③仕入債務回転期間
この計算式は、先に紹介した運転資金の計算式 (売上債権+棚卸資産-仕入債務) が、月商の何ヶ月分に相当するかを示しているのと同じことです。
例えば、計算の結果、あなたの会社の収支ずれ期間が「2ヶ月」だったとします。
これは、何を意味するのでしょうか。
それは、「今月100万円の利益が出たとしても、その利益がまるまる現金として手元に残るのは、2ヶ月後になる」ということを意味します。
この2ヶ月間、会社は利益がまだ現金化されていない状態で、仕入れ代金や給与、家賃などの支払いをこなしていかなければなりません。
このタイムラグを埋めるために必要となるのが、ほかでもない「運転資金」なのです。
自社の収支ずれの期間を正確に把握することは、必要な運転資金額を論理的に算出し、健全な資金繰りを維持するための第一歩と言えるでしょう。
まとめ:明日からできる資金繰り改善の第一歩
今回は、銀行融資を考える上で最も基本となる「運転資金」について、その本質的な考え方と具体的な計算方法を解説しました。
複雑に思えるかもしれませんが、ポイントは以下の2つです。
- 運転資金とは、事業活動における「立て替え資金」である。
その金額は、売上債権 + 棚卸資産 − 仕入債務 という式で計算できることを理解しましょう。 - 「儲かっているのにお金がない」原因は、「収支ずれ」にある。
自社の「収支ずれ期間」を回転期間から計算し、利益と現金の動きのタイムラグを把握しましょう。
まずは一度、お手元の決算書(貸借対照表と損益計算書)を使って、ご自身の会社の運転資金額と収支ずれ期間を計算してみてはいかがでしょうか。
自社の財務状況を数字で客観的に捉えることが、的確な経営判断と、説得力のある融資申込につながります。
ご不明な点や、具体的な資金繰り改善に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。