銀行格付けの真実:事業性評価時代に求められる融資戦略
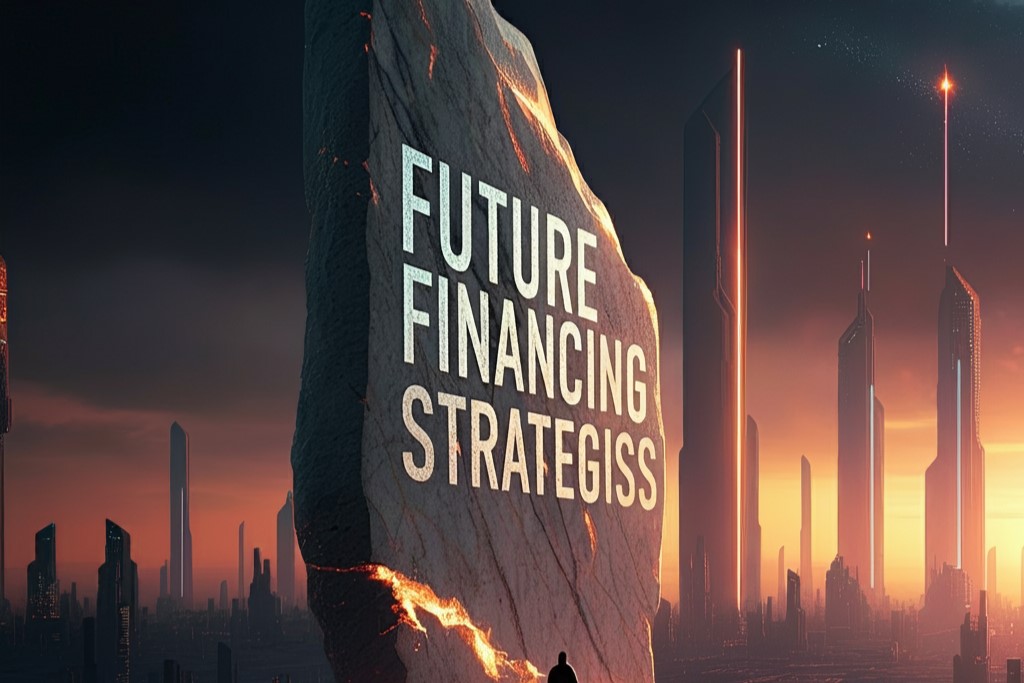
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週金曜日に、経営者なら知っておきたい「銀行融資」についての知識を解説しています。
近年、金融庁が提唱している「事業性評価」が徐々に浸透してきたことに伴い、銀行の融資姿勢は大きく変わりつつあります。
具体的には従来の「担保・保証」に依存した融資から、「企業の事業力」や「成長可能性」を見極める融資へとシフトしています。
本記事では「事業性評価の時代」に焦点を当て、これからの経営者に求められる融資戦略をわかりやすく解説していきます。
事業性評価時代の本質
まずは、事業性評価時代の本質を押さえておきましょう。
これまでの融資は、担保や保証、財務データなど「目に見える価値」を基準としていました。
しかし、事業性評価の時代には、企業が持つ「目には見えにくい価値」にも注目が集まります。
技術力、ノウハウ、人材、顧客基盤などの無形資産の活用や、成長の可能性が、融資判断に大きく影響するようになっているのです。
以下では、金融機関の評価基準と企業側に求められる対応の変化について、それぞれ詳しく見ていきます。
金融機関の評価基準の変化
金融機関の評価基準は、従来の財務データ中心の評価から、より多角的で総合的な視点へと変わっています。
具体的には、次のようなポイントが重視されるようになりました。
- 事業モデルの持続可能性
過去の数字だけでなく、ビジネスモデルが将来にわたって成立し続けるかどうかが、金融機関の関心を集めています。 - 市場における競争優位性
業界内でのポジショニングや差別化要因など、競合他社との差を明確に示す必要があります。 - 経営者の課題解決力
問題が生じたとき、どのような手段や戦略を用いて解決を図るのか、といった経営者の力量が評価材料となります。
こうした評価基準の変化は、金融機関が企業を長期的視点で支援し、成長をバックアップする姿勢へとシフトしていることの表れです。
特に中小企業の場合は、「いかに成長戦略を具体的に示すか」「その戦略を実現できるだけの経営資源を確保できるか」が、大きく関係してきます。
求められる対応の変化
銀行側の評価基準が変われば、当然ながら企業側の対応も変わらざるを得ません。
これまでは担保や保証に頼りきりであったり、過去の実績を見せて「融資してもらうのを待つ」姿勢でもなんとか通用していました。
しかし、事業性評価の時代には、以下のような能動的な対応が求められます。
- 事業の強みの明確化
自社の強みを言語化し、第三者にも理解しやすい形で示す必要があります。
単なるPRではなく、具体的かつ客観的な根拠を提示することが重要です。 - 経営課題への取り組み姿勢
潜在的な課題にどのように向き合い、解決策を考えているかが問われます。
たとえ数値がまだ伴わなくても、取り組む姿勢が評価につながる場合もあります。 - 情報開示の質的向上
財務諸表だけでなく、事業計画書や経営レポートなど、質の高い情報を開示することが重視されます。
自社の取り組みや将来像を論理的に整理し、情報開示によって「わかりやすく伝える」ことが鍵です。
以上のようなポイントを踏まえて、経営者自身が今の事業モデルを冷静に見直し、魅力や課題を客観的に評価できるようになることが大切です。
そのうえで、金融機関と積極的に対話し、必要な支援やアドバイスを引き出す力が求められます。
今後の金融環境の変化
銀行が重視する評価基準だけでなく、そもそも金融を取り巻くマクロ環境が大きく変わりつつあります。
低金利政策が長期間続いた日本でも、金利の先行きが不透明になりはじめ、資金調達コストに変化が生じる可能性があるのです。
さらに、フィンテックをはじめとするデジタル化の進展により、企業が金融機関と接する方法そのものも変化しようとしています。
ここでは、マクロ環境の変化と金融機関の融資スタンスについて整理してみましょう。
マクロ環境の変化
金利政策の見直しやデジタル化の加速など、企業を取り巻く金融環境はかつてないスピードで変化しています。
特に、金利面では超低金利状態が転換する局面が見えはじめており、借入による資金調達のメリットやリスクが従来と変わる可能性が出てきました。
加えて、オンライン融資やAI審査などの新しい仕組みも急速に普及しつつあります。
デジタル化の波が金融機関の業務を大きく変え、従来の「担当者との面談重視」から「システムを通じた迅速な審査」へと移行する事例が増えています。
金融機関の融資スタンス
マクロ環境の変化に対応するため、金融機関自体も融資スタンスをアップデートしています。
最近では、以下のような動きが顕著です。
- より踏み込んだ経営支援
金融機関が融資だけでなく、経営課題の共有や改善提案などにも積極的に関わるケースが増えています。 - デジタルデータの活用
銀行側が企業の売上や在庫などのリアルタイムデータを把握し、融資判断に生かすといった取り組みが広がっています。 - 業界特性の重視
画一的な基準だけでなく、飲食業や製造業、IT企業など、それぞれの業界特性や地域性を考慮した評価を行う傾向が強まっています。
こうした融資スタンスの進化は、企業にとってはチャンスでもあります。
以前は見過ごされがちだった非財務的な取り組みなども、金融機関から好意的な評価を得られる可能性が高まっているのです。
経営者が準備すべきこと
急激に変化する金融環境や評価基準に対応するためには、従来以上に経営者が主体的に準備を整える必要があります。
特に、自社の事業価値を多面的に示せるような体制づくりが欠かせません。
非財務面での強みを「数字や実績とセット」でわかりやすく表現できるようにしておくことが求められます。
情報発信力の強化
最初の大きなポイントは、自社の強みを外部に向けて効果的に伝えるための情報発信力を高めることです。
以下のような取り組みによって、金融機関に対しても説得力のあるアピールが可能になります。
- 経営の見える化
社内外に対して目標や施策がどのように進んでいるかを明確にし、結果を共有する仕組みを整えます。
数値管理だけでなく、プロセス面での改善・工夫についても情報を蓄積すると説明がしやすくなります。 - 経営計画の具体化
計画を作るだけで満足せず、実行フェーズまで落とし込むための具体的な施策、想定リスクへの対応策を示します。
計画と実績の差異を定期的にチェックし、必要に応じて修正するPDCAサイクルの徹底が重要です。 - 定性的情報の整理
技術力やノウハウ、人材育成、取引先との関係など、財務諸表には表れにくい強みを可視化し、伝えられる形でまとめます。
例えば、社員の資格取得状況や特許・実用新案の保有数、取引の長さや評価実績などを数値で示すと、金融機関にとっても評価しやすくなります。
このように、財務面と非財務面の両方から自社を捉え直し、価値を「わかりやすく提示する」ことで、銀行からの印象や評価が向上します。
経営基盤の強化
もう一つ重要なのは、事業の持続可能性を高めるための経営基盤の整備です。
銀行が企業を評価する際、経営の安定性やリスク管理体制は欠かせないチェックポイントとなります。
- ガバナンス体制の整備
意思決定プロセスを透明化し、リスク管理やコンプライアンスへの取り組みを整備しておくと、外部からの信頼度が高まります。
社外役員の登用などにより、経営の客観性を担保する仕組みを検討する企業も増えています。 - 人材・組織の強化
後継者育成や組織体制の構築、人材育成プログラムの整備は、金融機関から見ても「将来性が高い企業」であることを示す材料となります。
特に中小企業では、経営がオーナーに集中しがちなため、組織として持続的に成長できる仕組みをつくることが望ましいとされています。
こうした基盤強化の取り組みが「企業の信頼力」として評価される傾向はさらに強まっています。
これからの資金調達戦略
従来は銀行借入が主流でしたが、近年はファンドやクラウドファンディング、社債の発行など、資金調達の手法が多様化しています。
これまで以上に、「自社にとって最適な調達手段は何か」を冷静に検討し、組み合わせて活用することが重要です。
多様な調達手段の活用
銀行借入のみでは、企業の成長に必要な資金を十分に確保できないケースもあります。
そのため、下記のように多様な選択肢を視野に入れ、リスクとリターンを見極めながらポートフォリオを組む企業が増えています。
- ファンドの活用
ベンチャーキャピタルや事業再生ファンドなど、事業の成長をバックアップする目的で資金を出してくれる存在を活用する手段です。 - クラウドファンディング
新商品の開発や地域活性化プロジェクトなど、社会的な共感を得やすいテーマで支援を募ることで、資金だけでなく認知度向上にもつなげられます。 - 社債の発行
企業の信用力に応じて社債を発行し、中長期的な資金を安定的に確保する選択肢も見逃せません。
特に社債発行は「社外ステークホルダーとの関係性を強化する」きっかけにもなる可能性があります。
金融機関との関係進化
銀行借入以外の調達手段を組み合わせながらも、金融機関との関係をより深いレベルへ進化させることが、これからの時代の重要なポイントです。
経営課題の共有やネットワークの紹介など、金融機関が持つ多彩なリソースを有効活用することで、事業成長のスピードを加速させられます。
- 経営課題の共有
銀行と定期的に経営課題をすり合わせることで、新たなアイデアや解決策を得られる可能性があります。 - 成長戦略の協議
今後の事業拡大の方向性や、具体的な投資計画について金融機関と協議することで、適切な支援や提案を受けやすくなります。 - ネットワークの活用
銀行は地域経済や他業種とのパイプを持っていることが多く、ビジネスマッチングなどを通じて販路拡大や業務提携につながるチャンスを得られます。
銀行を「お金を貸してくれるところ」として見るだけでなく、「経営パートナー」として位置づけると、企業としての可能性が大きく開けるでしょう。
おわりに
金融庁の提唱する「事業性評価」が広まりを見せる中、担保や保証に偏らない融資の仕組みが整いつつあります。
これは企業にとって「経営全体を見直し、積極的に情報開示を行う」努力が必要になる時代でもあります。
経営環境の変化は激しく、金利政策の動向やフィンテックの進化、SDGs対応など、外部要因によって企業が直面する課題は多様化しています。
しかし、こうした時代だからこそ、経営者が主体的に戦略を練り、外部との連携を深めることで、企業の成長余地は大きく広がるはずです。
事業性評価のポイントを押さえたうえで、柔軟かつ戦略的な資金調達を実現することが、これからの中小企業にとって極めて重要なテーマになります。
ぜひ本記事の内容を参考に、自社の強みや課題を改めて整理し、これからの時代の融資戦略を構築してみてください。
きちんと準備を行い、情報を分かりやすく発信していけば、必ず金融機関との関係も深まっていくはずです。

