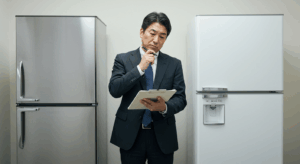社長の手取りを最大化する究極の節税対策は「出口戦略」です

皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週水曜日に、経営者なら知っておきたい「節税対策」についての知識を解説しています。
中小企業の経営者であるあなたは、日々「いかにして会社の利益を出すか?」そして「経営者個人として、いかにお金を残すか?」という2つの大きなテーマと向き合っておられることでしょう。
日々の資金繰りや人材育成、新規顧客開拓など、目の前の課題に追われる中で、ご自身の「引退」や会社の「出口」について具体的に考える時間は、なかなかないかもしれません。
しかし、もしあなたが手元に残る資産を最大化したいと本気で考えるなら、この「出口」から逆算して経営戦略を考える視点が不可欠です。
実は、相続税対策を含めた長期的な節税は、この経営者の「出口戦略」と密接に結びついています。
本記事では、究極の資産形成ともいえる「出口戦略」について、具体的な選択肢と比較、そして税制上のメリットまでを詳しく解説します。
あなたの出口はどれ?経営者が選べる5つの未来
経営者としてのキャリアの終着点、すなわち「出口」には、大きく分けて5つの選択肢しかありません。
- 廃業
ご自身の代で事業を終わらせる選択です。
会社に残った資産から借入金をすべて返済し、手元にお金が残るのであれば、決して悪い選択肢ではありません。 - 倒産
経営者が積極的に選ぶものではなく、借入金を返済できなくなるなど、資金繰りが立ち行かなくなった場合に、やむを得ず迎える結末です。 - 事業承継
ご自身が引退した後も、会社を存続させるための選択肢です。
お子様などに継がせる「親族内承継」と、役員や従業員に引き継ぐ「親族外承継」があります。 - 売却(M&A)
第三者である他の会社に、自社を売却する方法です。 - 上場(IPO)
株式を証券取引所に公開し、誰でも売買できるようにすることです。
「廃業」や「倒産」を除き、会社を存続させることを前提とするならば、あなたの未来は「事業承継」「売却(M&A)」「上場(IPO)」の3つに絞られます。
では、この中で最も現実的、かつ経営者の利益に繋がりやすい選択肢はどれなのでしょうか。
なぜ「M&A(会社売却)」が現実的な選択肢なのか?
結論から言えば、多くの中小企業経営者にとって、「M&A(会社売却)」が最も合理的で、検討すべき選択肢になるケースが非常に多いのが実情です。
その理由を、他の選択肢と比較しながら見ていきましょう。
事業承継の壁
親族内に後を継ぐ意思と能力のある方がいれば幸運ですが、現代では後継者不在に悩む企業が後を絶ちません。
では、親族ではない役員や従業員に継いでもらう「親族外承継」はどうでしょうか。
この場合に大きなハードルとなるのが、自社株の買取資金です。
経営権を譲るためには、あなたが保有する株式を後継者に買い取ってもらう必要があります。
しかし、長年かけて価値を高めてきた自社株の評価額は、一個人が用意できる金額をはるかに超えていることがほとんどです。
この資金調達の問題が、親族外承継を非常に困難なものにしています。
上場(IPO)の本当の目的
「上場して、一気に億万長者に」というイメージをお持ちの方もいるかもしれません。
確かに、新規上場(IPO)のタイミングで保有株式の一部を売り出せば、創業者利益として大きな資金を手にすることができます。
しかし、注意しなければならないのは、上場は「出口戦略」というより「事業をさらにスケールさせるための資金調達手段」であるという点です。
そして、上場後に大株主である創業経営者が、市場で自由に株式を売却するのは極めて困難です。
なぜなら、経営者が大量の株を売却すれば、「経営者が自社の将来に自信がないのでは?」というメッセージとして市場に受け取られ、株価が暴落する要因になりかねません。
これは、他の株主の利益を損なうだけでなく、結果的に自身の資産価値を毀損することにも繋がります。
このように、事業承継の難しさや上場の実情を考慮すると、「子供に後を継がせる選択をしない・できない」経営者が、築き上げた会社の価値を最大化して引退するためには、「M&A(会社売却)」が最も現実的な選択肢として浮かび上がってくるのです。
【衝撃の事実】役員報酬より手残りが圧倒的に多い「株式売却」という選択
では、出口をM&Aに定めた場合、経営者個人には具体的にどれほどのメリットがあるのでしょうか。最大の利点は、税制上の圧倒的な優位性にあります。
近年、事業を立ち上げては売却し、その資金を元手にまた新たな事業を始める「シリアルアントレプレナー(連続起業家)」という存在が注目されていますが、彼らがなぜこの手法を取るのか。その核心は税率にあります。
役員報酬と株式売却益の税率比較
経営者として個人資産を増やす最も分かりやすい方法は、役員報酬を上げることです。
しかし、ご存知の通り、役員報酬には所得税・住民税が課され、その税率は収入が上がるほど高くなる「累進課税」です。
最高税率は合計で55%にも達します。さらに、高額な役員報酬には重い社会保険料もかかってきます。
結果として、額面の半分近くが税金や社会保険料で引かれてしまう、という事態も珍しくありません。
一方で、M&Aによる株式の売却益(譲渡所得)にかかる税金は、「分離課税」という方式が適用され、税率は一律で20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)です。
| 役員報酬 | 株式売却益 | |
| 税率 | 累進課税(最大55%) | 一律 約20% |
| 社会保険料 | かかる | かからない |
例えば、会社の価値が5億円と評価され、株式を5億円で売却できたとしましょう。この場合、手元に残る金額は、税金を差し引いて約4億円です。
毎年数千万円の役員報酬を受け取り、そこから高い税率で納税していくことと比較すれば、最終的な手残りの差は歴然です。
この税制は、ある意味で「労働所得」よりも「資本所得」を優遇する仕組みになっていると言えます。この事実を知れば、経営戦略は大きく変わるはずです。
「個人」ではなく「会社」を太らせるべき本当の理由
「個人の役員報酬をできるだけ抑え、利益は会社に貯め込む(内部留保)。そして、十分に価値が高まった会社を売却する」
これが、経営者の手元資金を最大化するための黄金律です。M&Aを具体的な目標として設定していなくても、この「会社を太らせる」という発想は、経営において非常に重要です。
メリット1:将来収益の“先食い”
M&Aにおける会社の売却価格は、どのように決まるのでしょうか。
一概には言えませんが、大まかには「会社の経常的な利益額 × 将来の年数(3年~7年など)」という計算式で算出されることが多くあります。
例えば、毎年1億円の利益を安定して出している会社であれば、「1億円 × 5年分 = 5億円」といった価格がつく可能性があるのです。
経営者の視点から見れば、今期1億円の利益が出たとしても、来期、再来期の利益は誰にも保証できません。
しかし、M&Aによって会社を売却するということは、買い手側が将来のリスクを負い、売り手であるあなたは不確実な将来数年分の収益を「前倒し」で、かつ「一括」で手にすることができるのです。
これを、私たちは「将来収益の先食い」と呼んでいます。
メリット2:法人の与信力向上
M&Aをすぐには考えていない場合でも、会社に利益を貯めるメリットは計り知れません。
その最たる例が、銀行からの与信(信用力)です。
あなたが個人として銀行から借入できる金額には限りがあります。
しかし、財務体質が健全で、自己資本が厚い「強い会社」であれば、その信用力は個人の比ではありません。
数億円、数十億円といった規模の融資も可能になります。
どちらの与信を高めるべきか、どちらの所得(個人の所得か、法人の所得か)を上げるべきかは、このことからも明白でしょう。
会社の与信力を高めることは、より大きな事業展開を可能にし、結果として会社の価値をさらに高め、将来のM&Aにおける売却価格の上昇にも繋がります。
まとめ:出口から逆算する経営戦略が、あなたの資産を最大化する
日々の節税対策、例えば経費の適切な計上や各種控除の活用ももちろん重要です。
しかし、経営者として生涯にわたって築き上げる資産を最大化するためには、より長期的で、より大きな視座が求められます。
それが、「出口から逆算して、今やるべきことを考える」という経営戦略です。
ご自身の引退後、会社をどうしたいのか。その選択肢の中で、ご自身の利益を最大化できるのはどの方法か。
そして、その選択肢を実現するためには、どのような財務体質の会社にしておくべきか。
今回ご紹介したM&Aは、単に会社を手放すというネガティブなものではありません。
ご自身が人生をかけて育て上げた事業の価値を最大化して評価してもらい、その対価を元に、次の豊かな人生をスタートさせるための、極めて有効でポジティブな戦略です。
この記事が、日々の経営に奮闘されるあなたにとって、ご自身のキャリアと会社の未来を改めて考えるきっかけとなれば幸いです。