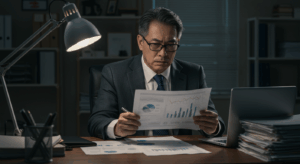税務調査で否認されない!交際費と広告宣伝費の境界線とは?

皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週月曜日に、経営者なら知っておきたい「税務調査」についての知識を解説しています。
「この経費、交際費にすべきか、広告宣伝費にすべきか…」
経理処理をしていると、そんな風に迷うことはありませんか?
特に、得意先への贈答品やイベントへの招待費用などは、どちらにも解釈できそうで判断に悩むことが多いものです。
実は、この「交際費」と「広告宣伝費」の区分は、税務調査で非常に厳しくチェックされるポイントの一つです。
もし、広告宣伝費として処理していたものが税務調査で交際費と認定されると、損金に算入できる金額が制限され、結果的に追徴税額が発生する可能性があります。
そこで本記事では、交際費と広告宣伝費の区分について、国の通達や過去の裁判例・裁決例を基に、経営者の皆様が実務で使えるレベルまで掘り下げて解説します。
なぜ区分が重要?交際費と広告宣伝費の基本的な考え方
そもそも、なぜこの二つの費用を厳密に区別する必要があるのでしょうか。
それは、税務上の取り扱いが大きく異なるからです。
- 広告宣伝費
原則として、全額を損金(経費)に算入できます。 - 交際費
資本金の額などに応じて、損金に算入できる金額に上限が設けられています。
つまり、広告宣伝費にできれば節税効果は大きいですが、誤って計上すると税務調査で指摘されるリスクがあるのです。
では、税法ではどのように区分しているのでしょうか。根拠となる通達を見てみましょう。
租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)-9
不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用(後略)
この通達から、広告宣伝費と認められるためには、以下の2つの要件を満たす必要があることがわかります。
- 不特定多数の者に対するものであること
- 宣伝的効果を意図するものであること
この2つの要件が、税務調査における最大の論点となります。
以下で、それぞれを詳しく見ていきましょう。
論点①:「不特定多数の者」とは誰のことか?
まず最初の要件である「不特定多数の者」とは、具体的に誰を指すのでしょうか。
原則は「一般消費者」
判例では、「不特定多数の者」とは「通常継続して取引することが予定されていない最終消費者」、つまり一般的な消費者を指すとされています。
これを裏付ける有名な裁判例があります。漬物メーカーが、得意先である卸売業者や小売業者などを対象に、購入金額に応じて韓国旅行や電化製品をプレゼントした費用の扱いです。
大阪高裁昭和56年1月23日判決(要旨)
招待や贈呈の基準を見ると、不特定多数である一般消費者を対象としていたとは到底認めがたい。特定の得意先や、今後得意先になることを期待できる者を対象とした費用は、支出の相手方や行為の性質から見て、交際費に該当する。
この判決が示すように、自社の商品を仕入れて消費者に転売する卸売業者や小売業者は、「特定の取引先」と見なされます。
たとえ広告宣伝の意図があったとしても、これら特定の事業者への支出は原則として交際費として扱われる可能性が高いのです。
【応用編】事業の特殊性が考慮されるケースも
ただし、この「不特定多数」の考え方は、常に一般消費者だけを指すわけではありません。企業の事業内容によっては、判断が異なる場合があります。
語学関係の教科書を出版する会社が、大学の担当教授に販促目的で狭山茶を送付した事例を見てみましょう。
昭和50年7月21日裁決(要旨)
教科書の出版社という販路が限定されている特殊性を考慮すれば、潜在的な採用可能性のある者を含めて一律に配布していることから、狭山茶を送付した担当教授等は不特定多数に該当する。主として広告宣伝効果を意図した配布と認めるべきであり、特定の得意先と解することは相当でない。
この裁決のポイントは、事業の特殊性です。大学の教科書は、採用する教授の判断が売上に直結します。
そのため、潜在的な顧客である全国の大学教授は、この会社にとっては「不特定多数」の広告対象と認められたのです。
自社のビジネスモデルにおいて、広告宣伝の対象が誰になるのかを相対的に判断する必要がある、ということを示唆する重要な事例です。
論点②:「宣伝的効果」は客観的に判断される
次に、2つ目の要件である「宣伝的効果を意図する」についてです。
これは、「宣伝のつもりでやりました」という主観的な意図だけでは不十分で、その行為の外形から客観的に判断される必要があります。
祝賀の意図が強ければ交際費
例えば、取引先の開店祝いに社名入りの花輪を贈るケースです。
社名が入っているため宣伝効果も期待できますが、税務上はどう判断されるのでしょうか。
静岡地裁平成7年10月13日判決(要旨)
花輪等の贈呈行為が祝賀の意思を表すことを主たる目的とすることが推認される以上、自社の宣伝目的を併せ有していたというだけでは、交際費と解することの妨げとはならない。広告宣伝費とするためには、贈呈の主たる目的が広告宣伝であると客観的に判断され得るような外形的事実関係がなければならない。
つまり、お祝いの気持ちを表すという「交際」の目的が主であると客観的に判断される場合、たとえ宣伝効果があったとしても、その費用は交際費になるということです。
同様に、社名の入った看板を掲示した野球場の年間予約席を購入し、そのチケットを得意先に渡していたケースでは、「看板は小型で入場者の目安程度」とされ、広告宣伝効果は認められず交際費と判断されています(昭和46年6月12日裁決)。
広告宣伝が主目的であると認められるには?
では、どのような場合であれば「主たる目的が広告宣伝」と認められるのでしょうか。
先ほども登場した、教科書出版社が狭山茶を送付した裁決が参考になります。
昭和50年7月21日裁決(要旨)
狭山茶は、社名等が記載された簡易な紙製パックで包装され、配布の際には出版物のカタログやパンフレット等を同封して送付している。これらの事実と会社の特殊性を合わせ考えると、狭山茶は教材テキストの販売促進のための広告宣伝的効果をより一層高める意図のもとに配布されたものと認めるのが相当である。
この事例では、以下の点がポイントになりました。
- 贈答品(狭山茶)自体は、簡易な包装で高価なものではない
- 必ず広告宣伝物(カタログ等)と一緒に送付している
このように、接待や贈答の側面があくまで付随的なものであり、誰が見ても「主目的はカタログやパンフレットを見てもらうことだな」と客観的に判断できる状況であれば、広告宣伝費として認められる余地が出てくるのです。
実務上の最重要対策は「記録」を残すこと
ここまで見てきたように、交際費と広告宣伝費の区分は、非常に個別性が高く、曖昧な部分も多いのが実情です。
最終的には、その支出の目的がどこにあるのかが問われます。
- 購買意欲の直接的な刺激にあるのか → 広告宣伝費
- 取引関係を円滑にするなど、企業活動の遂行を円滑に行うことにあるのか → 交際費
税務調査で指摘を受けた際に、「これは広告宣伝目的でした」と口頭で主張しても、客観的な証拠がなければ認められません。
そこで重要になるのが「記録」です。支出をする際には、稟議書や社内メモなどに、以下の点を具体的に記録しておくことを強くお勧めします。
- 支出の目的(例:新商品の認知度向上のため、〇〇キャンペーンの一環として)
- 対象者(例:当社の潜在顧客となりうる、〇〇業界の企業リストに基づき選定)
- 期待する効果(例:同封したカタログからの問い合わせを〇件獲得する)
こうした一手間が、万が一の税務調査の際に、自社の主張を裏付ける強力な武器となります。
【補足】カレンダーや手帳など少額物品の取り扱い
最後に、年末の挨拶回りなどで渡すカレンダーや手帳、タオルといった物品の扱いについて補足します。
これらは、以下の要件を満たすものとして、交際費の範囲から除かれる広告宣伝費的な性格のものとして認められています。
- 多数の者に配付することを目的とする
- 主として広告宣伝的効果を意図する
- その価額が少額であるもの
この「少額」の基準について、法令で明確な金額が定められているわけではありません。
しかし、実務上は「1,000円以下」が一つの目安とされています。
これは、過去の税務当局者の解説(社名入りテレホンカードの単価が1,000円以下なら交際費から除かれる、など)が根拠となっているようです。
この1,000円という基準は絶対的なものではありませんが、社名入りの記念品などを作成する際には、一つの安全ラインとして意識しておくと良いでしょう。
まとめ:判断に迷ったら専門家へ相談を
今回は、税務調査の重要論点である「交際費と広告宣伝費の区分」について、具体的な判例や裁決例を交えながら解説しました。
- 広告宣伝費の要件は「不特定多数」への「宣伝効果」
- 「不特定多数」かは、原則(一般消費者)と例外(事業の特殊性)がある
- 「宣伝効果」は、客観的に見て主目的が広告宣伝である必要がある
- 対策の基本は、支出の目的を稟議書などで「記録」に残すこと
- 少額な記念品は「1,000円以下」が一つの目安
この区分は、形式的な名目ではなく、その支出の実態に即して判断されます。
少しでも判断に迷う支出があった場合は、安易に自己判断せず、税務の専門家に一度ご相談ください。
貴社の事業内容や過去の事例を深く理解した上で、最適なアドバイスをさせていただきます。