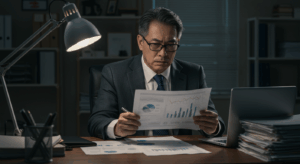「お金の仕入れ先」として銀行と付き合うための金融機関ポートフォリオ
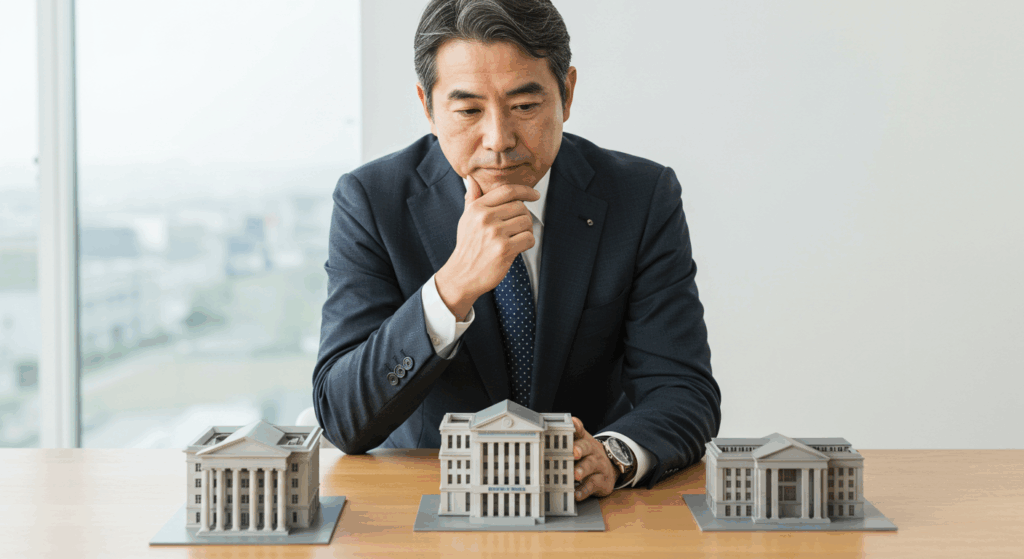
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週金曜日に、経営者なら知っておきたい「銀行融資」についての知識を解説しています。
「銀行の担当者が変わったら、急に融資に厳しくなった…」
「金利交渉をしたいが、うちが借りられるのはここだけだから、強く言えない…」
中小企業の経営者の皆様から、このようなお悩みを伺うことは少なくありません。
銀行との関係において、どこか「お願いする」という立場になってしまい、対等な交渉ができていないと感じている方は多いのではないでしょうか。
しかし、安定した経営基盤を築くためには、銀行との関係性を根本から見直す必要があります。
本記事では、銀行を単なる「お金を貸してくれる場所」ではなく、「お金という商品を仕入れる取引先」と捉え、対等なパートナーシップを築くための具体的な戦略について、詳しく解説します。
その鍵を握るのが、「金融機関ポートフォリオ」の構築です。
なぜ「取引銀行一行」では危険なのか?
多くの中小企業が、長年の付き合いがある一つの銀行に資金調達を依存しています。
一見、関係性が深く安心できるように思えますが、経営の観点から見るとこれは非常に危険な状態です。
具体的には、以下のようなリスクが常に付きまといます。
- 銀行側の都合による融資方針の転換
銀行も一企業です。
経営方針が変わり、特定の業種への融資を絞ったり、保証協会付き融資しか扱わなくなったりすることがあります。
そうなった場合、たとえ自社の業績が良くても、突然融資がストップする可能性があります。 - 担当者の交代による関係性のリセット
これまで親身に相談に乗ってくれていた担当者が異動になった途端、後任の担当者とは全く話が通じない、というケースは頻繁に起こります。
担当者個人の力量や考え方に依存した関係性は、非常に脆いのです。 - 交渉力の欠如
「この銀行からしか借りられない」という状況は、経営における最大の弱みの一つです。
金利や融資条件について交渉したくても、「他に行き場がない」と思われているため、銀行側の提示する条件を呑むしかなくなってしまいます。
これらのリスクは、どれも自社の努力だけではコントロールできません。
だからこそ、外部環境の変化に左右されない、安定した財務基撃を築くための仕組みが必要となるのです。
安定経営の礎!「金融機関ポートフォリオ」という考え方
そこで重要になるのが、「金融機関ポートフォリオ」という考え方です。
ポートフォリオとは、もともと金融商品の組み合わせを指す言葉ですが、これを銀行取引にも応用します。
つまり、特徴の異なる複数の金融機関とバランス良く取引関係を構築し、資金調達のリスクを分散させる戦略です。
複数の銀行と付き合うことで、
- リスク分散
一つの銀行の方針が変わっても、他の銀行から資金調達できる。 - 金利交渉力
他行の金利を引き合いに出すことで、有利な条件を引き出しやすくなる。 - 情報収集力
各銀行から様々な情報(経済動向、補助金、ビジネスマッチング等)を得られる。
といった大きなメリットが生まれます。
これはまさに、特定の仕入れ先に依存せず、複数の仕入れ先を確保しておくという、事業における基本的なリスク管理と同じ考え方です。
【企業規模別】最適な金融機関ポートフォリオの組み方
では、具体的にどのような金融機関を組み合わせれば良いのでしょうか。
ここでは、企業の成長ステージに応じたポートフォリオの目安をご紹介します。
もちろん、これはあくまで一般的なモデルであり、最終的には自社の事業内容や地域性に合わせて最適化していくことが重要です。
【年商5億円以下の企業様】
- 地方銀行:1行
- 信用金庫・信用組合:2行
- 日本政策金融公庫
このステージでは、地域に根ざし、小回りの利く信用金庫・信用組合との取引を手厚くすることがポイントです。
普段からこまめにコミュニケーションを取り、事業内容を深く理解してもらう関係性を築きましょう。
併せて、プロパー融資(信用保証協会の保証を付けない融資)にも対応できる地方銀行、そして創業者や中小企業の強い味方である日本政策金融公庫との取引も必須です。
【年商10億円以下の企業様】
- メガバンク:1行
- 地方銀行:1~2行
- 信用金庫・信用組合:1~2行
- 日本政策金融公庫
事業が拡大し、運転資金や設備投資の金額が大きくなってくるこの段階では、メガバンクとの取引を開始するタイミングです。
メガバンクは融資金額の規模や情報量が魅力ですが、審査のハードルは高い傾向にあります。
そのため、これまで築き上げてきた地方銀行や信用金庫との関係も維持し、バランスを取ることが重要です。
【年商10億円超の企業様】
- メガバンク:1~2行
- 地方銀行:2行
- 信用金庫・信用組合:1行
- 日本政策金融公庫
- (必要に応じて商工中金も検討)
年商が10億円を超えてくると、より多様な資金ニーズが生まれます。
海外展開やM&Aなどを視野に入れる場合は、メガバンクのノウハウが活きてきます。
また、複数の地方銀行と付き合うことで、より積極的なプロパー融資の提案を引き出すことも可能になります。
必要に応じて、中小企業専門の政府系金融機関である商工中金との取引も検討に入れると、さらに選択肢が広がります。
各金融機関の特徴を理解し、賢く付き合う
ポートフォリオを効果的に機能させるためには、それぞれの金融機関の特性を理解しておくことが不可欠です。
- メガバンク
全国展開しており、融資可能額が大きく、海外取引や高度な金融サービスに強みがあります。
一方で、審査はシステム化・画一化されている傾向があり、中小企業への対応は地方銀行や信用金庫に比べてドライな側面もあります。 - 地方銀行
地域経済の発展をミッションとしており、地元の有力企業とのネットワークが豊富です。
経営者の顔が見える関係を築きやすく、プロパー融資にも比較的積極的です。 - 信用金庫・信用組合
地域の中小企業や個人事業主を支える相互扶助の精神に基づいています。
Face to Faceの関係を重視し、決算書の数字だけでは測れない事業の将来性なども評価してくれる傾向があります。
融資の相談だけでなく、日頃から経営の相談ができる関係を築いておきたい相手です。 - 日本政策金融公庫
政府が100%出資する金融機関です。
民間金融機関の補完を役割とし、創業融資やソーシャルビジネス支援、災害時の融資など、政策に基づいた融資制度を多く扱っています。
民間の銀行とは審査の視点が異なるため、必ず取引しておくべき金融機関です。
これらの特徴を理解し、「この相談はこの銀行に」「この規模の融資はこちらに」といったように、目的に応じて相談先を使い分けることが、賢い銀行付き合いの第一歩です。
「競合」の存在が、あなたを対等な交渉のテーブルに着かせる
金融機関ポートフォリオを組むことの最大の効果、それは「競合」の存在を生み出すことにあります。
例えば、設備投資のためにA銀行に融資を相談した際、満足のいかない金利を提示されたとします。
もしA銀行としか取引がなければ、その条件を飲むか、計画を諦めるかの二択しかありません。
しかし、B銀行やC信用金庫とも取引があれば、「他行さんではもう少し良い条件を検討してくれています」と、客観的な事実を元に交渉することが可能になります。
銀行側も、優良な融資先を他行に取られたくはありませんから、真剣に条件の見直しを検討せざるを得なくなります。
これは、脅しや駆け引きではありません。複数の「お金の仕入れ先」の中から、最も良い条件を提示してくれる取引先を選ぶという、経営者として当然の経済合理的な判断です。
この「いつでも他を選べる」という状態を作ることこそが、銀行と対等なパートナーシップを築く上で最も重要なのです。
まとめ:戦略的な銀行取引で、変化に強い経営を
銀行との関係は、一度構築すると見直す機会が少ないかもしれません。しかし、資金繰りは会社経営の生命線です。
特定の銀行に依存した、受け身の資金調達から脱却し、自社が主導権を握るための「金融機関ポートフォリ」を、ぜひこの機会に検討してみてください。
ご紹介したポートフォリオはあくまで雛形です。どの金融機関と、どのようなバランスで付き合っていくべきか。その最適解は、一社一社の状況によって全く異なります。
自社にとって最適なポートフォリオを構築し、銀行との交渉を有利に進めたいとお考えの経営者様は、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。
貴社の未来を切り拓く、最適な財務戦略をご提案いたします。