銀行融資の「幹」とは?最初に知るべき銀行の仕組みと力関係
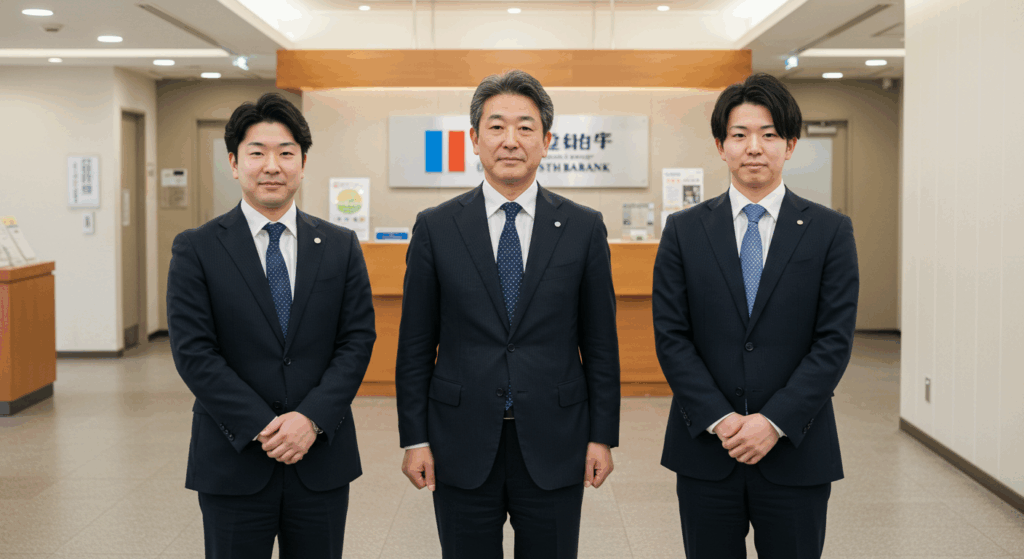
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週金曜日に、経営者なら知っておきたい「銀行融資」についての知識を解説しています。
「銀行融資を有利に進めたい…」
そう考える経営者の皆様にとって、元銀行員が執筆した対策本は心強い味方です。現場のリアルな声が反映されており、すぐに使えるテクニックも多いでしょう。
しかし、そこに書かれているテクニックを試しても、なぜか上手くいかない。担当者によって反応が全く違う…。そんな経験はないでしょうか。
それは、融資交渉の「枝葉」であるテクニックばかりに目が行き、その土台となる「幹」、つまり銀行という組織そのものへの理解が不足しているからかもしれません。
どんなに優れた交渉術も、相手を知らなければ効果は半減します。
銀行員はどのような組織構造の中で、誰の顔色を伺い、何を基準に物事を判断しているのか。
この「内部の力学」を理解することが、交渉を有利に進めるための最も確実な近道です。
この記事では、書籍だけではわからない融資の「幹」となる部分、交渉の前提となる「銀行の仕組みとリアルな力関係」について徹底的に解説します。
この知識は、あなたと銀行との関係を対等なものに変える、強力な武器になるはずです。
銀行は特殊な組織?まずは基本の仕組みを理解しよう
「銀行は特殊な業界だから…」と、どこか遠い存在に感じていませんか?
しかし、その本質は皆様が経営されている会社と同じです。利益を追求し、組織のルールに則って動いています。
まずは、その組織構造と力関係の基本を押さえることが、交渉を有利に進めるための第一歩です。
銀行の掟①:支店長の絶大な権力とその背景
一般の事業会社にも支店長はいますが、銀行の支店長はそれよりもはるかに強い権限を持っています。
銀行の支店を「一つの独立した会社」、支店長をその「社長」とイメージすると分かりやすいでしょう。
支店長が持つ主な権限は以下の2つです。
- 一定金額までの融資決済権限
- スタッフの人事権
特に大きいのが、部下の人事権を掌握している点です。
これにより、支店長は支店内で絶対的な力を持つことになります。
融資の可否や条件が、支店長の考え方一つで大きく変わることは日常茶飯事です。
支店の役職者の序列
ちなみに、一般的な銀行支店の役職者の序列は以下のようになっています。
融資の相談をする際、相手がどのポジションにいるのかを把握しておくと、話の進み方も変わってきます。
(金融機関によって呼称が異なる場合があります)
- 支店長
- 副支店長、次長(ナンバー2クラス)
- 支店長代理(融資課長など、課長クラス)
担当者レベルで話が止まってしまう場合は、その上司である支店長代理や次長に話を通すことで、局面を打開できるケースもあります。
銀行の掟②:出世するのは「運の良い人」?
では、その絶大な権力を持つ支店長には、どのような人がなるのでしょうか。
もちろん学歴や成績も加味されますが、多くの銀行員が口を揃えて言うのは「運の良い人」が出世する、という少し意外な事実です。
これは、銀行が基本的に「減点主義」の世界であることに起因します。大きな成功を収めることよりも、失敗をしないことが評価される文化なのです。
特に、責任あるポジションに就いた際に、担当する部下の不祥事(横領など)や多額の貸し倒れといった事故が起きない「運」が、昇進において重要な要素と見なされるという特殊な文化があります。
また、これは一般企業とも共通しますが、上司に可愛がられる、いわゆる「上司受けの良い人」が出世しやすい傾向も強いです。
ドラマ『半沢直樹』のように上司に真っ向から逆らうタイプは、残念ながら現実の組織では評価されにくいのが実情です。
銀行の掟③:担当者への「付け届け」は本当に効果があるのか?
「担当者さんへのお中元は必要ですか?」
「担当者から頼まれた貸金庫やクレジットカードの契約には応じるべきでしょうか?」
こうしたご相談をよく受けます。
結論を出すために重要なのは、融資判断において「誰の意見が、どれくらい強いのか」というパワーバランスを正確に理解することです。
融資判断における影響力の序列
影響力が強い順に並べると、以下のようになります。
- 本店の意向(圧倒的!ほぼこれで決まる)
- 支店長の度量(リスクを取るタイプか、安定志向か)
- 担当者の力量(影響力は限定的)
最も影響力が強いのは、言うまでもなく「本店の方針」です。
銀行全体が融資に積極的な局面(金融緩和期など)では融資は出やすく、逆に引き締めの方針(不景気など)の際には、支店長や担当者がどれだけ頑張っても融資のハードルは格段に上がります。
次に影響力があるのが、前述の「支店長の度量」です。
本店の方針という大きな流れの中で、個別の案件をどこまでリスクを取って承認するかは、支店長の性格や経験に大きく左右されます。
支店長が交代した途端、それまで否定的だった融資姿勢がガラッと前向きに変わる、といったことも珍しくありません。
担当者の力量が影響するのは、そのずっと後です。もちろん、優秀な担当者は稟議書を巧みに書き、上司を説得する力を持っています。
しかし、担当者個人への気遣い、例えばお中元や関連商品の契約が、融資を「有利にする」効果は限定的です。
むしろ、「この担当者は経験が浅くて話が進まない…」というように、マイナスに働く可能性をケアする方が重要かもしれません。
銀行が本当に頭が上がらない「最強の相手」とは?
では、銀行にとって最も弱い相手、絶対に逆らえない相手は誰でしょうか。それは「金融庁」です。
金融庁の課長が呼び出せば、銀行の頭取が応じると言われるほど、その力関係は絶対的なものです。
この事実を知っておくだけで、銀行との交渉における強力なカードを持つことになります。
もし銀行から理不尽な要求をされた際には、まず冷静にこう確認してみてください。
「そのお話は、あくまで『お願い』という認識でよろしいでしょうか。それとも、何か強制力のあるものなのでしょうか?」
お願いであれば、断る権利がこちらにはあります。それでも相手が強く迫ってくるようなことがあれば、次の一言が有効な場合があります。
「あまりに不合理なご提案が続くようでしたら、金融庁に相談することも検討いたします」
これはまさに「伝家の宝刀」であり、決して安易に口にすべき言葉ではありません。
しかし、自社の経営実態に見合わない不合理な金融商品(仕組みが複雑なスワップ商品など)を強引に勧められたり、その解約で揉めたりした場合の最後の切り札として、頭の片隅に置いておいてください。
この一言があるだけで、銀行側の対応が軟化する可能性があります。
まとめ:相手を知ることが交渉の第一歩
今回は、金融機関とのあらゆる交渉の前提となる「銀行の組織と力関係」について解説しました。
- 支店長は「会社の社長」に匹敵する強い権限を持つ
- 融資判断の力関係は「本店 > 支店長 >> 担当者」である
- 銀行が最も恐れるのは「金融庁」である
融資交渉というと、すぐに事業計画や資金繰り表の作り方といったテクニックに目が行きがちですが、まずは「相手を知る」ことが何よりも重要です。
彼らがどのような組織文化の中で、誰の意向を気にして仕事をしているのかを理解するだけで、今後の交渉が格段に進めやすくなります。
今回の内容を踏まえていただくと、次回以降のテーマがより深くご理解いただけるはずです。
次回は、より実践的な「融資の4つの基本形式」について詳しく解説します。どうぞお楽しみに。
銀行融資に関するご不明な点や、具体的なお悩み事がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

