あなたの銀行融資、最適ですか?会社の成長ステージで考える「銀行選び」の新基準
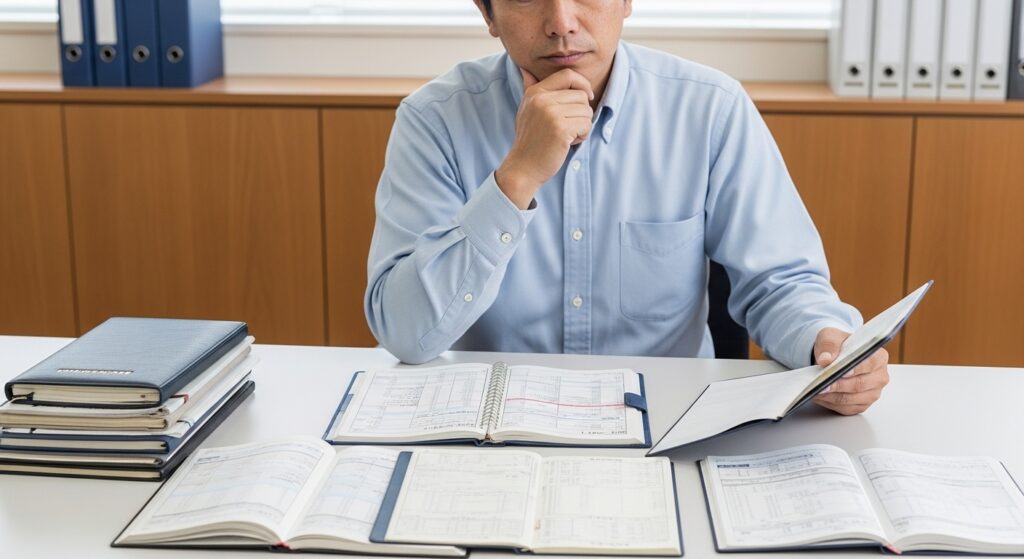
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週金曜日に、経営者なら知っておきたい「銀行融資」についての知識を解説しています。
「会社の運転資金、設備投資の資金をどう調達しようか…」
中小企業の経営者であれば、銀行融資は常に重要な経営課題の一つではないでしょうか。
そして、その成否を大きく左右するのが「どの銀行と取引するか」という選択です。
「メガバンクの方が安心?」「地元の信用金庫の方が親身になってくれる?」「そもそも、いくつの銀行と付き合えばいいのだろう?」
もし、あなたが何となく取引銀行を選んでいるとしたら、それは将来の成長機会を逃すだけでなく、いざという時のリスクを高めているかもしれません。
この記事では、会社の成長ステージに合わせた「取引銀行の選び方」と「戦略的な付き合い方」について、実践的なノウハウを余すところなくお伝えします。
この記事を読めば、自社に最適な金融機関を選び、安定した資金調達を実現するための具体的な道筋が見えるはずです。
なぜ「複数行との取引」が鉄則なのか?
まず、最も基本的かつ重要な原則からお伝えします。
それは、融資取引は必ず複数の銀行と行うべきだということです。
現在、取引銀行が一行だけという経営者の方は、すぐにでも取引銀行を増やすことを検討してください。
なぜなら、一行取引には大きなリスクが潜んでいるからです。
1.一行取引に潜む「断られたら終わり」のリスク
もし、その唯一の取引銀行に融資を断られてしまったらどうなるでしょうか。
他の金融機関に慌てて駆け込んでも、新規の取引では審査に時間がかかったり、条件が厳しくなったりする可能性があります。
最悪の場合、資金調達の道が完全に断たれ、会社の存続が危ぶまれる事態になりかねません。
複数の銀行と付き合っていれば、ある銀行に断られても、他の銀行に相談するという選択肢が生まれます。
これは、企業にとって極めて重要なリスクヘッジです。
2.銀行側にとっても「複数行取引」はメリットがある
意外に思われるかもしれませんが、実は銀行側も、取引先企業が他の銀行とも付き合うことを望んでいるケースが多いのです。
銀行には、それぞれの内部事情や融資方針があります。
例えば、「この業種への融資は今、積極的ではない」「融資残高がこの企業に集中しすぎている」といった理由で、融資をしたくてもできない場合があります。
そんな時、他行が融資に応じてくれれば、取引先企業は事業を継続できます。
これは、自行にとっても将来の取引機会を失わずに済むというリスクヘッジになるのです。
もちろん、著しく業績が悪化している場合は、すべての銀行から断られてしまうこともありますが、健全な経営をしていれば、複数行取引は双方にとってメリットのある関係なのです。
【企業ステージ別】取引すべき金融機関と理想の行数
では、具体的にどのような金融機関と、何行くらい付き合うのが適切なのでしょうか。
これは、会社の売上規模や今後の成長戦略によって異なります。
ここでは、3つのステージに分けて解説します。
ステージ1:創業期〜年商3億円まで
このステージの企業に最適なのは、以下の組み合わせです。
- 取引金融機関
地元の地方銀行、信用金庫 + 日本政策金融公庫(国民生活事業) - 理想の行数
合計2〜3行
創業したばかりの会社や、地域に根差して着実に事業を拡大している企業にとって、最も頼りになるパートナーは「地域金融機関」である地元の地銀や信金です。
時々、「どうせならメガバンクと取引したい」と考える経営者の方もいらっしゃいますが、正直なところ、この規模の企業にとってはあまりお勧めできません。
メガバンクの主要な取引先は日本を代表する大企業であり、中小企業とは事業規模も融資の目線も大きく異なります。
その点、地域金融機関は、地元の中小企業の成長を支援することを使命としています。親身に相談に乗ってくれ、長期的な視点で良好な関係を築きやすいでしょう。
これに加えて、政府系金融機関である日本政策金融公庫との取引は必須です。
特に「国民生活事業」は、創業期の企業や小規模事業者への融資に積極的であり、民間金融機関を補完する重要な役割を担っています。
ステージ2:年商3億円〜10億円
会社が成長し、年商が3億円を超えてくると、金融機関との付き合い方も次のステップに進める必要があります。
- 取引金融機関
地方銀行、信用金庫を中心とし、取引バランスを戦略的に構築 - 理想の行数
3〜4行
このステージで最も重要なのは、融資取引のバランスを考え、「メインバンク」を明確に定めることです。
なぜ今、メインバンクが重要なのか?
近年、「かつての日本特有のメインバンク制は薄れている」として、「メインバンクは不要だ」と主張する専門家もいます。
しかし、私は数々の事業再生支援の現場を見てきた経験から、この意見には賛同できません。
事業再生のような厳しい局面において、メインバンクが明確でない会社は、銀行団の対応が非常に困難になるケースが後を絶ちません。
どの銀行も「他行の出方を見てから…」と様子見に徹してしまい、支援の意思決定が遅々として進まないのです。
平時には問題がなくても、いざという時に自社の支援をリードしてくれる銀行の存在は、企業にとって最大のセーフティネットになります。
メインバンクを明確に定めておくことは、究極のリスクヘッジなのです。
メインバンクは地銀?信金?
では、どの金融機関をメインバンクにすべきか。これは、今後の成長目標によって判断が変わります。
- 年商5億円程度を当面の目標とする場合
信用金庫でも地方銀行でも大きな差はありません。 - 年商10億円以上を目指す場合
地方銀行をメインバンクに据えるべきです。
信用金庫は地域密着で小回りが利くという強みがありますが、融資の規模には限界があります。
年商が10億円規模に近づくと、必要となる資金額も大きくなり、信用金庫だけでは支えきれなくなる可能性があります。
将来の成長を見据えるなら、より大きな融資体力を持つ地方銀行をメインに育てていく戦略が不可欠です。
ステージ3:年商10億円超
年商が10億円を超えると、資金調達の規模も格段に大きくなります。
一段上のステージを見据えた金融機関との関係構築が必要です。
- 取引金融機関
第一地方銀行(メイン)、メガバンク、商工中金、日本政策金融公庫(中小企業事業) - 理想の行数
4行以上(取引の深さが重要)
この規模になると、1回あたりの融資申込額が平均月商の1〜1.5ヶ月分、つまり8,000万円〜1億2,000万円程度になることも珍しくありません。
ここで大きな壁となるのが、信用保証協会の保証枠です。原則として無担保での保証枠は8,000万円(一部別枠を除く)が上限です。
つまり、これ以上の資金調達には、不動産などの担保を提供するか、銀行から直接、信用力のみで借り入れる「プロパー融資」が必要不可欠になります。
プロパー融資を引き出すための布石
年商10億円を超えるステージまでに、いかにして銀行から無担保のプロパー融資を十分に受けられる状態を作っておくか。これが経営者の腕の見せ所です。
そのためには、融資体力のある第一地方銀行との関係をさらに深化させることが大前提となります。
それに加えて、大企業や中堅企業との取引に強いメガバンクや、政府と民間の共同出資による金融機関である商工中金、そして日本政策金融公庫の中でも中堅企業を対象とする「中小企業事業」との付き合いを始めることも極めて有効な戦略となります。
これらの金融機関は、プロパー融資の実績も豊富であり、企業の成長を力強く後押ししてくれる存在になり得ます。
「借りやすさ」や「金利」だけで銀行を選んではいけない
最後に、銀行選びで多くの経営者が陥りがちな罠についてお話しします。
それは、「どの銀行が一番借りやすいか」「どこが一番金利が低いか」という短期的な視点だけで判断してしまうことです。
もちろん、それらも重要な要素ではあります。しかし、銀行の融資スタンスというものは、常に変動します。
- 銀行自身の業績や方針によって、融資に積極的な時期と消極的な時期がある
- 同じ銀行でも、支店長の方針や担当者の力量によって対応が全く違う
「あの銀行は今、融資に積極的らしい」という情報に飛びついても、その状況が永遠に続く保証はどこにもありません。
より長期的な視点で見るべきなのは、取引する金融機関そのものの「健全性」です。
万が一、取引銀行が経営破綻したり、他の銀行に吸収合併されたりした場合、あなたの会社が受ける影響は計り知れません。
融資方針が急に変わり、資金繰りに窮することもあり得ます。
目先の借りやすさや金利の低さだけに囚われず、財務内容が良好で、安定した経営を続けている金融機関をパートナーとして選ぶ。
この視点が、10年後、20年後の会社の安定を支える礎となるのです。
まとめ:銀行選びは、会社の未来を左右する経営戦略
今回は、中小企業経営者のための取引銀行の選び方について解説しました。
最後に、本日の重要なポイントを振り返ります。
- 原則は「複数行取引」
1行取引のリスクを避け、選択肢を確保する。 - 会社の成長ステージで選ぶ
- 〜年商3億円
地元の地銀・信金+日本政策金融公庫(2〜3行) - 〜年商10億円
メインバンクを明確にし、地銀・信金とバランスよく付き合う(3〜4行) - 年商10億円超
プロパー融資を視野に、地銀に加えメガバンクや商工中金とも関係を構築
- 〜年商3億円
- メインバンクの重要性を再認識する
いざという時のリスクヘッジになる。 - 長期的な視点を持つ
「借りやすさ」だけでなく、金融機関の「健全性」を重視する。
銀行との付き合いは、一朝一夕で築けるものではありません。
日頃からコミュニケーションを取り、自社の経営状況を誠実に伝え、信頼関係を育んでいくことが何よりも大切です。
ぜひ、この機会に自社の取引銀行のラインナップを見直し、未来の成長に向けた最適なパートナーシップを構築するための一歩を踏み出してください。

