税務調査の連絡後でも間に合う?加算税を回避する修正申告の分岐点
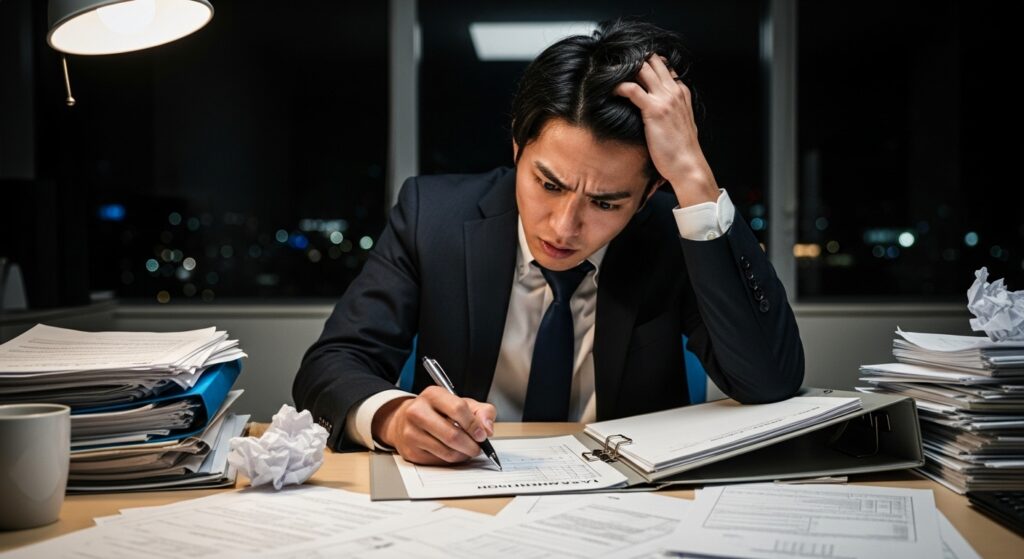
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週月曜日に、経営者なら知っておきたい「税務調査」についての知識を解説しています。
「税務署から調査の連絡が来た。まずい、申告漏れがある…。今すぐ修正申告すれば、ペナルティ(加算税)は軽くなるはずだ!」
中小企業の経営者であれば、このように考えた経験が一度はあるかもしれません。
確かに、自主的な修正申告はペナルティを回避または軽減するための有効な手段です。
しかし、その「自主的」が認められるかどうかには、専門的な境界線が存在します。それが、「更正の予知」です。
この「更正の予知」があったかなかったかで、過少申告加算税が課されるかどうかが決まります。
そして、この判断は、経営者が考えているよりもずっと広い範囲の「調査」が影響してくるのです。
本記事では、数々の税務調査に立ち会ってきた税理士の視点から、加算税の分かれ目となる「更正の予知」について、裁判例を交えながら具体的に解説します。
特に、「法人税の調査だと思っていたら、他の税金にまで影響が…」という、経営者が陥りがちな落とし穴に焦点を当てていきます。
そもそも「更正の予知」とは?加算税減免の分かれ目
税務調査が始まる前に、自社の申告に誤りを見つけて自主的に修正申告した場合、本来課されるべき「過少申告加算税」が免除されます。
しかし、税務署から調査の連絡があった後に修正申告をすると、「調査により更正があるべきことを予知してされたもの」と判断され、原則として加算税が課されてしまいます。
では、どのタイミングから「予知していた」と判断されるのでしょうか。
単に「税務調査に伺います」という一本の電話があっただけでは、通常「予知」にはあたりません。
裁判例では、以下のように示されています。
東京地裁平成7年3月28日判決
国税通則法65条5項にいう「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」とは、税務署員が申告に係る国税についての調査に着手し、その申告が不適正であることを発見するに足りるか又はその端緒となる資料を発見し、 これによりその後調査が進行して先の申告が不適正で申告漏れの存することが発覚し更正に至るであろうことが客観的に相当程度の確実性をもつて認められる段階に達した後に、納税者がやがて更正に至るべきことを認識した上で修正申告を決意して修正申告書を提出したものでないことをいうものと解すべきである。
少し難しい表現ですが、ポイントは以下の通りです。
- 税務職員が調査に着手している
- 申告が不適切であることの端緒(きっかけ)となる資料を発見している
- このまま調査が進めば、高い確率で申告漏れが発覚し、更正処分に至ると客観的に認められる段階にある
つまり、調査官が具体的な問題点を把握した段階で「予知」があったと判断されるのが原則です。
単なる調査通知の段階では、まだセーフの可能性があるわけです。
「調査」の範囲はどこまで?法人税調査だけではない落とし穴
経営者の多くは「税務調査」と聞くと、自社の法人税や消費税に関する調査をイメージするでしょう。
しかし、「更正の予知」の判断基準となる「国税についての調査」は、それだけにとどまりません。
例えば、脱税などの不正行為を調査する「犯則調査(マルサ)」も、この「調査」に含まれます。
そして重要なのは、その調査対象が自社でなかったとしても、影響が及ぶケースがあるということです。
【事例解説①】関連会社への調査が自社に及ぼす影響
「調査対象はうちの関連会社だから、自社には関係ない」とは言えません。
以下の裁判例を見てみましょう。
東京地裁 「更正の予知」該当性を巡る事件で国勝訴(税務通信3662)
事案の概要:
関連会社(S社)に対して犯則調査が行われ、その過程で納税者(自社)の売上除外(着服金)が発覚した。その後、納税者は修正申告を提出した。裁判所の判断:
犯則調査の嫌疑者がS社であったとしても、その結果として納税者の申告漏れが税務当局に明らかになった以上、その後の修正申告は「更正の予知」によるものと判断。納税者の修正申告は自発的とは言えず、加算税は免除されない。
この事例のポイントは、調査の名目が何であれ、誰に対する調査であれ、その過程で自社の申告漏れの事実が具体的に把握されたかどうかです。
国税局の職員が、関連会社の調査で自社の売上除外を示す証拠(虚偽契約書の写しなど)を入手した時点で、「客観的に相当程度の確実性」が認められる段階に達したと判断されました。
【経営者への教訓】
グループ会社や主要な取引先が税務調査(特に犯則調査)を受けたという情報を得た場合、それは決して他人事ではありません。
自社との取引の中に問題がないか、速やかに確認し、必要であれば専門家と対応を協議する必要があります。
【事例解説②】電話や書面での指摘も「調査」に含まれる
実地調査だけでなく、税務署内で行われる「机上調査」も、もちろん「調査」に該当します。
税務署からの電話一本で、状況が大きく変わることもあります。
令和3年6月25日裁決
事案の概要:
納税者は所得税の申告をしていなかった。調査担当職員が証券会社の法定調書から株式の譲渡所得があることを把握し、納税者に電話で連絡。その後、申告を勧奨し、納税者は期限後申告書を提出した。審判所の判断:
調査職員は電話や面接を通じて、納税者の申告漏れを具体的に把握していた。これは課税額を認定する一連の判断過程であり、「調査」に該当する。納税者も調査内容や進捗状況を認識した上で申告書を提出しているため、この申告は「決定があるべきことを予知してされたもの」と判断され、無申告加算税の減免は適用されない。
この事例では、調査官が「株式等の譲渡所得に係る申告漏れがある」と具体的に把握し、納税者に伝えたことが決定打となりました。
税務署からの電話で問題点を指摘された後に提出した申告は、もはや自主的とは認められないのです。
【経営者への教訓】
税務署からの問い合わせの電話には、誠実に対応しつつも、安易な回答は禁物です。
どのような内容で、どの程度具体的に指摘されているのかを正確に把握することが重要です。
少しでも不安があれば、その場で即答せず、「税理士に確認して折り返します」と伝えるのが賢明です。
【事例解説③】相続税調査が所得税に波及するケース
さらに複雑なケースとして、ある税目の調査が、全く別の税目の「更正の予知」につながる場合があります。
次の事例は、相続税の調査が所得税の修正申告に影響したケースです。
東京地裁令和3年5月27日判決
事案の概要:
被相続人の相続税調査の過程で、相続人名義の海外財産が発見された。この財産が「本当に相続人のものか、それとも被相続人のもの(相続財産)か」が調査の焦点となった。調査の過程で、相続人らは海外財産から生じる所得について、所得税の修正申告を行った。裁判所の判断:
相続税調査は、海外財産の真の所有者を明らかにすることを目的としていた。もし財産が相続人のものであれば、そこから生じる所得の申告漏れが明らかになる関係にあったため、この相続税調査は「実質的に所得税の調査を含むものであった」と認定。
税務当局が、相続人から提出された回答書によって海外財産の具体的な内容を把握した時点で、所得税の申告漏れが発覚する「客観的確実時期」に至ったと判断。その後の修正申告は「更正の予知」によるものであり、加算税は免除されない。
この事例は、税務調査の視野の広さを示唆しています。
調査官は、調査対象となっている税目だけでなく、関連するあらゆる税金の問題点にアンテナを張っています。
【経営者への教訓】
相続税調査や贈与税調査など、一見すると会社の法人税とは関係ないように思える調査でも、役員個人のお金の動きから、会社との不透明な取引が疑われることがあります。
税務調査は常に多角的な視点で行われていることを忘れてはいけません。
要注意!調査官の「加算税は課さない」は信じてはいけない
最後に、経営者が特に注意すべき点をお伝えします。
それは、調査官の口頭での発言を鵜呑みにしてはいけないということです。
上記で解説した相続税調査の事例では、実は調査官が「所得税の修正申告については加算税を課さない」といった趣旨の発言をしていたようです。
納税者はこの言葉を信じて修正申告をしたにもかかわらず、結果的に加算税が課されてしまいました。
裁判所は、この調査官の発言が「公的見解」に当たらないとは言えないとしつつも、納税者を救済しませんでした。
東京地裁令和3年5月27日判決(同判決より)
仮に本件発言がなく、原告ら及び亡母が修正申告書等を提出した事実がなかったとしても、韓国財産から生じた所得について所得税の申告を怠っていたことに変わるところはないのであるから、本件各賦課決定処分は、原告らの本件発言に対する信頼等に関わりなく、当然に課せられるべきものであったといわざるを得ない。
要するに、「調査官の発言がなくても、申告漏れの事実があった以上、加算税が課されるのは当然」ということです。
これを「信義則の原則」の否定と呼びますが、税務の世界では、よほどのことがない限り、税務署側の言動を理由に納税者が救済されることはありません。
【経営者への教訓】
調査官とのやり取りで、自社に有利な発言があったとしても、それを安易に信じ込んではいけません。
重要な確認事項は、必ず文書で取り交わすか、税務調査に精通した税理士などの専門家を介して確認することが、自社を守るための鉄則です。
まとめ:調査の連絡が来たら、まず専門家にご相談を
ここまで見てきたように、「更正の予知」の判断は非常に専門的かつ実務的です。
- 「調査」は法人税だけでなく、あらゆる国税調査が対象となる。
- 関連会社や取引先への調査が自社に波及することもある。
- 電話での指摘でも「予知」と判断される可能性がある。
- 調査官の口頭での約束は、基本的に保証されない。
税務署から調査の連絡を受けた段階で、経営者の方が自己判断で「今なら間に合う」と修正申告をしてしまうのは、非常に危険です。
その申告が、かえって「予知」があったことを認める結果になりかねません。
もし税務調査の連絡が来たら、まずは深呼吸をして、慌てて行動する前に、税務調査の経験が豊富な専門家にご相談ください。
現状を正確に分析し、加算税のリスクを最小限に抑えるための最善の策を共に考えることが、会社を不要なダメージから守る最良の道です。

