「役員借入金」を賢く精算して相続税の節税対策をする方法2選
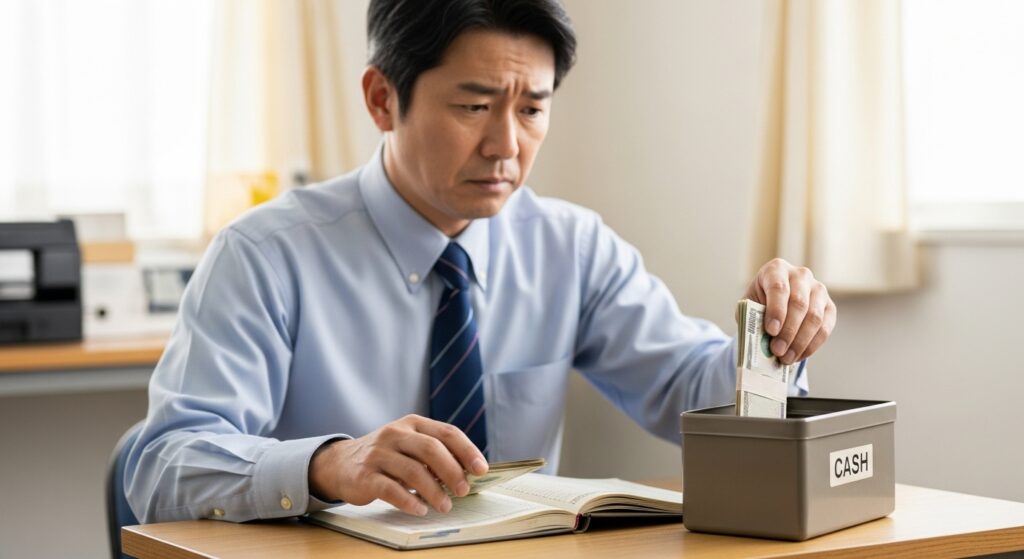
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週水曜日に、経営者なら知っておきたい「節税対策」についての知識を解説しています。
会社の資金繰りが厳しくなった時、「とりあえず個人の資産から会社に補填しよう」あるいは「一時的に自分の役員報酬の支払いを止めよう」と考えたことはありませんか?
多くの中小企業経営者にとって、ご自身の会社は一心同体であり、個人のお金と法人のお金を「右手から左手へ」移すような感覚で扱ってしまうのは、ある意味で自然なことかもしれません。
しかし、その手軽さが、将来的に大きなリスクを生む火種になることをご存知でしょうか。
経理上、これらの行為によって生じるのが「役員借入金」です。これは、法人が経営者からお金を借りている状態を示す勘定科目です。
この役員借入金を安易に考え、貸借対照表(B/S)に残したまま放置してしまうと、「銀行からの評価低下」そして「予期せぬ多額の相続税」という、二つの深刻な問題を引き起こす可能性があるのです。
私自身、多くの中小企業様とお付き合いする中で、この役員借入金が原因で手遅れとも言える状況に陥ってしまったケースを数多く見てきました。
この記事では、なぜ役員借入金を放置してはいけないのか、その具体的なデメリットと、いざという時に慌てないための賢い精算方法について、実務的な視点から徹底解説します。
放置は危険!役員借入金がもたらす2つの大きなデメリット
「会社に貸しているだけなのだから、問題ないだろう」
そう思われるかもしれませんが、税務署や金融機関はそう見てはくれません。
帳簿に「役員借入金」が残り続けることのデメリットは、主に以下の2つです。
デメリット1:金融機関からの評価(与信)が著しく下がる
会社が融資を受けようとする際、金融機関は必ず決算書をチェックします。
その貸借対照表に多額の「役員借入金」が計上されていると、金融機関からの評価は確実に下がります。
理由は主に2つあります。
- ① 事業目的以外の資金流出を懸念される金融機関から見れば、「この会社に融資をしても、その資金が事業投資ではなく社長個人への返済に充てられてしまうのではないか」という疑念が生じます。融資はあくまで事業を成長させるための資金であり、経営者個人への返済が目的と見なされれば、審査は格段に厳しくなります。
- ② 会社の資金繰りを不安視される「経営者個人のお金を投入しなければ事業が回らない会社」というレッテルを貼られてしまいます。これは、会社の収益力が低く、自己資金で事業を継続できない状態であると判断されることに他なりません。結果として、与信枠は低く抑えられ、いざという時に必要な融資が受けられないという事態に陥りかねません。
デメリット2:経営者の死亡時に「相続税爆弾」となる
金融機関からの評価低下も深刻ですが、それ以上に経営者とそのご家族にとって致命的となりうるのが、相続税の問題です。
経営者が会社に貸し付けている「役員借入金」は、法的に見れば経営者個人の「貸付金債権」という資産になります。
そして、経営者にもしものことがあった場合、この貸付金債権はそのまま相続財産として扱われ、相続税の課税対象となるのです。
にわかには信じられないかもしれませんが、これは中小企業で実際に起こりがちな、非常に恐ろしいケースです。
具体的な例を見てみましょう。
【事例】
- 過去の業績不振時に、経営者が個人資産から1億円を会社に投入し、そのまま「役員借入金」として残っていた。
- 経営者個人の資産(預貯金など)は1,000万円だった。
- この状態で、経営者が突然亡くなってしまった。
この場合、相続税の対象となる財産額は、個人の預貯金1,000万円と、会社への貸付金1億円を合計した1億1,000万円となります。
仮に、このケースでの相続税額が2,000万円だったとしましょう。遺族が相続した個人の金融資産は1,000万円しかありません。
つまり、相続税を支払うことすらできないという、絶望的な状況に陥ってしまうのです。
もちろん、理屈の上では、会社が遺族に対して1億円を返済すれば、そのお金で相続税を支払うことができます。
しかし、そもそも経営者が1億円もの私財を投じなければならなかった会社に、それだけの返済能力(キャッシュ)があるでしょうか。
ほとんどのケースで答えは「ノー」です。
結果として、ご家族は納税資金を捻出するために自宅を売却したり、生命保険を切り崩したりといった事態に追い込まれかねません。
事前にこの1億円の役員借入金を整理しておきさえすれば、支払う必要のなかった、まさに「ムダな相続税」と言えるでしょう。
なぜ役員借入金は放置されがちなのか?
これほど大きなリスクがあるにもかかわらず、なぜ役員借入金は放置されてしまうのでしょうか。
それは冒頭でも触れた通り、経営者にとって「個人と法人は一心同体」という感覚が強いからです。
日々の経営に追われる中で、帳簿上の数字を整理することまで手が回らない。
あるいは「いつでも返してもらえる(はずだ)」という思い込みから、問題を先送りにしてしまうケースが後を絶ちません。
しかし、相続はいつ発生するか誰にも予測できません。
問題が顕在化してからでは、打てる手が限られてしまうのです。
役員借入金を解消する原則的な方法とは?
では、この役員借入金はどのように解消すればよいのでしょうか。
最も正攻法で、建前とも言える方法は「会社から経営者へ実際に返済する」ことです。
具体的には、経営者の役員報酬を一時的に減額し、その分だけ会社に生まれたキャッシュフローの余剰分を、借入金の返済に充てていくというものです。
例えば、月額100万円の役員報酬を30万円に減額したとします。
社会保険料の会社負担分なども考慮すると、会社には毎月80万円程度の余剰資金が生まれます。
この80万円をコツコツと返済に回していく、というイメージです。
しかし、この方法には大きな欠点があります。
借入金の額が数千万円、数億円と多額になっている場合、完済までに途方もない時間がかかってしまいます。
その間、経営者にもしものことがあれば、前述の相続税リスクは残り続けたままになってしまうのです。
役員借入金を一気に解消する具体策2選
そこで、より現実的かつスピーディーに役員借入金を解消するための、実務でよく使われる2つの方法をご紹介します。
ただし、どちらの方法も税務上の専門的な判断が必須となるため、実行する際は必ず顧問税理士に相談してください。
方法1:債務免除|繰越欠損金があるなら有効な手段
一つ目は、経営者が会社に対して「債権放棄(債務免除)」を行う方法です。
これは、経営者が「会社に貸しているお金は、もう返してもらわなくて結構です」と法的に意思表示をすることです。
これにより、帳簿上の役員借入金はゼロになります。ただし、この方法には一つだけ重大な注意点があります。
それは、会社側に「受贈益」という利益が発生し、法人税が課税される可能性があることです。
会社からすれば、例えば1億円の返済義務がなくなるわけですから、税務上は1億円の利益(債務免除益)が生まれたと見なされるのです。
では、どのような場合にこの方法は有効なのでしょうか。それは、会社に「繰越欠損金」がある場合です。
繰越欠損金とは、簡単に言えば「過去の事業年度に出した赤字の繰り越し分」のことです。税法上、この欠損金は将来発生した利益と相殺することができます。
例えば、会社に7,000万円の繰越欠損金があれば、7,000万円分の債務免除を行っても、利益と欠損金が相殺されて課税所得はゼロとなり、法人税は発生しません。
繰越欠損金の範囲内で行う債務免除は、役員借入金を精算する上で非常に有効な手段となり得ます。
方法2:DES(デット・エクイティ・スワップ)|借金を資本に変える
もう一つの強力な方法が「DES(デット・エクイティ・スワップ)」です。
これは、Debt(負債)とEquity(資本)をSwap(交換する)という名の通り、役員借入金(負債)を、会社の資本金に振り替える手続きのことです。
経営者側からすると、会社にお金を「貸している」状態から、その貸付金が「自社株(資本)」に変わる、ということになります。
DESを実行すると、以下のような大きなメリットがあります。
- ① 役員借入金が一気にゼロになる相続税のリスクとなる貸付金債権がなくなり、将来の憂いを断ち切ることができます。
- ② 財務体質が劇的に改善される貸借対照表上で負債が減り、自己資本が増強されます。これにより、自己資本比率などの経営指標が大きく改善し、金融機関からの評価(与信)が向上するという、非常に大きな副次的効果も期待できます。
ただし、このDESという手法は、一見シンプルに見えて、実行する際の株式の時価評価など、専門的な論点が多く存在します。
場合によっては思わぬ課税リスクが生じることもあるため、こちらも非常に複雑な判断が求められます。
(※DESの課税リスクについては非常に専門的かつ複雑なため、詳しくはお問い合わせください)
まとめ:役員借入金は「いつか」ではなく「今」対処すべき経営課題
今回は、多くの中小企業が抱えがちな「役員借入金」のリスクと、その具体的な解消方法について解説しました。
- 役員借入金を放置すると、「金融機関からの信用低下」と「高額な相続税」のリスクがある。
- 解消するには、繰越欠損金を利用した「債務免除」や、財務体質も改善できる「DES」が有効。
- ただし、どちらの方法も専門的な税務判断が不可欠。自己判断は絶対に避けるべき。
経営者個人の資産を会社につぎ込むのは、会社を愛するがゆえの行為だと思います。
しかし、その善意が、将来的に会社やご家族の首を絞める結果になっては元も子もありません。
役員借入金は、いわば静かに進行する時限爆弾のようなものです。
もし御社の貸借対照表に役員借入金が計上されているのであれば、決して問題を先送りにせず、すぐに顧問税理士などの専門家にご相談ください。
早期に対策を講じることが、会社とあなたの大切なご家族を守るための最善の一手となります。

