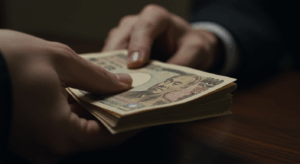銀行融資の否決理由No.1?審査を突破する「資金使途」の伝え方
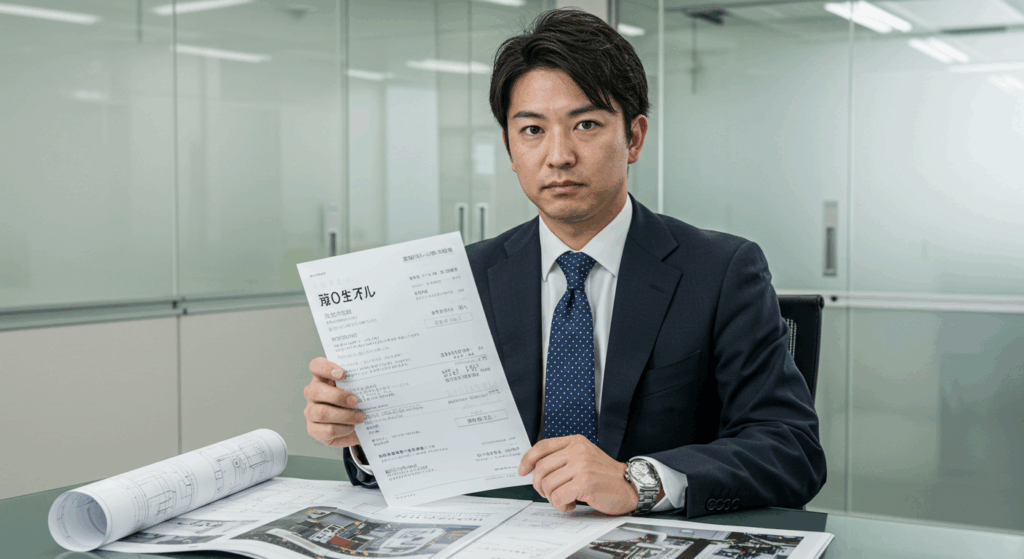
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週金曜日に、経営者なら知っておきたい「銀行融資」についての知識を解説しています。
企業の成長戦略において、銀行融資は事業を加速させるための重要な選択肢です。
しかし、いざ申し込んでみたものの、「資金使途が曖昧だ」という思わぬ理由で、残念ながら融資を断られてしまった…というご相談を、私は数多く受けてきました。
実は、融資審査において、金融機関が最初に、そして最も重視するのが、この「資金使途(=借りたお金の使い道)」なのです。
そこで今回は、これまで数多くの融資支援に携わってきた専門家の視点から、融資審査の最初の関門である「資金使途」に焦点を当てます。
「なぜそれほど重要なのか?」という根本的な理由から、「審査担当者を納得させる具体的な伝え方」まで、すぐに実践できるノウハウを分かりやすく解説してまいります。
なぜ銀行は「資金使途」をこれほど重視するのか?
なぜ金融機関は、企業の事業内容や財務状況と同じくらい、あるいはそれ以上に「資金使途」を厳しくチェックするのでしょうか。
これは、お金を貸す側の立場になってみれば、至極当然のことと言えます。
金融機関の使命は、貸したお金を利息とともにきちんと返済してもらうことです。
そのためには、「今回の融資が企業の成長に繋がり、将来の返済原資を生み出すかどうか」を正確に見極める必要があります。
もし、資金使途が曖昧だったり、事業計画に具体性がなかったりすると、審査担当者は次のように考えます。
- 「この融資で利益が生まれるイメージが湧かないな…(=返済の見通しが立たない)」
- 「行き当たりばったりの経営なのではないか…(=事業の計画性・継続性に疑問がある)」
特に注意が必要なのが、「他の金融機関からの借入金の返済に充てたい」といった申し込みです。
これは事業成長のための前向きな投資とは見なされず、「自転車操業に陥っているのではないか」という最も強い警戒感を与えてしまいます。
融資審査とは、単なるお金の貸し借りではなく、「事業の未来への投資」です。
その投資の妥当性を証明する最初のステップが、明確な資金使途を示すことなのです。
こんな説明はNG!「資金使途が不明確」と判断される典型ケース
では、具体的にどのような説明が「資金使途が不明確」と判断されてしまうのでしょうか。
現場でよく見られるNGケースを4つご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
ケース1:「とりあえず手元資金に余裕を持たせたい」
新型コロナウイルスの影響もあり、漠然とした不安から「何かあったときのために」「手元資金を厚くしておきたい」という理由だけで申し込むケースです。
お気持ちはよく分かりますが、具体的な目的がない資金調達は、金融機関からすると「貸したお金が何に使われるか管理できない」と判断され、審査を通過することは極めて困難です。
ケース2:設備投資と運転資金の区分が曖昧
例えば、「新しい機械の購入費用と、当面の仕入れ資金を合わせて1,000万円お願いします」といった、複数の目的が混在した申請です。
この場合、「機械の代金はいくらで、仕入れ資金はいくら必要なのか」が明確に区分されていません。
それぞれの資金の必要性や、金額の根拠が見えず、計画性の欠如を指摘されてしまいます。
ケース3:金額の根拠が全く示されていない
「Webサイトリニューアルと広告宣伝費として300万円が必要です」と口頭で伝えても、審査担当者は納得しません。
「なぜ300万円なのですか?」という問いに、論理的に答えられなければなりません。
この問いに答えるためには、「どの制作会社に依頼し、どの媒体に、いつ、どのような広告を出し、それによってどれくらいの売上増加が見込めるのか」といった具体的な計画と、それを裏付ける見積書などの客観的な資料が不可欠です。
ケース4:過去に受けた融資の成果説明がない
以前にも「運転資金」などの名目で融資を受けているにもかかわらず、その融資によってどのような成果が出たのか、あるいは課題がどう改善されたのかについて一切説明がない場合も、金融機関は追加融資に慎重になります。
「前回お貸しした資金は、本当に有効活用されたのだろうか?」という当然の疑問を抱かせてしまい、信頼関係を損なう原因にもなります。
審査担当者を納得させる!資金使途の伝え方3つのポイント
それでは、どうすれば資金使途を明確に伝え、金融機関からの信頼を勝ち取ることができるのでしょうか。
数多くの案件を成功に導いてきた経験から、特に重要だと断言できる3つのポイントをご紹介します。
ポイント1:客観的な根拠資料で「なぜ必要か」を証明する
まず最も基本的なことですが、「なぜその金額が必要なのか」を客観的に証明する資料を必ず用意しましょう。
熱意ある口頭での説明も大切ですが、それ以上に「事実」を示す書類が物を言います。
- 設備投資の場合
- 購入する設備の見積書
- 設備の性能がわかるカタログ
- リースや購入に関する契約書 など
- 運転資金の場合
- 過去の実績と今後の予測をまとめた資金繰り表
- 売上の見込みを示す受注契約書や発注書
- 仕入れ増加の根拠となる発注書 など
こうした裏付け資料を提出することで、申請金額の妥当性が格段に高まり、「堅実な経営計画に基づいた申請である」という評価に繋がります。
ポイント2:具体的な数値で「投資対効果」を示す
借りたお金を使って、会社の業績や利益がどのように向上するのか。
この「投資対効果」を、具体的なストーリーと数値で説明することが極めて重要です。
抽象的な表現は避け、誰が聞いても納得できるロジックを組み立てましょう。
(悪い例)
「新しい機械を導入して、生産性を上げたいです」
(良い例)
「この新設備(見積額500万円)を導入することで、製造工程が10%短縮され、残業代などの人件費が月々20万円削減できます。その結果、製品1個あたりの利益が50円向上し、年間で240万円の利益増が見込めます。3年以内には投資回収できる計算です」
このように、支出(融資)が将来の利益(返済原資)にどう結びつくのかを明確に伝えることで、金融機関は「この会社に融資する価値がある」と判断しやすくなります。
ポイント3:「スケジュールと過去の実績」で信頼度を高める
融資実行後の具体的なアクションプランを示すことも、信頼度を高める上で有効です。
「融資実行後、〇月〇日に設備を発注し、△月△日に稼働開始予定です。効果が出始めるのは□月頃からで、売上への貢献と返済開始のタイミングも問題ありません」
といったように、資金の具体的なスケジュールを示すことで、計画の実現性が増します。
さらに、過去に融資を受けた実績がある場合は、その成果をアピールする絶好の機会です。
「前回の運転資金の融資のおかげで、〇〇という大きな案件を受注でき、売上が前年比で15%増加しました」といったように、過去の実績と効果を補足説明することで、あなたの会社の経営の堅実性を証明でき、金融機関との良好な関係をさらに深めることができます。
これらの内容は、口頭で伝えるだけでなく、「事業計画書」として体系的にまとめて提出するのが最も効果的です。
もし否決されても大丈夫!再申請で逆転を狙う方法
万が一、資金使途の説明不足が原因で融資が否決されてしまったとしても、決して諦める必要はありません。
計画をしっかりと練り直し、提出資料を補強すれば、再申請で融資を獲得することは十分に可能です。
まずは、正直に金融機関の担当者に否決の理由を確認し、どこが不足していたのかを正確に把握しましょう。
その上で、指摘された点を改善した事業計画書や、追加の見積書などを準備します。
このとき、私たちのような融資支援に詳しい専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。
専門家の客観的な視点が加わることで、金融機関がどの点を評価するのか、どのような資料や伝え方が審査担当者の心に響くのかといった、内部の人間だけでは気づきにくいポイントを押さえた、精度の高い申請書類を作成することができます。
一般的に、再申請は状況や資料が整った段階で、1〜3か月程度の間隔を空けて行うのが良いとされています。
専門家と二人三脚で戦略的に準備を進め、次こそは満額回答を引き出しましょう。
まとめ
最後に、今回の内容を3つのポイントにまとめました。
- 融資審査では、「何に、なぜ、いくら必要なのか」という資金使途の明確さが最も重要視される。
- 申請の際は、見積書などの客観的な根拠資料に加え、その投資が将来の利益にどう繋がるかを具体的な数値で示すことが不可欠。
- 一度否決されても、理由を分析し、専門家と連携して事業計画を練り直せば、再申請での融資獲得は十分に可能である。
銀行融資は、事業を大きく飛躍させるための重要なエンジンです。
しかし、そのエンジンを動かすためには、しっかりとした「設計図」、すなわち明確な資金使途と事業計画が欠かせません。
ご自身のケースでどう説明すれば良いか分からない、事業計画書の作り方に不安があるなど、ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。