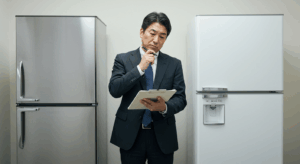銀行融資の審査を劇的にスムーズにする「三種の神器」とは?
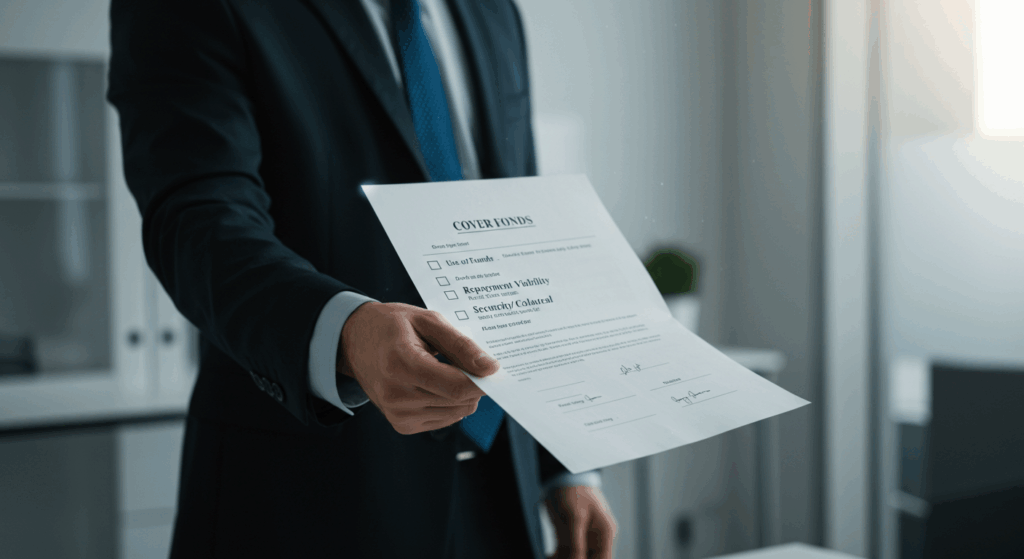
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週金曜日に、経営者なら知っておきたい「銀行融資」についての知識を解説しています。
「銀行に融資を申し込んだけれど、審査に時間がかかっている…」
「担当者から何度も追加資料を求められて、本業に集中できない…」
中小企業の経営者の皆様にとって、資金調達は事業を成長させるための生命線です。
しかし、銀行融資のプロセスが不透明で、どうすればスムーズに進むのか悩まれている方も多いのではないでしょうか。
実は、銀行が融資審査で本当に知りたいポイントは、驚くほどシンプルです。
銀行側の視点を理解し、彼らが求める情報を先回りして提供することで、審査のスピードと結果は劇的に変わります。
本記事では、融資審査をスムーズに進めるための「三種の神器」と、銀行との信頼関係を築くための具体的なアクションについて、詳しく解説していきます。
銀行が本当に知りたいのは、たった3つのこと
なぜ、あなたの会社の融資審査は時間がかかるのでしょうか。
それは、銀行が判断を下すために必要な情報が不足しているか、情報が整理されておらず担当者が理解するのに時間を要しているからです。
銀行が融資審査において、企業の事業内容や将来性を多角的に分析するのは事実です。
しかし、その評価の根幹にあるのは、突き詰めると以下の3つの問いに対する答えに他なりません。
- 資金使途:『何に』お金を使うのか?
- 返済可能性:『どうやって』返すのか?
- 保全:『もしも』の時はどうするのか?
この3つのポイントを、明確かつ客観的な資料に基づいて説明しきること。これこそが、融資審査をスムーズに進めるための最大の秘訣です。
これらを私たちは「三種の神器」と呼んでいます。次章から、一つずつ具体的に見ていきましょう。
【第一の神器】資金使途:『何に』お金を使うのか?を明確に伝える
融資審査の第一歩は、「借りたお金を何に使うのか」を具体的に示すことです。
銀行は、融資した資金が企業の成長や収益向上に繋がり、最終的に返済原資を生み出すものであるかを確認したいと考えています。
資金使途が曖昧では、「本当に必要な資金なのか?」「他の目的に流用されるのではないか?」といった疑念を抱かせてしまい、審査の初期段階でつまずく原因となります。
資金使途は、大きく分けて以下の2つに分類されます。
- 設備資金
- 事業拡大のための機械購入、工場の増築、新規店舗の開設、車両の購入など、長期的に会社の資産となるものへの投資。
- 運転資金
- 仕入代金の支払い、人件費、家賃など、日々の事業活動を円滑に運営していくために必要となる資金。
これらの使い道を明確に伝えるために、客観的な根拠資料を提出することが極めて重要です。
必要な提出資料とは?
口頭での説明だけでなく、なぜその金額が必要なのかを第三者が見ても納得できる資料を準備しましょう。
- 設備資金の場合
- 見積書(機械や車両の購入、工事など)
- 契約書(不動産の購入など)
- 事業計画書(新規出店に伴う投資効果のシミュレーションなど)
- 運転資金の場合
- 事業計画書(売上増加に伴い、どれくらいの仕入資金や人件費が追加で必要になるかの説明)
- 資金繰り表(今後の入出金の予測)
これらの資料を添えることで、資金使途の妥当性と計画性に説得力を持たせることができます。
【第二の神器】返済可能性:『どうやって』返すのか?を具体的に示す
銀行が融資審査で最も重要視するポイント、それが「返済可能性」、つまり企業の返済能力です。
銀行は営利企業であり、貸したお金が利息と共にきちんと返ってくることを大前提としています。
したがって、「どうやって返済していくのか」を論理的に説明できなければ、融資を受けることはできません。
この返済能力を示すための重要なキーワードが「キャッシュフロー」です。
返済能力の証明:「利益+減価償却費」
銀行は、企業の返済原資を基本的に「キャッシュフロー」で見ています。
キャッシュフローとは、簡単に言えば「会社が事業活動で生み出した、自由に使える現金」のことです。
会計上の利益(税引後当期純利益)も重要ですが、銀行はそれに減価償却費を足したものを、大まかな返済原資として捉えます。
返済原資=税引後当期純利益+減価償却費
なぜ減価償却費を足すのでしょうか。
減価償却費は、設備などの資産の価値減少分を費用として計上するものですが、実際に社外へ現金が出ていくわけではない「非資金費用」だからです。
そのため、会計上の利益に減価償却費を足し戻すことで、より実態に近い現金の創出能力を測ることができるのです。
健全性の指標:「償還年数」とは?
もう一つ、返済可能性を評価する上で重要な指標が「償還年数」です。
これは、今ある借入金全体(短期・長期含む)を、年間のキャッシュフローで何年で返済できるかを示す指標です。
償還年数=総借入金÷年間キャッシュフロー(利益+減価償却費)
この償還年数が一般的に「10年以内」であることが、財務的に健全な水準の一つの目安とされています。
自社の償還年数を計算し、健全な範囲内であることを示す、あるいは範囲外であっても今後の改善計画を具体的に提示することができれば、銀行の納得感は大きく高まります。
【第三の神器】保全:『もしも』の時の備えを伝える
最後の神器は「保全」です。
これは、万が一、企業の業績が悪化し、計画通りの返済が困難になった場合に、銀行が貸したお金をどうやって回収するか、という視点です。いわば、リスクヘッジの側面です。
どんなに素晴らしい事業計画であっても、ビジネスに「絶対」はありません。銀行は常に最悪の事態を想定しています。
そのため、万が一の際の回収手段が確保されているかどうかは、融資判断における重要な要素となります。
保全の具体的な手段としては、以下のようなものが挙げられます。
- 不動産担保
土地や建物などを担保として提供します。
融資審査において最も評価が高い保全策の一つです。 - 経営者の連帯保証
経営者個人が会社の債務を連帯して保証します。
近年は「経営者保証ガイドライン」の運用により、必ずしも必要とされないケースも増えていますが、依然として重要な要素です。 - 信用保証協会の保証
公的な機関である信用保証協会が、企業が返済不能に陥った場合に銀行へ代位弁済を行う制度です。
特に実績の浅い企業や担保が不足している場合に有効な手段となります。
これらの保全策をどの程度提供できるかによって、金利や融資金額などの条件交渉にも影響を与える場合があります。
審査を加速させる「カバーレター」という切り札
ここまで解説してきた「三種の神器」、すなわち【資金使途】【返済可能性】【保全】。
これらを決算書や事業計画書と共にただ提出するだけでは、その意図が担当者に十分に伝わらない可能性があります。
そこでおすすめしたいのが、A4用紙一枚程度の「カバーレター(送付状)」を添えることです。
このカバーレターに、今回の融資申込の要点として、
- 何に使う資金が、いくら必要なのか(資金使途)
- その資金を、どの事業の利益から、どのように返済していくのか(返済可能性)
- 万が一の場合の備えとして、どのような担保・保証を提供できるか(保全)
を簡潔にまとめて記載するのです。
多忙な銀行担当者は、毎日多くの企業の資料に目を通しています。
この一枚があるだけで、担当者は融資案件の全体像を瞬時に把握でき、その後の審査部門への説明もスムーズに進みます。
結果として、審査プロセスが格段にスピードアップするのです。
少しの手間が、結果に大きな違いを生む、非常に効果的なテクニックです。
信頼関係を築くための「決算報告」という習慣
最後に、融資をスムーズに進めるための、最も本質的で重要なアクションをお伝えします。
それは、日頃から銀行と良好な関係を築いておくことです。
特に、決算が終わったら、必ず経営者自身が銀行の支店へ足を運び、業績報告を行う習慣をつけましょう。
その場で伝えるべきことは、以下の3点です。
- 前期の振り返り
決算内容の説明。良かった点、悪かった点とその原因などを率直に話す。 - 今期の見通し
今期はどのような計画で、どれくらいの売上・利益を目指すのか。 - 今後の資金需要
今後の事業展開の中で、いつ頃、どのような資金が必要になる可能性があるか。
これを継続することで、銀行はあなたの会社の状況を継続的に把握でき、深い理解者となります。
普段からコミュニケーションを取り、信頼関係を醸成しておくこと。
「いざ、資金が必要だ」という時に、迅速かつ親身に相談に乗ってもらえるかどうかは、こうした日々の地道な活動にかかっているのです。
まとめ:銀行との良好な関係が、未来の資金調達を左右する
今回は、銀行融資の審査をスムーズに進めるための「三種の神器」について解説しました。
- 【第一の神器】資金使途
客観的な資料に基づき、「何に使うか」を明確にする。 - 【第二の神器】返済可能性
「利益+減価償却費」というキャッシュフローで、「どうやって返すか」を具体的に示す。 - 【第三の神器】保全
担保や保証で、「万が一の備え」を提示する。
これらのポイントを「カバーレター」にまとめ、決算報告などの定期的なコミュニケーションを通じて銀行との信頼関係を築くこと。
これが、中小企業が安定した資金調達を実現するための王道です。
銀行を単なる「お金を借りる場所」と捉えるのではなく、事業を共に成長させていく「パートナー」として捉え、誠実な情報提供と対話を心がけてみてください。
その姿勢が、きっとあなたの会社の未来を力強くサポートしてくれるはずです。