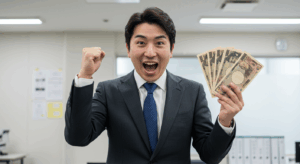銀行融資の第一歩!「マル保」を完全攻略し、資金調達を成功させる

皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週金曜日に、経営者なら知っておきたい「銀行融資」についての知識を解説しています。
中小企業の経営者にとって、資金調達は事業の成長、ひいては存続を左右する最重要課題の一つです。
その中でも、多くの経営者が最初に検討するのが「銀行融資」ではないでしょうか。
しかし、いざ銀行の窓口に行こうと思っても、「ウチのような小さな会社が相手にされるだろうか」といった不安を感じる方も少なくありません。
実は、銀行融資にはいくつかの種類があり、その仕組みを正しく理解することが、資金調達成功への第一歩となります。
特に、ほとんどの企業が最初にお世話になるであろう「マル保(保証協会付き融資)」という制度の知識は、経営者にとって必須教養と言っても過言ではありません。
本記事では、これまで数多くの企業の資金調達を支援してきた税理士の視点から、銀行融資の基本である「マル保」について、その仕組みから実践的な活用ポイントまで、体系的に解説していきます。
まずは基本から!銀行融資の2つの顔、「マル保」と「プロパー」
銀行などの民間金融機関から融資を受ける方法は、大きく分けて「マル保(まるほ)」と「プロパー」の2種類が存在します。
この2つの違いを理解することが、融資戦略を立てる上での出発点となります。
初めての融資の強い味方「マル保(保証協会付き融資)」
「マル保」とは、「信用保証協会」という公的な機関が会社の保証人になってくれる融資制度です。
特に、創業して間もない企業や、まだ事業実績が十分に積み上がっていない企業にとって、資金調達の強力な味方となります。
なぜなら、金融機関にとって最大の懸念は「貸したお金が返ってこない」という貸し倒れリスクだからです。
しかし、マル保を利用すれば、万が一会社が返済できなくなった場合でも、信用保証協会が代わりに返済してくれます。
この「公的なお墨付き」があることで、金融機関はリスクを大幅に低減できるため、融資のハードルがぐっと下がるのです。
会社の信用力の証「プロパー融資」
一方、「プロパー融資」は、信用保証協会の保証を一切利用せず、金融機関が100%自らのリスクで実行する融資を指します。
銀行が直接すべてのリスクを負うため、その審査はマル保に比べて格段に厳しくなります。十分な事業実績、健全な財務内容、そして将来性などが厳しく問われます。
逆に言えば、このプロパー融資を受けられるということは、その銀行から「この会社は事業も財務も安定しており、将来性も高い」という太鼓判を押された証拠です。
企業の信用の高さを示す一種のステータスであり、多くの経営者が目指すべき目標と言えるでしょう。
多くの企業は、まず「マル保」で銀行との取引実績をコツコツと積み上げ、事業成長とともに財務内容を強化し、将来的には「プロパー融資」へ移行していく、というステップを踏むのが一般的です。
なぜ「マル保」は借りやすい?その仕組みを徹底解剖
マル保が中小企業にとって有利な制度であることはご理解いただけたかと思います。
では、その背景にある仕組みはどのようになっているのでしょうか。
この仕組みを理解することは、融資担当者との対話や交渉を円滑に進める上で非常に重要です。
中小企業の公的な保証人「信用保証協会」とは
信用保証協会は、中小企業・小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関です。
その最も重要な役割が「信用保証」業務、つまり中小企業の「公的な保証人」となることです。
私たちは、融資を受ける際に、保証の対価として所定の「保証料」を信用保証協会に支払います。
この保証料を支払うことで、万が一、業績不振などで返済が困難になった場合に、保証協会が私たち企業に代わって金融機関へ残りの借入金を返済してくれます。
これを「代位弁済(だいいべんさい)」と呼びます。この仕組みがあるからこそ、金融機関は安心して中小企業に融資ができるのです。
銀行の審査を健全に保つ「責任共有制度」
ここで一つ、鋭い方は「保証協会が100%肩代わりしてくれるなら、銀行は誰にでも融資してしまうのでは?」と疑問に思うかもしれません。
かつては実際に、保証協会が100%損失を補填していた時代もありました。
しかし、それでは銀行側の審査が甘くなり、安易な融資が横行してしまう「モラルハザード」が起きる懸念がありました。
そこで現在では、貸し倒れが発生した際の損失を、金融機関と保証協会とで分担する「責任共有制度」が導入されています。
原則として、損失の負担割合は以下のようになっています。
- 信用保証協会:損失の80%を負担
- 金融機関:損失の20%を負担
金融機関も20%のリスクを負うことで、自行の審査にも緊張感が生まれます。
これにより、保証協会付き融資でありながら、より健全な融資審査が行われる体制が整っているのです。
経営者としては、この「銀行も2割のリスクを負っている」という事実を知っておくと、銀行との交渉の際に役立つ場面があるかもしれません。
「マル保」を最大限に活用するための経営者の必須知識
「マル保」は非常に有用な制度ですが、その効果を最大限に引き出すためには、経営者として知っておくべき重要なポイントがいくつかあります。
知っているかどうかで、借りられる金額やコストが変わってくる可能性もあるため、しっかりと押さえておきましょう。
自社の「保証枠」はいくら?保証料はどう決まる?
信用保証協会が保証してくれる金額には、上限が定められています。これを「保証枠」と呼びます。
- 無担保での保証枠:最大8,000万円
- 不動産などの担保を提供する場合:別途最大2億円
つまり、合計で最大2億8,000万円の保証枠が設定されています。
自社が現在いくらの保証枠を利用しているのかを把握しておくことは、今後の資金調達計画を立てる上で不可欠です。
また、私たちが支払う「保証料」は一律ではありません。その料率は、決算書の評価(CRD評価※)などに基づき、会社の信用力に応じて9段階に区分されています。
一般的に、年率 約0.45%~2.2% の間で設定され、信用力が高く、財務内容が良い企業ほど保証料率は低くなります。
日頃から質の高い決算書を作成し、財務基盤を強化しておくことが、融資の受けやすさだけでなく、保証料というコストの削減にも直結するのです。
※CRD(Credit Risk Database)評価:信用保証協会や金融機関が利用する、中小企業の信用リスクを統計的に算定するモデルのこと。
最新トレンド「経営者保証ガイドライン」を意識する
これまでの日本の融資慣行では、中小企業が融資を受ける際、経営者個人が会社の借金の「連帯保証人」になるのが当たり前でした。
しかし、この個人保証は、経営者が一度事業に失敗すると、個人としても多額の負債を抱え、再チャレンジすることが極めて困難になるという大きな課題を抱えていました。
そこで国は、こうした状況を改善し、起業や事業承継を促進するために、経営者の個人保証を求めない融資を推進しています。
その中核となるのが「経営者保証に関するガイドライン」です。
このガイドラインが示す以下の要件を満たすことで、経営者保証なしで融資を受けられる可能性が広がっています。
- 【主な要件】
- 法人と経営者個人の資産・経理が明確に区分・分離されている(公私混同がない)。
- 自己資本の充実など、財務基盤がしっかりしている。
- 金融機関の求めに応じ、資産や負債の状況などを正確かつ真摯に情報開示している。
すぐに個人保証を完全に外すことは難しい場合もありますが、国全体としてこういう流れがあることと、これらの要件を意識したクリーンな会社経営を心がけることが、将来の円滑な資金調達や、万が一の際の経営者自身のリスク軽減に繋がることは、ぜひ知っておいてください。
まとめ:融資成功の第一歩は「マル保」の完全理解から
今回は、銀行融資の基本である「マル保(保証協会付き融資)」について、その仕組みから、経営者が知っておくべき実践的な知識までを詳しく解説しました。
ほとんどの中小企業にとって、資金調達のキャリアは「マル保」から始まります。これは、事業を成長軌道に乗せるための、いわば最初のエンジンです。
このエンジンの仕組みを正しく理解し、自社の状況と照らし合わせて「保証枠はあといくらか」「保証料を下げるために決算をどう改善すべきか」「経営者保証を外すために何をすべきか」といった視点で準備を進めることが、資金調達の成功確率を大きく左右します。
銀行融資は、決して怖いものではありません。正しい知識を身につけ、誠実な経営を続けていれば、銀行はあなたの事業を支える心強いパートナーとなってくれるはずです。
まずは本記事の内容を参考に、自社の資金調達戦略を見直してみてはいかがでしょうか。