節税対策よりも効果的!?あの社会保険料削減スキームの落とし穴
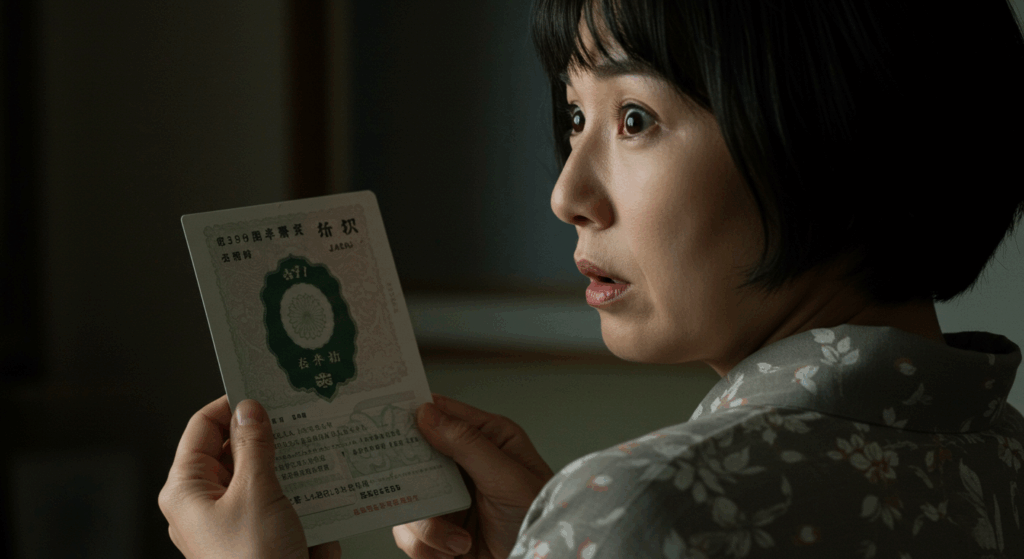
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週水曜日に、経営者なら知っておきたい「節税対策」についての知識を解説しています。
中小企業の経営者の皆様にとって、「社会保険料の負担」は常に頭を悩ませる大きな課題ではないでしょうか。
役員個人と会社の双方に重くのしかかるこのコストを、少しでも圧縮したいと考えるのは当然のことです。
その解決策の一つとして、近年注目を集めているのが「役員報酬の一部を賞与に振り分ける」ことで、社会保険料の負担を軽減するスキームです。
月々の役員報酬を低く設定し、その分を賞与として受け取ることで、社会保険料の算定基礎を合法的に引き下げるという有名な手法があります。
確かに、短期的なキャッシュフロー改善効果は絶大で、魅力的に映るかもしれません。
しかし、税理士として多くの現場を見てきた私からすると、このスキームには安易に飛びつくべきではない、看過できない「問題点」が存在します。
今回は、この社会保険料削減スキームが内包する3つの重大なリスクについて、専門的な視点から詳しく解説していきます。
目先の利益の裏にあるデメリットを正確に理解することが、会社とご自身の未来を守る第一歩です。
リスク1:制度改正により、いつ使えなくなるか分からない時限的な手法である
まずご理解いただきたいのは、この社会保険料削減スキームが、国(厚生労働省)によってすでに問題視されているという事実です。
2024年9月末に開催された「第183回社会保障審議会医療保険部会」では、まさにこの手法が審議の対象となりました。
厚生労働省が公開している以下の資料をご覧いただければ、国が「働き方の多様化」を名目に、被用者保険(健康保険や厚生年金保険)の適用や保険料算定のあり方について、見直しを検討していることが明確に分かります。
参照:厚生労働省「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方について」
これは何を意味するのでしょうか。裏を返せば「現時点では」まだ規制されておらず、完全合法のスキームであると言えます。
しかし、国の審議会で議題に上がっている以上、早ければ2025年、2026年といった近い将来、この手法が法改正によって封じられる可能性は非常に高いと考えられます。
もちろん、これはあくまで可能性であり、どのような形で規制されるか、あるいは何らかの形で存続するのかは現時点では断定できません。
しかし、いつ終わるか分からない時限的な節税策に、会社の根幹である役員報酬制度を大きく委ねることの危うさについては、経営者として冷静に判断する必要があるでしょう。
リスク2:将来受け取る厚生年金の受給額が減少する
次に指摘すべきは、将来の生活設計に直結する問題です。
それは、将来受け取れる公的年金(特に厚生年金)の額が減ってしまうという、考えてみれば至極当然の帰結です。
ご存知の通り、厚生年金の受給額は、現役時代に納めてきた社会保険料の金額(正確には、その基準となる標準報酬月額・標準賞与額)に応じて決まります。
このスキームは、まさにその「標準報酬月額」を意図的に低く抑えることで社会保険料を削減するものです。
つまり、支払う保険料が少なくなるということは、将来の自分への給付が減ることに直結するのです。
目先の数十万円、数百万円の社会保険料を削減するために、老後の生活を支える重要な収入源である年金を、数十年単位で減らしてしまう。
このトレードオフが、本当に自社の、そしてご自身のライフプランにとって合理的な選択なのか。長期的な視点での検証が不可欠です。
リスク3:【最大の懸念】経営者死亡時の「役員退職金」が激減する
そして、私がこのスキームにおける最大のリスクだと考えているのが、経営者に万が一の事態(死亡など)が発生した際に、ご遺族に支払われるべき「役員退職金」の額が極端に少なくなってしまうという問題です。
これは、会社の財務と遺族の生活を同時に揺るがしかねない、非常に深刻な論点です。
役員退職金の計算方法とスキームの致命的な影響
まず、役員退職慰労金の損金算入限度額(会社が経費として計上できる上限額)を計算する一般的な算式を確認しておきましょう。
役員退職金の損金算入限度額 = 最終月額報酬 × 在任年数 × 功績倍率
※功績倍率は、役職に応じて税務上妥当とされる倍率で、社長の場合は一般的に「3倍」が用いられます。
この計算式が、なぜ社会保険料削減スキームと致命的に相性が悪いのか。具体的な数字で比較してみましょう。
【ケース1:通常の役員報酬設定の場合】
- 最終月額報酬:100万円
- 社長在任年数:25年
- 功績倍率:3倍
この場合、会社が損金として計上できる役員退職金の上限は、
100万円×25年×3=7,500万円
となります。
【ケース2:社会保険料削減スキームを適用した場合】
- 役員報酬(月額):5万円
- 役員賞与(年額):1,140万円
- 社長在任年数:25年
- 功績倍率:3倍
この場合、計算の基礎となるのはあくまで「最終月額報酬」です。賞与の額は考慮されません。
5万円×25年×3=375万円
いかがでしょうか。その差は実に7,125万円。
スキームを適用したがために、会社の経費にできる退職金の額が、7,500万円からわずか375万円にまで激減してしまうのです。
生命保険で備えても「課税リスク」は消えない
「死亡退職金は、会社で加入している生命保険でカバーすれば良いのでは?」
そう思われるかもしれません。しかし、ここにも大きな落とし穴があります。
仮に、会社が受取人となっている生命保険から数千万円の死亡保険金が支払われたとしても、上記のケース2では、役員退職金として損金処理できるのは375万円までです。
つまり、受け取った保険金から375万円を差し引いた残りの数千万円には、そのまま法人税が課税されてしまうのです。
社長の死という一大事に、会社は想定外の多額の納税負担を強いられることになります。
そして何より、社長の死亡退職金が少ないということは、長年会社を支えてきたご遺族(相続人)に、十分な資金を残すことができないこととほぼ同義です。
もちろん、70歳で勇退するなど、計画的に役員退職金を支給できるのであれば、退任の数年前にスキームの利用を停止し、月額報酬を適正な額に戻すことでこのリスクは回避可能です。
しかし、人の死期は誰にも予測できません。この「予測不能な死」というリスクを軽視すべきではないのです。
専門家としての見解:多数派の意見と私たちのスタンス
ここで一点、補足させていただきます。
一部の専門家(税理士など)の中には、「このスキームを適用して月額役員報酬を極端に下げても、死亡時の役員退職金は減らない」と主張する方がいることも事実です。
しかし、数多くの税務調査の実態や過去の判例を踏まえるならば、その主張が認められる可能性は極めて低いと言わざるを得ません。
役員退職金の妥当性を判断する上で「最終月額報酬」が極めて重要な指標であることは、実務における圧倒的なコンセンサスであり、私たちの見解もこれと全く同じです。
経営者の【突然の死亡】こそが、このスキームにおける最大のリスクであることに間違いありません。
まとめ:目先の利益に囚われず、長期的・複眼的な視点で経営判断を
今回は、役員報酬の賞与振り分けによる社会保険料削減スキームに潜む、3つの重大なリスクについて解説しました。
- 制度改正により、将来的に使えなくなる可能性が高い
- 将来受け取る年金額が減少してしまう
- 【最大のリスク】万が一の際、役員退職金が激減し、会社と遺族に大きな打撃を与える
このスキームがもたらす短期的なメリットは、確かに魅力的です。
しかし、その裏側には、会社の将来、経営者個人のライフプラン、そしてご家族の生活にまで影響を及ぼしかねない、深刻なリスクが潜んでいます。
これらのリスクを大きいと判断するか、許容範囲内と考えるかは、経営者お一人お一人の価値観や状況によって異なるでしょう。
しかし、その判断は、すべてのデメリットを正確に理解した上で行うべきです。
もし、ご自身での判断が難しい、自社の場合はどうなのか具体的に知りたいと思われた方は、決して一人で悩まず、私たち専門家にご相談ください。
目先の節税額だけではなく、事業承継やご家族の未来まで見据えた、最適な解決策を共に考えさせていただきます。

