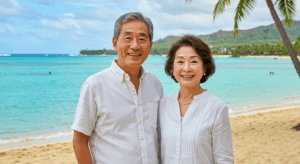税務調査が5年に延長!?期間延長に必要な法的要件と反論の根拠

皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週月曜日に、経営者なら知っておきたい「税務調査」についての知識を解説しています。
「税務調査」という言葉に、良いイメージを持つ経営者の方は少ないでしょう。
日々の経営に尽力する中で、突然やってくる税務調査の通知は、大きな不安とストレスの原因となります。
特に、調査官から何気なく告げられる「調査対象期間を3年から5年に延ばします」という一言は、経営に深刻な影響を与えかねません。
多くの経営者は、この一言に明確な反論ができず、調査期間の延長を受け入れてしまうケースが後を絶ちません。しかし、それは不当な結果を招く可能性があります。
これまで多くの現場で、調査官との交渉に立ち会ってきた経験から言えるのは、税務調査の期間延長には明確な法律上の要件があり、それを知っているか否かで、結果は天と地ほど変わるということです。
この記事では、なぜ調査期間が延長されるのか、そして、その延長を阻止するために経営者が知っておくべき「法的根拠」と「具体的な反論のポイント」を、専門家の視点から分かりやすく解説します。
税務調査の基本:調査対象期間は原則「3年」
まず大前提として、税務調査の対象となる期間は、法律で明確に定められているわけではなく、実務上の運用として「3年分」とされるのが一般的です。
税務署から送られてくる「税務調査の事前通知」には、通常、調査対象期間として直近3年分(3事業年度)が記載されているはずです。
これは、ほとんどの税務調査で採用されている基本的なルールだと認識してください。しかし、問題はここからです。
調査が開始され、帳簿や資料を確認する過程で、調査官が何らかの誤り(専門用語で「非違(ひい)」と言います)を発見した場合、冒頭で述べたように調査期間の延長を打診してくることがあるのです。
なぜ調査期間が「5年」に延長されるのか?
調査期間が3年から5年に延長されれば、単純に調査される範囲が2年分増えることになります。
もし、その2年間にも同様の誤りがあったと指摘されれば、当然ながら追加で納める税金(追徴税額)も大きく膨れ上がってしまいます。
調査官は、調査対象の3年間で申告漏れなどの非違が見つかると、「他の年も同じような誤りをしているのではないか」という前提で、調査期間の延長を求めてきます。
これに対し、多くの経営者は「誤りがあったのだから仕方ない」と、延長要求を安易に受け入れてしまいがちです。
しかし、ここで立ち止まって考えてみてください。その期間延長は、本当に法的に正当なものなのでしょうか?
「事前通知」の法的効力とその重要性
ここで極めて重要になるのが、調査の最初に受け取る「事前通知」の存在です。
事前通知は、単なる「これから調査に行きます」というお知らせではありません。
国税通則法という法律に基づいて行われる手続きであり、通知された内容には法的な拘束力が生じます。
つまり、事前通知で「調査対象期間は3年です」と通知された以上、税務署側はその3年という期間に縛られるのが原則です。
それを超えて4年、5年と遡って調査を行うためには、法律で定められた特別な要件をクリアしなければならないのです。
形式的な手続きに見える事前通知ですが、実はこれこそが、不当な調査範囲の拡大を防ぐための最初の防波堤となるのです。
期間延長の法的根拠は?国税通則法を読み解く
では、その「特別な要件」とは何でしょうか。
根拠となる法律の条文を見てみましょう。少し難しいですが、ポイントを解説します。
国税通則法 第74条の9 第4項
第1項の規定は、当該職員が、当該調査により当該調査に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項以外の事項について非違が疑われることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。
この条文を非常にシンプルに要約すると、「事前通知した内容(調査対象期間など)を変更して追加で調査するには、『通知した範囲外の事項について非違が疑われることになった場合』に限る」という意味になります。
これだけではまだ分かりにくいかもしれません。実は、国税庁は職員向けに、より具体的な解説を出しています。
【最重要】期間延長が認められる「本当の要件」とは?
国税庁が内部向けに出している「税務調査手続等に関するFAQ(職員用)」には、期間延長が認められるケースについて、以下のような問答が記載されています。
これこそが、私たちが知るべき「本当の要件」です。
問1-56
事前通知した調査対象期間以外の課税期間につき、質問検査等を行う場合とは、具体的にどのような場合をいうのか
(答)
事前通知した調査対象期間を調査している過程で非違を把握し、その非違が認められる取引先との取引が調査対象期間よりも前の課税期間にも存在するなど、調査対象期間よりも前の課税期間にも同様の非違が疑われる場合などが該当します。
ここに書かれている内容が、全てを物語っています。重要なポイントを整理しましょう。
- 間違い探しゲームではない
- NGパターン
事前通知された3年間を調査した結果、誤りが見つかった。
→ だから、自動的に5年に延長する。 - これは、法律上の要件を満たしていません。
- NGパターン
- これが本当の要件
- OKパターン
事前通知された3年間を調査する過程で、ある誤りを発見した。
そして、その誤りに関連する証拠(例えば、特定の取引先との契約書や請求書など)から、「通知した3年間よりも前の期間にも、同じような誤りが存在していることが強く疑われる」と判断された場合。
→ その場合に限り、延長が認められる。
- OKパターン
いかがでしょうか。
単に「調査対象の3年間に誤りがあった」という事実だけでは、調査期間を5年に延長する十分な理由にはなりません。
「調査中の3年間の調査から、それ以前の年度にも同様の誤りがあるという『疑い』が生じたこと」が絶対的な要件なのです。
この違いを理解しているかどうかが、調査官の要求に冷静かつ的確に反論できるかどうかの分かれ道となります。
経営者が今すぐできること、持つべき視点
もし、あなたの会社に税務調査が入り、調査官から調査期間の延長を求められたら、どう対応すべきでしょうか。
- 安易に同意しない
まずは「分かりました」と即答してはいけません。
その一言で、法的に同意したと見なされる可能性があります。 - 冷静に根拠を問う
感情的にならず、この記事で学んだ知識を基に、冷静に以下の質問を投げかけてみてください。- 「調査期間を延長されるとのことですが、その法的根拠は何でしょうか?」
- 「国税通則法第74条の9第4項に基づき、事前通知した期間外を調査するには『同様の非違が疑われる場合』と承知していますが、調査対象期間よりも前の期間に、同様の非違があると疑う具体的な理由や証拠は何でしょうか?」
- 専門家(税理士)に相談する
もちろん、これらの交渉を経営者自身が行うのは困難な場合もあるでしょう。その際は、必ず顧問税理士に相談してください。
そして、税理士がこの法的根拠を理解しているかを確認し、共に毅然とした態度で交渉に臨むことが重要です。
調査官の中には、この要件を十分に理解せず、安易に期間延長を求めてくる者もいるのが実情です。
しかし、こちらが正しい知識で武装していれば、不当な要求を退けることは十分に可能なのです。
まとめ:正しい知識が会社を守る盾になる
税務調査は、経営者にとって避けては通れない道の一つかもしれません。
しかし、それは決して、税務署の言いなりにならなければならない場ではありません。
- 税務調査の対象期間は原則3年。
- 「事前通知」には法的拘束力がある。
- 期間延長には「調査対象期間より前の期間にも同様の非違が疑われる」という厳格な要件が必要。
このポイントをしっかりと心に刻んでおくだけで、いざという時の対応は大きく変わります。
税務調査とは、法律と事実に基づいて行われる、いわば論理の交渉の場です。
正しい知識という「盾」を持つことが、あなたの会社を不当な追徴課税から守るための、最も確実な方法なのです。
もし、税務調査に関して少しでも不安な点や、具体的な相談事項がございましたら、いつでも専門家を頼ってください。
私たちは、経営者の皆様が安心して事業に専念できるよう、全力でサポートいたします。