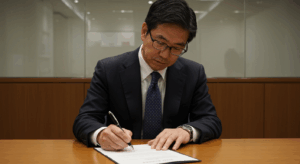税務調査はいつ来る?調査時期から読み解く税務署の狙いと対策
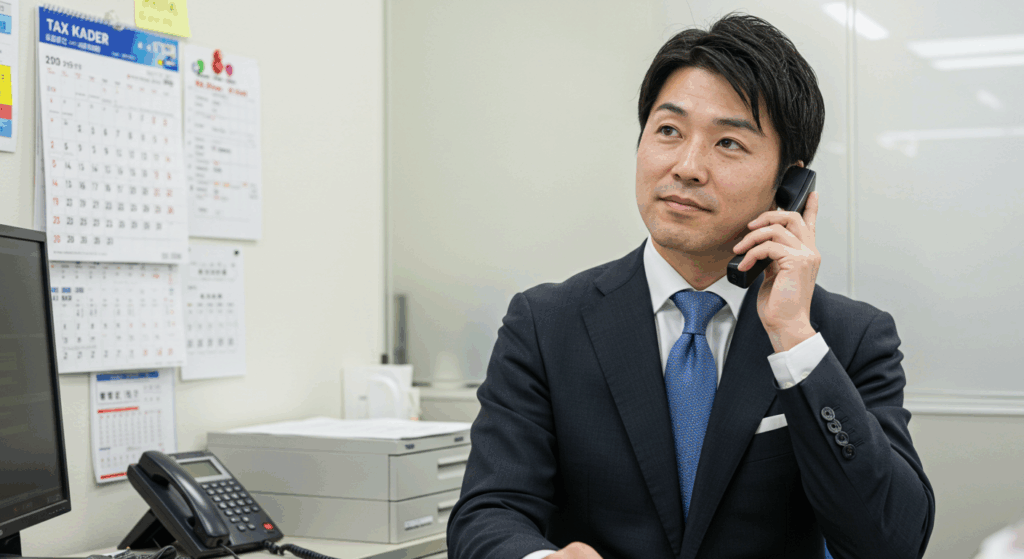
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週月曜日に、経営者なら知っておきたい「税務調査」についての知識を解説しています。
「うちの会社には、いつ税務調査が来るのだろうか…」
日々の経営に邁進される中で、多くの経営者様がふと、このような不安を感じることがあるのではないでしょうか。
税務調査は、できれば避けたい、しかし避けては通れない経営上のリスクの一つです。
ただ、闇雲に怖がる必要はありません。実は、税務調査が行われる時期には一定の傾向があり、その背景を知るだけでも、漠然とした不安は大きく和らぎます。
本記事では、税理士だけが知っている「税務調査の時期」について、経営者様にぜひ知っておいていただきたい基礎知識をお伝えします。
専門家として、皆様が少しでも安心して事業に集中できるための一助となれば幸いです。
税務署の「年間スケジュール」を知る
まず、税務調査の時期を考える上で基本となるのが、税務署の内部的な動きです。
一般企業が4月に新年度を迎えるのとは異なり、国税局や税務署では、毎年7月に新しい事務年度がスタートします。
- 上期(春の調査)
1月~6月 - 下期(秋の調査)
7月~12月
7月には調査官の人事異動があり、新たな体制で下期の業務が始まります。
この大きな流れが、いつ、どのような会社に調査が入りやすいのかを考える上での出発点となります。
法人税調査の対象になりやすい時期とは?
法人に対する税務調査は、闇雲に行われるわけではなく、多くの場合、法人の決算月が関係してきます。
税務署が申告書を受け取ってから、その内容を検討し、調査先を選定するまでには一定の時間が必要だからです。
一般的には、以下のような傾向があります。
- 上期(1月~6月)に調査の可能性が高まる法人
- 対象:6月決算~1月決算法人
- 下期(7月~12月)に調査の可能性が高まる法人
- 対象:2月決算~5月決算法人
例えば、日本の多くの企業が採用している3月決算の場合、申告期限は5月末です。
税務署は提出された申告書を分析・検討する時間を経て、新体制が整った下期(特に秋以降)に調査に着手する、というケースが多く見られます。
もちろんこれはあくまで原則的な傾向ですが、自社の決算期から、税務署が動きやすい時期を把握しておくだけでも、心の準備は大きく変わるはずです。
経営者個人に関わる「資産税」の調査時期
中小企業の経営者様にとって、会社の経営だけでなく、ご自身の資産やご家族への承継も重要な関心事かと思います。
不動産の売却や相続・贈与などに関わる「資産税」の税務調査にも、時期的な傾向が存在します。
- 譲渡所得(不動産売却など)の調査
主に 上期(1月~6月) - 相続税・贈与税の調査
主に 下期(7月~12月)
特に相続税の調査は、内容が複雑で時間を要するため、体制の整った下期に集中する傾向があります。
法人のことだけでなく、こうした個人に関わる税務についても、大きな流れを知っておくことは大切です。
【要注意】原則から外れた「イレギュラーな調査」が示唆すること
ここまでお話ししてきたのは、あくまで一般的な調査のサイクルです。
しかし、私たちが実務で特に注意を払うのが、この原則から外れたタイミングでやってくる「イレギュラーな税務調査」です。
もし、このセオリーから外れた時期に調査の連絡が来た場合、それは単なる偶然ではないかもしれません。
税務署がわざわざ通常のサイクルを崩してまで調査に来るということは、「何らかの具体的な情報を基に、調査対象として明確にマークしている」可能性を示唆しています。
例えば、
- 取引先とのやり取りの中で、申告内容との矛盾が見つかった(反面調査)
- 第三者から、信憑性の高い情報提供があった(資料せん等)
といったケースが考えられます。
このような状況は、税務署側も相応の準備をして臨んでくるため、経営者様だけで対応するのは非常に困難であり、精神的なご負担も計り知れません。
その電話、調査ですか?指導ですか?―無用な加算税を避ける視点
ここからは、少し実践的なお話をします。特に個人事業主の方や、確定申告を終えた春先(3月下旬~5月)に注意したい点です。
この時期、税務署から申告内容について電話連絡や「お尋ね」の文書が届くことがあります。
多くは単純な計算ミスや記載漏れの確認ですが、ここで非常に重要なのが、その連絡が「税務調査」なのか、それとも「行政指導」なのかという違いを意識することです。
- 税務調査
法律(質問検査権)に基づく強制力を伴う手続き。
指摘を受けて修正した場合、本来の税金に加えて「過少申告加算税」などのペナルティが発生します。 - 行政指導
あくまで税務署の任意のお願い。
これに応じて自主的に修正申告した場合、原則として加算税はかかりません。
問題は、この区別が曖昧なまま電話でやり取りし、指摘通りに修正した結果、後から税務署に「あれは実質的な調査でしたので、加算税も納付してください」と言われてしまうケースが少なくないことです。
税務署からの電話だからといって、すべてが厳しい「調査」とは限りません。
しかし、安易に対応すると、払う必要のなかったはずのペナルティまで課されかねないのです。
この「調査」と「指導」の違いを知っているか否かが、結果を大きく左右することがあります。
まとめ:本当の安心は「信頼できるパートナー」と共に
税務調査の時期や、税務署からの連絡に対する注意点など、いくつかの知識やノウハウをご紹介しました。
このように、知っているか知らないかで、有利にも不利にもなり得るのが税務の世界です。
しかし、経営者の皆様がこれらの全てを把握し、お一人で対応するのは現実的ではありません。
私が考える税務調査対策で最も重要なことは、日頃から何でも相談でき、いざという時には経営者様の「盾」となって共に戦ってくれる専門家、つまり信頼できる税理士というパートナーがいることです。
私は、税務の専門家として、経営者の皆様が目の前の事業に安心して集中できる環境を守りたいと心から願っています。
税務調査に関するご不安やご心配事がございましたら、どんな些細なことでも構いません。どうぞお一人で抱え込まず、いつでもご相談ください。