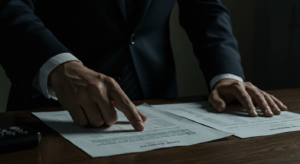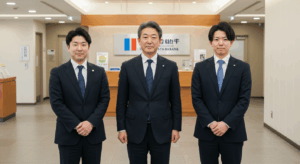社員1人で年間60万円コスト削減!給与を外注費に変える最強の節税対策

皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週水曜日に、経営者なら知っておきたい「節税対策」についての知識を解説しています。
会社の利益を最大化し、手元に残る現金をいかに増やすか。
これは、すべての中小企業経営者が日々向き合っている重要な経営課題ではないでしょうか。
設備投資、新規事業、人材採用など、成長のための選択肢は多々ありますが、その原資となるキャッシュフローを改善する強力な一手として、今回は「人件費」の構造に踏み込む節税策をご紹介します。
それは、社員への「給与」を「外注費」として支払うという手法です。
「社員を外注にするなんて、本当にできるのか?」「リスクはないのか?」と感じるかもしれません。
しかし、正しい手順と理解のもとで実行すれば、会社の財務体質を劇的に改善できる可能性があります。
本記事では、数多くの企業の財務を見てきた税理士の視点から、この節税策の具体的なメリット、成功事例、そして最も重要な「税務調査で否認されないための注意点」まで、実践的なノウハウを余すところなく解説します。
なぜ「給与の外注費化」で会社の現金が60万円以上も増えるのか?
社員への支払いを「給与」から「外注費」に変えるだけで、なぜこれほど大きなインパクトが生まれるのでしょうか。
その理由は、大きく分けて2つあります。
- 社会保険料の会社負担がゼロになる
従業員を雇用する場合、会社は健康保険や厚生年金保険といった社会保険料の約半分を負担する義務があります。
これは、利益が出ているかどうかにかかわらず発生する固定費であり、経営上の大きな負担です。
しかし、外部の事業者への支払いである「外注費」には、この社会保険料の負担が発生しません。 - 消費税の納税額が減る(仕入税額控除)
「給与」は消費税の課税対象外(不課税取引)のため、いくら支払っても消費税の計算上、経費として差し引くことはできません。
一方で、「外注費」は課税仕入れに該当するため、支払った外注費に含まれる消費税額を、自社が納めるべき消費税額から控除(仕入税額控除)できます。
言葉だけでは分かりにくいかもしれませんので、具体的なシミュレーションを見てみましょう。
【シミュレーション】月給30万円(年収360万円)の社員を外注に切り替えた場合
(※支払総額は360万円で変わらないと仮定)
| 項目 | ① 給与として支払う場合 | ② 外注費として支払う場合 | 差額(会社にとってのメリット) |
| 支払額の内訳 | 給与:3,600,000円 | 本体価格:3,272,728円 消費税:327,272円 | – |
| 会社負担の社会保険料 | 約507,060円 | 0円 | + 507,060円 |
| 控除できる消費税額 | 0円 | 327,272円 | + 327,272円 |
このケースでは、経費(本体価格)が減ることで法人税の負担が若干増えるものの、それを差し引いても社会保険料と消費税の削減効果により、会社の手残りは年間で60万~70万円も増加します。
これは、あくまで年収360万円の社員一人を切り替えた場合の試算です。
もし対象となる社員が複数名いたり、より高年収の社員であったりすれば、その節税効果はさらに大きなものになります。
【業種別】外注化で成功しているビジネスモデルのカラクリ
「給与の外注費化」は、どんな職種でも適用できるわけではありません。
この手法が特に効果を発揮するのは、個人の成果が売上に直結しやすい専門職や営業職です。
ここでは、実際に外注化をうまく活用して成長しているビジネスモデルを2つご紹介します。
ケーススタディ1:急成長する美容室の「儲かる構図」
昨今、多店舗展開で急拡大している美容室チェーンの多くが、この外注化の仕組みを取り入れています。
- 仕組み
美容師を社員として雇用するのではなく、個人事業主(外注先)として業務委託契約を結びます。
報酬は固定給ではなく、美容師個人の売上(例:売上の40%)に応じた完全歩合制です。 - 双方のメリット
- 美容師側
頑張って顧客を増やせば収入が青天井に増えるため、モチベーションが向上します。
自身の技術や人気が直接収入に反映される、やりがいのある働き方が可能です。 - 会社側
社会保険料や消費税の負担を大幅に削減できます。
これにより生まれたキャッシュを、新たな店舗展開の原資に充て、スピーディーな事業拡大を実現できるのです。
- 美容師側
ただし、ここで重要なポイントは「全員を外注にしない」ということです。
この美容室でも、材料の発注、予約管理、電話応対などを行うバックオフィススタッフは、社員として雇用し「給与」を支払っています。
売上に直接連動しない内部事務職まで無理に外注化するのは現実的ではありません。
ケーススタディ2:マッサージ店・運送業の共通点
この「成果連動型職種の外注化」というモデルは、他の業界でも広く見られます。
- マッサージ店
多店舗展開するチェーンでは、施術を行うマッサージ師を外注とし、店長やマネージャー職を社員としています。 - 運送業
大手運送会社の配送ドライバーの多くは、会社と直接雇用契約を結ぶ社員ではなく、配送個数に応じて報酬を得る個人事業主(外注)として働いています。
このように、業務内容に応じて雇用形態を戦略的に使い分けることが、ビジネスを成功させる鍵となります。
あなたの会社でも可能?外注化できる職種の見極め方
美容室やマッサージ店は特殊な例だと感じるかもしれません。
しかし、成果を可視化しやすい職種であれば、多くの会社で外注化を検討する余地があります。
そのヒントとなるのが「保険外交員」の働き方です。
同じ保険営業という仕事でも、会社との関わり方によって報酬体系は主に3つのパターンに分かれます。
- フルコミッション(完全外注)
基本給はなく、成果に応じて報酬を得る完全歩合制。
交通費なども自己負担の個人事業主です。 - 社員(完全な給与制)
保険会社の正社員として、固定給や賞与を得る。
営業成績は給与査定に影響しますが、あくまで雇用契約です。 - ハイブリッド型(給与+外注費)
週1回の社内会議への出席など、拘束時間に対しては「給与」を支払い、
それ以外の営業成果に対しては「外注費(報酬)」を支払うパターンです。
このハイブリッド型は、多くの企業にとって参考になるはずです。
完全に成果主義に移行するのが難しい職務でも、社内業務などの拘束時間分を最低限の給与とし、成果に応じた上乗せ部分を外注費として切り分けるという柔軟な設計が可能なのです。
他にも、お笑い芸人、キャバクラのキャスト、法律事務所に所属する勤務弁護士など、世の中には社員に近い働き方をしながらも「外注」として扱われている職種が数多く存在します。
皆さんの会社でも、一部の業務を外注費に切り替える可能性が潜んでいるかもしれません。
最大のリスク!税務調査で「給与」と認定されないための絶対条件
ここまで大きなメリットを解説してきましたが、この節税策には重大なリスクが伴います。
それは「税務調査で外注費が給与とみなされ、追徴課税されるリスク」です。
税務署は、安易な節税策に対して常に厳しい目を光らせています。
特に、実態は社員と変わらないのに形式だけを外注に変えたと判断されれば、遡って社会保険料の支払いや、控除した消費税の納税を求められることになります。
そうした事態を避けるために、外注費として認められるためには、絶対に遵守すべき2つの手続きがあります。
- ① 業務委託契約書を締結する
口約束は論外です。社員であれば「雇用契約書」ですが、外注であれば「業務委託契約書」の締結が必須です。
その中には、どのような成果物に対して、いくらの報酬を支払うのかという基準を明確に記載する必要があります。 - ② 外注先に確定申告をさせる
給与であれば会社が年末調整を行いますが、外注費(事業所得)を受け取った個人事業主は、自身で確定申告を行い納税する義務があります。
外注先が確定申告をしていない場合、税務署は「本人も給与所得と認識している」とみなし、給与認定する強力な根拠とします。
会社側は、外注先が確定申告を行っているかまで管理すべきです。
「給与」か「外注費」か?税務署が見る具体的な判断基準
契約書を交わし、相手が確定申告をしていれば万全かというと、そうではありません。
税務署は契約書の形式だけでなく、業務の「実態」を重視します。
給与か外注費かの判断は、以下の基準を総合的に見て行われます。
- 成果に応じた支払いか?
外注とは、特定の仕事の完成(成果物)に対して報酬が支払われるものです。
売上ゼロや仕事の失敗があっても一定額が支払われるのであれば、それは給与とみなされる可能性が高くなります。 - 指揮命令権の有無
会社が業務の進め方を細かく指示したり、勤務時間や勤務場所を厳しく管理したりしている場合、それは社員への「指揮命令」と判断されます。
外注であれば、仕事の進め方は基本的に本人の裁量に委ねられ、時間や場所の拘束はありません。 - 仕事道具や経費の負担
社員が使うパソコンや事務用品は会社が支給しますが、外注(個人事業主)であれば、仕事に必要な道具は基本的に自己負担です。
経費をどちらが負担しているかも重要な判断材料となります。
これらの基準に明確な線引きはなく、一つでも当てはまれば即NGというわけではありません。
しかし、実態として限りなく社員に近いと判断されれば、否認されるリスクは高まります。
まとめ:賢い節税は専門家との連携が成功のカギ
今回は、社員への支払いを「給与」から「外注費」へ切り替えることで、社会保険料と消費税の負担を軽減し、会社のキャッシュフローを改善する手法について解説しました。
この手法は、正しく運用すれば絶大な節税効果を発揮する一方で、税務上の明確な基準がないため、税務調査で否認されるリスクと常に隣り合わせです。
経営者としてこの選択肢を検討する際には、
- 業務委託契約書を法的に不備なく作成すること
- 外注先との業務実態が「指揮命令下にある」と見なされないよう管理すること
- 個別の状況に応じた税務リスクを正確に把握すること
が不可欠です。
実行前には、必ず顧問税理士などの専門家に相談し、自社の状況に合わせた最適なプランニングとリスク管理について、十分な助言を受けるようにしてください。