銀行融資で必ず見られる決算書の重要ポイント5選
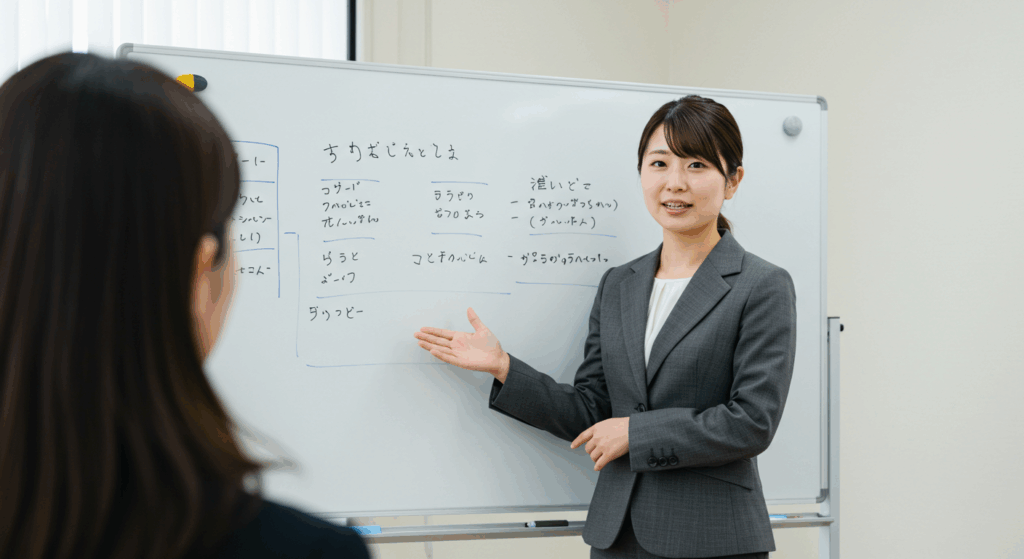
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週金曜日に、経営者なら知っておきたい「銀行融資」についての知識を解説しています。
「銀行に融資の相談に行きたいが、何をどう見られるのかわからず不安だ…」
「銀行員は決算書の細かい数字をたくさん見て、難しい質問をしてくるのでは?」
多くの経営者様から、銀行融資に関するこのような漠然とした不安や疑問を伺うことがあります。
特に、融資の経験が少ない方にとっては、銀行員がどんな視点を持ち、何を考えているのかイメージが湧きにくく、「少し怖い」と感じてしまうこともあるかもしれません。
しかし、ご安心ください。銀行員も私たちと同じ人間です。そして、彼らが融資審査の初期段階で決算書を見るポイントは、実は驚くほどシンプルです。
電卓を片手に難しい顔で長時間決算書を分析する、というよりは、限られた時間の中でまず「事業の全体像」を掴むための重要なポイントをさらっと確認していくのです。
この記事では、銀行が融資審査で必ず見る「5つの勘定科目」について、その見方と理由を具体的かつ実践的に解説します。
この記事を読み終える頃には、銀行員の視点が理解でき、自社の決算書を客観的に見つめ直すヒントが得られるはずです。
銀行員はどこを見ている?融資審査のリアルな現場
まず、銀行員との面談のイメージを少しアップデートしてみましょう。
多くの経営者様は、銀行員が決算書を見ながらその場で詳細な分析を行うと想像されるかもしれません。
しかし、実際の現場では、そういったシーンは意外と少ないものです。
基本的には、担当者は限られた面談時間の中で経営者様から事業の状況をヒアリングし、決算書と合わせて持ち帰ります。
その後、支店内でじっくりと分析し、必要に応じて追加の質問や資料の依頼をします。
つまり、面談の場では、融資の可否を判断するための「大枠」を掴んでいるのです。
そして、その大枠を掴むために、これからお話しする5つのポイントを特に重視して見ています。
融資の可否を左右する!銀行員が瞬時に見抜く5つの勘定科目
それでは、銀行員が決算書のどこを、どのような流れで確認しているのか、具体的に見ていきましょう。
正直なところ、以下の5つの項目を見れば、その会社に融資ができるかどうか、大雑把な判断はついてしまいます。
- 売上・利益
- 純資産合計
- 現預金
- その他資産
- 借入状況
この流れで決算書全体を俯瞰し、会社の「健康状態」を診断していくのです。
もちろん、これ以外にも様々な”ツボ”はありますが、まずはこの5つが基本であり、最も重要なポイントです。
一つずつ詳しく解説していきましょう。
① 事業の「勢い」と「返済能力」の源泉を見る【売上・利益】
まず銀行員が最初に見るのは、損益計算書(PL)の売上と利益です。
これは事業の根幹であり、返済の原資が生まれているかを確認する、いわば会社の「稼ぐ力」を見るための最重要項目です。
銀行員は、以下のような視点でチェックしています。
- 黒字か、赤字か?
言わずもがなですが、利益が出ているかは基本中の基本です。 - 増収増益か、減収減益か?
単年度の数字だけでなく、過去からのトレンドを重視します。
事業が成長しているのか、停滞しているのか、その勢いを見ています。 - 赤字の場合、何期連続か?
一時的な要因による赤字なのか、構造的な問題を抱えているのかを見極めます。
連続赤字であれば、その原因と改善策について、より深い説明が求められます。
会社の業績そのものである売上・利益の状況は、銀行が融資判断をする上での大前提となります。
② 会社の「体力」と「安全性」を示す【純資産合計】
次に銀行員が確認するのは、貸借対照表(BS)の右下にある「純資産合計」です。
これは、総資産(会社の全財産)から負債(返済義務のあるお金)を差し引いた、いわば「会社の本当の財産」です。
自己資本とも呼ばれ、会社の体力を示す重要な指標です。
ここで特に厳しくチェックされるのが、「債務超過」に陥っていないかという点です。
- 債務超過とは?
純資産合計がマイナスになっている状態のこと。
つまり、会社の資産をすべて売り払っても、負債を返しきれない状態を指します。
銀行にとって、債務超過は「倒産リスクが極めて高い危険な状態」と映ります。
いくら利益が出ていても、債務超過であるというだけで、融資のハードルは一気に上がってしまうのが現実です。
それほど、純資産の部は会社の安全性を測る上で重視されているのです。
③ 会社の「資金繰り」の安定性を見る【現預金】
事業の「稼ぐ力(利益)」と「体力(純資産)」を確認したら、次に見るのは足元の「現預金」の残高です。
どれだけ利益が出ていても、手元にお金がなければ会社は立ち行かなくなります。いわゆる黒字倒産のリスクです。
銀行は現預金の残高やその推移から、以下のような点を読み取ります。
- 当面の支払能力は十分か?
急な支払いが発生しても対応できるだけの現金を持っているか。 - 資金繰りは安定しているか?
一般的に、月商の1〜3ヶ月分程度の現預金があると、当面の資金繰りは安定していると見なされやすいです。
手元資金の厚みは、経営の安定性に直結します。
銀行は、不測の事態にも耐えうるキャッシュを確保できているかを慎重に見ています。
④ 資産の「質」を見極める【その他資産】と【借入状況】
現預金と合わせて、資産の中身と負債の状況もチェックします。
これらを見ることで、借りたお金が何に使われ、どのように資産を形成しているのかを推測するのです。
その他資産(在庫、貸付金、仮払金など)
現預金以外の資産項目、特に在庫や貸付金、仮払金などもさらっと確認します。
これらの勘定科目に不自然に大きな金額が計上されている場合、その中身について質問されることがあります。
例えば、長期間売れていない不良在庫や、回収見込みの薄い貸付金、内容が不明瞭な仮払金などが資産として計上されていると、実質的な資産価値は低いと判断され、決算書の見た目ほど体力がないと見なされる可能性があります。
借入状況
現在の借入金がどこから、どれくらいあるのかを確認します。
全体の借入額はもちろんですが、銀行員は「借りた資金が何に使われているか?」という視点を持ち、資産と負債のバランスを見ています。
例えば、借入金が増えている一方で、機械や設備といった生産性を高めるための資産が増えていれば、それは「前向きな投資」と評価されます。
しかし、資産が増えずに借入金だけが増えている場合は、「赤字の補填」や「運転資金の穴埋め」に使われているのではないか、と推測され、ネガティブな印象を与えかねません。
まとめ:自社の決算書を「銀行員目線」で見直してみませんか?
今回ご紹介した5つのポイントは、銀行員が融資審査の入り口で確認する、いわば「会社の健康診断」の基本項目です。
- 売上・利益
事業は順調に成長しているか? - 純資産合計
会社に体力はあるか?(債務超過ではないか?) - 現預金
資金繰りは安定しているか? - その他資産
資産の中身は健全か? - 借入状況
借入金のバランスと使途は適切か?
ぜひ一度、この5つの視点から自社の損益計算書(PL)と貸借対照表(BS)をじっくりと眺めてみてください。
これまでとは違った発見があるかもしれません。
「見方はわかったけれど、自社の決算書がどう評価されるのか判断が難しい」
もしそう感じられたら、ぜひ顧問の税理士さんに相談する時間を作ってみてください。
「銀行は、うちの決算書のこの数字をどう見ますかね?」と問いかけてみるのです。
そうした時間を意識的に作ることで、自社の財務状況を客観的に把握でき、次に打つべき手が見えてくるはずです。

