自社株評価から始める経営者のための究極の節税対策
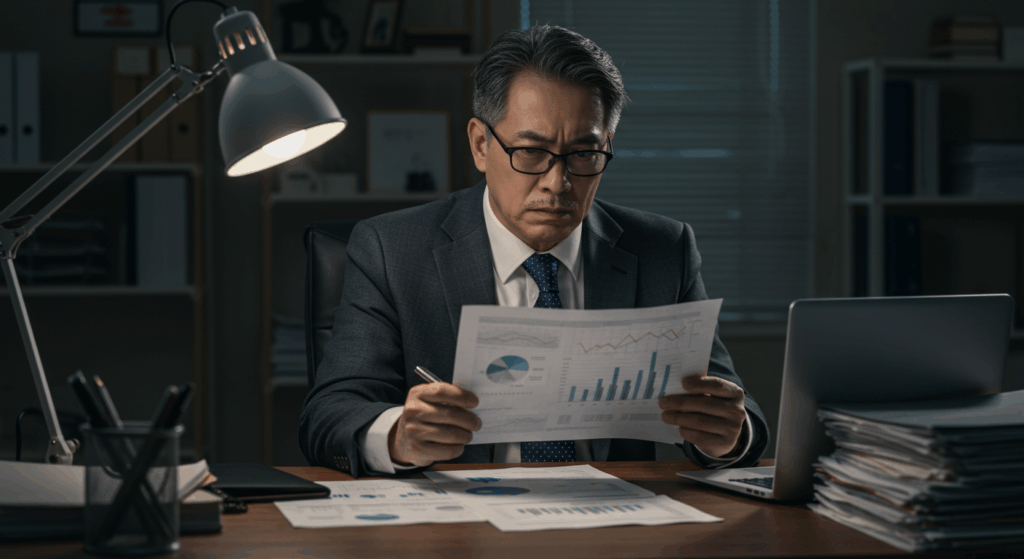
皆さんこんにちは。税理士の中川祐輔です。
毎週水曜日に、経営者なら知っておきたい「節税対策」についての知識を解説しています。
「社長、いきなりですが、自社の『税務上の株価』がいくらかご存知ですか?」
経営者の皆様とお話しする中で、私が必ずお伺いすることの一つです。
しかし、残念ながらほとんどの経営者様が「知らない」とお答えになります。
たとえ顧問税理士がいても、過去に一度でも株価の算定を依頼した経験があるケースは極めて稀なのです。
しかし、この「知らない」という状態が、将来的に多額の損失、特に想定外の相続税に繋がる可能性があるとしたらどうでしょうか。
本記事では、自社の株価を把握することの重要性と、決算書だけでは見えない「本当の企業価値」の姿、そして具体的な対策について、税理士の視点から分かりやすく解説します。
なぜ自社の株価を知らないと「損」をするのか?【税理士が解説する実例】
まずは、自社の株価を知らないことで、いかに大きな不利益が生じる可能性があるのか。
ある経営者様からご相談いただいた際の事例をご紹介します。
【ご相談の概要】
- 経営者
60代後半。数年後の引退を検討中。 - ご家族
お子様はまだ大学生と高校生で、事業承継はまだ現実的ではない。 - 会社状況
親会社(事業会社)と子会社(不動産保有会社)の2社を経営。
どちらも毎期堅調に利益を計上しており、決算書上の純資産額は合計で数億円にのぼる。 - 税務状況
顧問税理士はいたが、株価算定についてはこれまで特に話したことがなかった。
この経営者様から「漠然と相続税が心配なので、何か対策はできないか」というご相談を受け、まず現状を正確に把握するため、私の方で2社の株価を算定してみることにしました。
その結果は、驚くべきものでした。
- 親会社の株価評価額:3億円
- 子会社の株価評価額:▲5億円(マイナス5億円)
なぜこのようなことが起こるのでしょうか。
子会社は多くの不動産を保有していますが、税務上の評価ルールに基づくと、決算書の数字とは大きく乖離することがあります。
例えば、4億円で購入した土地の税務上の評価額が2億円になる、といったケースです。
これは決して経営が不振なわけではなく、あくまで「税法上の評価」が低いということを意味します。
さて、この状態で経営者様が亡くなられた場合、相続財産となる株価はいくらになると思いますか?
答えは「3億円」です。
子会社の評価額はマイナスですが、税務上は「ゼロ円」として扱われます。そのため、親会社のプラスの評価額だけが相続財産として計上されてしまうのです。
これでは、グループ全体の実態とはかけ離れた、不合理な評価額に基づいて多額の相続税が課せられてしまいます。
解決策は驚くほどシンプル!たった一つの手続きで評価額がゼロに
この不合理な状況を解消する方法は、実は非常にシンプルです。それは、親子会社を「合併」させることです。
(もちろん他にも方法はありますが、今回は最も分かりやすい例としてご紹介しています。)
合併して一つの会社にしてしまえば、評価額は単純に合算されます。
3億円(親会社) + (▲5億円)(子会社) = ▲2億円
評価額がマイナスになるため、この会社の相続税評価額は「ゼロ円」となります。
このように、会社の組織構造を少し見直すだけで、将来発生するであろう莫大な相続税負担をなくすことが可能なのです。
なぜ「株価評価」は見過ごされがちなのか?
解決策はシンプルですが、問題の根は深いと考えています。
なぜなら、この状況は以下の二つの要因によって引き起こされているからです。
- 「株価算定」が税理士の日常業務に含まれていないという実情
税理士の主な業務は、月次決算や法人税申告といった、会社の根幹を支える会計・税務です。
これらは非常に重要ですが、それゆえに、将来の相続や事業承継を見据えた『株価算定』は、お客様からご依頼がない限り、日常業務の中で積極的に行うことは少ないのが実情です。
株価算定は、実は非常に専門的で手間のかかる作業であり、通常の顧問契約の範囲とは別の業務としてお受けするのが一般的なのです。 - 経営者様ご自身も、何から手をつけて良いか分からない
「相続税対策」というキーワードが頭にありながらも、「何から始めればいいか分からない」「税理士から何も言われないから大丈夫だろう」と考え、自社の株価評価を依頼するという発想に至らない方がほとんどです。
一般的な相場として、株価算定には30万円程度の費用がかかりますが、将来のリスクを考えれば、決して高い投資ではないはずです。
まずは自社の現状を正しく知ることが、すべての対策のスタートラインとなります。
なぜズレる?決算書と「税務上の株価」が乖離する3つの理由
では、なぜ決算書の純資産額と、税務上の株価はここまで大きく乖離するのでしょうか。その主な理由を3つご紹介します。
不動産などを保有していない情報サービス業のような会社であれば、決算書の数字から概算の評価額を掴むことは比較的容易ですが、以下の資産を保有している場合は特に注意が必要です。
理由①:不動産(土地・建物)
最も大きな乖離を生む要因が不動産です。これは、不動産の「実際に売買される価額(時価)」と「税務上の評価額」が異なるために起こります。
税務上の評価は、土地であれば「路線価」、建物であれば「固定資産税評価額」を基準に行いますが、これらは一般的に時価よりも低く設定されています。
特に昨今のように不動産価格が上昇している局面ではその差は顕著で、例えば都内の不動産を2億円で購入した場合、税務上の評価額が1億円未満になることも珍しくありません。
事例の会社のように、決算書上の価値よりも税務上の評価額が大幅に低くなる(含み損を抱える)ケースもあれば、逆に古い時代に取得した土地が値上がりし、決算書には載らない莫大な含み益を抱えているケースもあります。
理由②:生命保険(積立型)
積立型の生命保険に加入している場合も注意が必要です。
保険料の一部が経費(損金)として処理されるタイプの保険商品は、決算書の資産に計上されていない「含み益」が存在する可能性があります。
例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。
- 年間保険料
100万円 - 契約内容
保険料の半分(50万円)が経費(損金)になる - 決算書上の資産計上額
毎年50万円ずつ増加 - 現在の解約返戻金
900万円 - 決算書上の累計資産計上額
500万円
この場合、決算書には現れていない「900万円 – 500万円 = 400万円」もの含み益が存在することになります。
株価を算定する際には、この400万円も会社の資産として評価に加算されるため、決算書の見た目以上に株価が高く評価されることになります。
理由③:子会社・グループ会社株式
複数社を経営されている場合、子会社株式の評価も非常に重要です。
例えば、資本金100万円で子会社を設立した場合、親会社の決算書(貸借対照表)には、子会社株式の価値は「100万円」としか記載されません。
しかし、その後、子会社の経営が順調に推移し、利益が積み上がって純資産が数億円にまで成長した場合、その子会社株式の税務上の評価額も数億円となり、帳簿上の価額である100万円とは全く異なる金額になってしまいます。
もちろん、冒頭の事例のように、逆に子会社の評価額がマイナスになっているケースもあります。
いずれにせよ、グループ会社を経営している場合は、全社の株価を一体として算定・評価しなければ、全体像を正しく把握することはできないのです。
まずは第一歩!自社の株価を簡易的に把握する方法
「専門家に依頼する前に、まずは自分でざっくりと把握してみたい」という経営者様もいらっしゃるでしょう。
その場合は、インターネット上で公開されている無料のシミュレーションサービスを利用するのも一つの手です。
▼かんたん株価試算
ただし、これまでご説明した通り、不動産や保険、子会社株式などを保有している場合、決算書の数字を入力するだけでは正確な株価は算出できません。
あくまで「参考値」として捉えるようにしてください。
まとめ:最善の策は「決算後」のタイミングで専門家に相談すること
会社の「税務上の株価」は、法人税の計算のように毎年自動的に算出されるものではありません。
だからこそ、経営者の皆様ご自身がその重要性を認識し、意識的にアクションを起こす必要があります。
自社の株価を知ることは、将来の相続税対策や事業承継を円滑に進めるための、不可欠な第一歩です。
それは、会社の健康診断を受けるのと同じくらい重要なことと言えるでしょう。
まずは、会社の決算が確定したタイミングで、顧問税理士の先生に「自社の株価を算定してほしい」とご相談いただくことをお勧めします。
その上で、事業承継や相続に特化したセカンドオピニオンが必要だと感じられた場合は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

